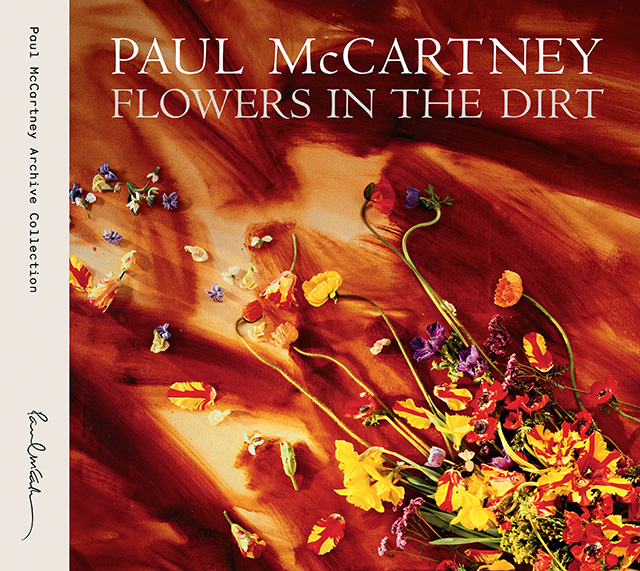| Paul McCartney/ポール・マッカートニー |
| Flowers In The Dirt |
| フラワーズ・イン・ザ・ダート |
| -Paul McCartney Archive Collection- |
|
| 収録曲は下記を参照(デラックス・エディションの仕様を記載) |
|
| スペシャル・エディション:2枚組(CD 1、CD 2) UICY-78242 |
| デラックス・エディション:4枚組(CD 1〜3、DVD)+ダウンロード UICY-78247 |
| (上記型番は日本・ユニバーサルミュージック) |
|
| 発売年月日:2017年3月24日(英国・Capitol) |
| 全体収録時間:54'10"(CD 1) 30'25"(CD 2) 33'01"(CD 3) 75'07"(DL) |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
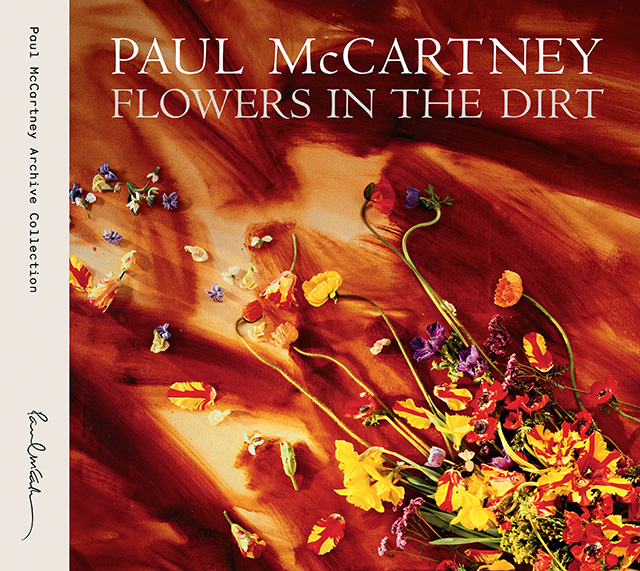 |
| [CD 1] Remastered Album |
| 1.My Brave Face マイ・ブレイヴ・フェイス 3'20" |
| 2.Rough Ride ラフ・ライド 4'45" |
| 3.You Want Her Too ユー・ウォント・ハー・トゥー 3'14" |
| 4.Distractions ディストラクションズ 4'42" |
| 5.We Got Married 幸せなる結婚 4'58" |
| 6.Put It There プット・イット・ゼア 2'12" |
| 7.Figure Of Eight フィギュア・オブ・エイト 3'27" |
| 8.This One ディス・ワン 4'12" |
| 9.Don't Be Careless Love ケアレス・ラヴに気をつけて 3'21" |
| 10.That Day Is Done ふりむかないで 4'22" |
| 11.How Many People ハウ・メニー・ピープル(チコ・メンデスに捧ぐ) 4'16" |
| 12.Motor Of Love モーター・オブ・ラヴ 6'27" |
| 13.Où Est Le Soleil? 太陽はどこへ? 4'46" |
|
| [CD 2] Original Demos |
| 1.The Lovers That Never Were |
| ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー 3'58" |
| 2.Tommy's Coming Home トミーズ・カミング・ホーム 4'09" |
| 3.Twenty Fine Fingers トゥエンティー・ファイン・フィンガーズ 2'27" |
| 4.So Like Candy ソー・ライク・キャンディ 3'29" |
| 5.You Want Her Too ユー・ウォント・ハー・トゥー 2'40" |
| 6.That Day Is Done ふりむかないで 4'16" |
| 7.Don't Be Careless Love ケアレス・ラヴに気をつけて 3'43" |
| 8.My Brave Face マイ・ブレイヴ・フェイス 2'40" |
| 9.Playboy To A Man プレイボーイ・トゥ・ア・マン 2'58" |
| 〜デラックス・エディションのみシークレット・トラック〜 |
| * The Lovers That Never Were[Geoff Emerick Mix] |
| ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー(ジェフ・エメリック・ミックス) 4'05" |
| |
|
| [CD 3] 1988 Demos |
| 1.The Lovers That Never Were |
| ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー 3'49" |
| 2.Tommy's Coming Home トミーズ・カミング・ホーム 5'03" |
| 3.Twenty Fine Fingers トゥエンティー・ファイン・フィンガーズ 2'46" |
| 4.So Like Candy ソー・ライク・キャンディ 3'48" |
| 5.You Want Her Too ユー・ウォント・ハー・トゥー 3'19" |
| 6.That Day Is Done ふりむかないで 4'21" |
| 7.Don't Be Careless Love ケアレス・ラヴに気をつけて 3'24" |
| 8.My Brave Face マイ・ブレイヴ・フェイス 3'29" |
| 9.Playboy To A Man プレイボーイ・トゥ・ア・マン 2'55" |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| [DVD] Bonus Video |
| 〜ミュージック・ヴィデオ〜 |
| 1.My Brave Face マイ・ブレイヴ・フェイス |
| 2.My Brave Face (Version 2) マイ・ブレイヴ・フェイス(ヴァージョン2) |
| 3.This One (Version 1) ディス・ワン(ヴァージョン1) |
| 4.This One (Version 2) ディス・ワン(ヴァージョン2) |
| 5.Figure Of Eight フィギュア・オブ・エイト |
| 6.Party Party パーティ・パーティ |
| 7.Où Est Le Soleil? 太陽はどこへ? |
| 8.Put It There プット・イット・ゼア |
| 9.Distractions ディストラクションズ |
| 10.We Got Married 幸せなる結婚 |
| 〜クリエイティング・フラワーズ・イン・ザ・ダート〜 |
| 1.Paul And Elvis ポールとエルヴィス |
| 2.Buds In The Studio スタジオで芽吹くつぼみ |
| 3.The Making Of 'This One' (The Dean Chamberlain One) |
| メイキング・オブ「ディス・ワン」(ディーン・チェンバレン監督) |
| 〜プット・イット・ゼア〜 |
| 1.Put It There Documentary プット・イット・ゼア・ドキュメンタリー |
|
| [Download only] B-sides,Remixes and Single Edits |
| 1.Back On My Feet バック・オン・マイ・フィート 4'24" |
| 2.Flying To My Home フライング・トゥ・マイ・ホーム 4'15" |
| 3.The First Stone ザ・ファースト・ストーン 4'06" |
| 4.Good Sign グッド・サイン 6'59" |
| 5.This One[Club Lovejoys Mix] |
| ディス・ワン(クラブ・ラヴジョイズ・ミックス) 6'10" |
| 6.Figure Of Eight[12" Bob Clearmountain Mix] |
| フィギュア・オブ・エイト(12インチ・ボブ・クリアマウンテン・ミックス) 5'13" |
| 7.Loveliest Thing ラヴリエスト・シング 4'02" |
| 8.Où Est Le Soleil?[12" Mix] |
| 太陽はどこへ?(12インチ・ミックス) 7'05" |
| 9.Où Est Le Soleil?[Tub Dub Mix] |
| 太陽はどこへ?(タブ・ダブ・ミックス) 4'29" |
| 10.Où Est Le Soleil?[7" Mix] 太陽はどこへ?(7インチ・ミックス) 4'53" |
| 11.Où Est Le Soleil?[Instrumental] |
| 太陽はどこへ?(インストゥルメンタル) 4'28" |
| 12.Party Party[Original Mix] |
| パーティ・パーティ(オリジナル・ミックス) 5'31" |
| 13.Party Party[Club Mix] パーティ・パーティ(クラブ・ミックス) 6'21" |
|
| [Download only] Cassette Demos |
| 1.I Don't Want To Confess アイ・ドント・ウォント・トゥ・コンフェス 2'21" |
| 2.Shallow Grave シャロウ・グレイヴ 2'14" |
| 3.Mistress And Maid ミストレス・アンド・メイド 2'28" |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
アルバム『フラワーズ・イン・ザ・ダート』の制作過程などの解説はこちらをごらんください。
'80年代の低迷期からポールが鮮やかな復活を遂げたアルバム『フラワーズ・イン・ザ・ダート』(1989年)のリマスター盤。2007年にヒア・ミュージックに移籍したポールは、過去に発表したアルバムを「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」というシリーズとしてヒア・ミュージックから再発売するプロジェクトを展開してきましたが、この『フラワーズ・イン・ザ・ダート』はその第10弾にあたります。なお、2016年8月にキャピトル・レコードとの契約締結を発表したポールが翌年までに再移籍したため、本作以降はキャピトルからのリリースとなっています(日本での販売元は引き続きユニバーサルミュージック)。『フラワーズ・イン・ザ・ダート』の大規模な再発売は、1993年のリマスター盤「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズ以来となります。
【発売形態】
今回の再発売では、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』は2種類の仕様で登場しました。1つは、アルバム本編を収録したCDと、アルバム収録曲などのデモ・ヴァージョンを収録したボーナス・ディスクによるCD2枚組の「スペシャル・エディション(Special Edition)」。もう1つは、「スペシャル・エディション」のCD2枚に加えてさらなるデモ・ヴァージョンを収録したボーナスCDもう1枚と、アルバムに関連する映像を集めたDVDが付き、112ページに及ぶハード・カヴァー・ブック(ポールの愛妻リンダ撮影の貴重な写真や、アルバム制作過程の完全解説などを掲載)と32ページのノートブック(ポール手書きの歌詞やメモを掲載)、64ページのフォト・ブック(「ディス・ワン」のプロモ・ヴィデオ撮影時の写真とコメントを掲載)そして32ページの展覧会カタログ(リンダ撮影の写真を掲載)をケースに収めたCD3枚組+DVD1枚組の「デラックス・エディション(Deluxe Edition)」です。「デラックス・エディション」は、インターネットを介して高音質楽曲データ及び、アルバム未収録曲やカセット・デモを含むボーナス・トラックをダウンロードできる特典付き。CDは、すべてのCDプレイヤーで再生可能な高音質CDであるSHM-CDが採用されています(日本盤のみ)。
【収録内容】
では、全ディスクを網羅した「デラックス・エディション」を基に収録内容を見てゆきましょう。まず全仕様共通のCD 1には、1989年に発売されたオリジナルの『フラワーズ・イン・ザ・ダート』が収録されています。曲目は1989年当時のCDに準拠しており、アナログ盤ではオミットされていた「太陽はどこへ?」も収録。一方で、「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズに収録されていたボーナス・トラック3曲は未収録です。全曲がロンドンのアビイ・ロード・スタジオにてデジタル・リマスタリングされていて、過去の再発盤に比べて音質が向上しています。
続いて、全仕様共通のボーナス・ディスクであるCD 2には、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』セッション最初期にエルビス・コステロと録音した共作曲のデモ・テイク(オリジナル・デモ)を9曲収録しています。CD 1と同じくデジタル・リマスタリングが施されていますが、全曲これまで公式では未発表だった音源です。CD 1収録曲と異なり、ブックレットには歌詞は掲載されていません(ただし日本盤には歌詞・対訳が掲載されたブックレットが別途用意されている)。
アルバムの3分の1を占め大いに話題を呼んだエルビスとの共作ですが、このオリジナル・デモは1987年9月〜10月にポールとエルビスがライティング・セッションと並行して2人きりで制作したものです。レコーディングは各曲を書き上げた直後に行われていて、ポールが「まるでフライパンで焼いたばかりのように熱々だよ」と解説するように、「マイ・ブレイヴ・フェイス」「ふりむかないで」といったおなじみの楽曲のまさに生まれたての姿を知ることができます。その大半がギターやピアノのみのシンプルなアコースティック・スタイルである上に、ポールとエルビスのデュエットが全曲でフィーチャーされ、公式テイクとは一線を画したアレンジです。実際のアルバムでは薄められてしまったエルビスのカラーと存在感が前面に押し出され、ポールとの相性のよさが最高の状態で反映されたパフォーマンスはエルビスのファンでなくとも目から鱗でしょう。しかも、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』収録曲はもちろん各自のソロ・アルバムで後に陽の目を浴びた曲や、未発表曲「トミーズ・カミング・ホーム」「トゥエンティー・ファイン・フィンガーズ」までもが飛び出すので興味が尽きません。これらはブートでは既に出回っていて存在自体は知られていましたが、非正規でしか入手できなかったものを高音質で手軽に楽しめる喜びはひとしおです。「ふりむかないで」に至ってはブートでも聴くことのできなかった完全初登場音源。オリジナル・デモでは、「トゥエンティー・ファイン・フィンガーズ」「マイ・ブレイヴ・フェイス」「ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー」辺りが特にお勧めです。なお、「デラックス・エディション」のCD 2には「ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー」の別ヴァージョン(ジェフ・エメリックによるミックスで、ブートも含め完全初登場)が、クレジットのないシークレット・トラックとして追加収録されています。
そして、「デラックス・エディション」のみのボーナス・ディスクであるCD 3には、エルビスとの共同プロデュースのもと進められた1988年初頭のセッションでのアウトテイク(1988デモ)を9曲収録しています。こちらもすべてデジタル・リマスタリングが施されています。CD 2のオリジナル・デモと同じ曲目・曲順の1988デモは曲想がより練られたバンド・サウンドで、「デモ」と銘打たれつつこのまま発表されても遜色ない仕上がりなのが特徴です。また、「ユー・ウォント・ハー・トゥー」「ケアレス・ラヴに気をつけて」など公式テイクに流用された要素を持つ曲がある反面、「プレイボーイ・トゥ・ア・マン」ではこの時期だけのアレンジを聞かせていて、スタジオでの試行錯誤の跡を随所に見て取れます。そんな興味深い音源が全曲、今までブートにも一切流出していなかったのですから、世紀の大発掘と言っても過言ではありません。ぜひ各ヴァージョンを聴き比べて、オリジナル・デモ→1988デモ→公式テイクと完成形に向かって変遷してゆくのを体感してみましょう。1988デモの聴き所は「トミーズ・カミング・ホーム」「ケアレス・ラヴに気をつけて」「プレイボーイ・トゥ・ア・マン」辺りでしょうか。
最後に、「デラックス・エディション」のみ付属のDVDには、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』関連の映像が収録されています。既に発表されているものと、これまで公式には未発表だったものとで構成されています。メニューは3つに分かれていて、うち「ミュージック・ヴィデオ」はアルバム発売当時に制作された8曲のプロモ・ヴィデオを全10ヴァージョン収めています。「ディス・ワン(ヴァージョン2)」「幸せなる結婚」など実に6作が初ソフト化。公式プロモ・ヴィデオ集「ポール・マッカートニー・アンソロジー(The McCartney Years)」に収録されていた残り4作に関しても、ここでは1989年〜1990年当時に忠実な画面サイズで収録されています(一方で従来品ほどは画質向上を徹底していない)。惜しむらくは、ポールのみに焦点を当てた「プット・イット・ゼア」の別ヴァージョンが割愛されていることでしょうか・・・。
続く「クリエイティング・フラワーズ・イン・ザ・ダート」では、レコーディング・セッションやプロモ・ヴィデオ制作の舞台裏に迫った3つのミニ・ドキュメンタリーを見ることができます。エルビスと一緒に1988デモを録音する姿を捉えた「ポールとエルヴィス」、その後仕切り直されたセッションを追った「スタジオで芽吹くつぼみ」と、プロモ・ヴィデオ「ディス・ワン(ヴァージョン2)」の撮影をポールとディーン・チェンバレン監督の解説を交えて振り返るメイキング映像で、いずれもほとんどのシーンが初公開でレアな映像が満載。関係者以外は普段見る機会のない、ポールたちが和気藹々と仕事をこなす様子を楽しめます。そして極めつけがドキュメンタリー作品「プット・イット・ゼア」。来るワールド・ツアーに備えバンドのメンバーと共に行ったリハーサルより、新曲からビートルズ・ナンバーそれにオールディーズのカヴァーまで取り上げた演奏シーンと、ポール本人へのインタビューをふんだんに盛り込んだ約1時間の作品です。1989年にVHS及びLDとして一般発売され後年DVD化も済ませていましたが、今回のフル収録で個別に入手する手間が省けるのはありがたいですね。チャプターが約10分おきにしか設定されておらず、各曲の頭出しができないのは難点でしょうか。
これまでの「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズではボーナス・ディスクに収録されていたアルバム未収録曲/関連楽曲は、今回は専用のダウンロード・カード(「デラックス・エディション」のみ付属)に印字されたコードを使用し、公式サイトから無料ダウンロードする形式で聴くことができます。この方針転換について、マネージャーのスコット・ロジャーは「ディスク枚数が増えすぎるのをポールが望まなかったため、アルバムの歴史を語る上で核とならない音源はCDに収録していない。一方、ポールは昨今のデジタル配信市場の急成長に可能性を見出している」と説明していますが、いつまでも手元に残る物理メディアでなく、突然のサービス終了もありえるデジタル・ダウンロード(しかも高価な完全生産限定盤の購入者が対象)が採用されたことにはファンの間で批判の声が相次ぎました。ポールの場合、アルバム未収録曲やリミックス・ヴァージョンにもクオリティの高いものが多いので、そうした佳曲への門戸を閉ざしてしまうのは大変もったいないですし、今回の措置で初CD化を再び逃してしまった曲が散見されるのも残念でなりません。オリジナル・デモと1988デモは1枚のCDにまとめても十分収まるので、ポールの懸念も解消しつつCD化できたはずなのに・・・。ボーナス・ダウンロード・トラックも全曲デジタル・リマスタリングされていますが、ブックレットには歌詞(日本盤は対訳も)は掲載されていません。
既発表のものから見てみると、「バック・オン・マイ・フィート」「フライング・トゥ・マイ・ホーム」「ラヴリエスト・シング」はアルバムと同時期にレコーディングされシングルのB面/カップリングに収録された曲です。この3曲の収録により、「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズでのボーナス・トラックは全曲網羅したことになります。また、同じくアルバム未収録曲「ザ・ファースト・ストーン」「グッド・サイン」「パーティ・パーティ」や、「ディス・ワン」「フィギュア・オブ・エイト」「太陽はどこへ?」の各種リミックスは今までシングルや来日記念盤『フラワーズ・イン・ザ・ダート -スペシャル・パッケージ-』(廃盤)でしか聴くことができませんでしたが、格段に手に入れやすくなりました(ただし「グッド・サイン」は当時のシングルとは演奏時間が異なる)。さらに、数量限定のプロモ・シングルでのみ出回った超レア・アイテム「パーティ・パーティ(クラブ・ミックス)」が初商品化を果たしています。レコーディング時期が異なるものを除いても、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』と同時期に発表された曲は他にも『スペシャル・パッケージ』の新曲「P.S.ラヴ・ミー・ドゥ」、「フィギュア・オブ・エイト」のエディット・ヴァージョン、「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」「ラフ・ライド」のヴィデオ・ヴァージョンがあり、特に前者の収録漏れは痛いですが、聴き所は一通り押さえてあります。
残る3曲が未発表音源で、1987年にポールとエルビスがライティング・セッション中に録音したデモ・テイク(カセット・デモ)です。オリジナル・デモと同様に書き上げたばかりの新曲をアコースティック・ギターで披露していて、2人の息の合ったデュエットが魅力的ですが、いずれもブート含め完全初登場。中でも「アイ・ドント・ウォント・トゥ・コンフェス」は、タイトルすらろくに知られていなかったという秘密に満ちた1曲で大変貴重です。欲を言えば、ブートで聴くことのできるその他のアウトテイク(「モーター・オブ・ラヴ」「ニュー・ムーン・オーヴァー・ジャマイカ」のデモ・ヴァージョンや、5分ある「フィギュア・オブ・エイト」の完全版など)も引っ張り出してきてほしかったですが・・・膨大なテープを整理してかき集めてくれたポールには素直に敬意を表したいですね。なお、今回の再発売に合わせて、ポールの公式サイトでは「ディストラクションズ(デモ)」「ディス・ワン(デモ)」「バック・オン・マイ・フィート(デモ)」という3曲の未発表音源が無料公開されていて、こちらも注目です(「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズには未収録)。
「デラックス・エディション」にはハード・カヴァー・ブックとノートブック、フォト・ブック、展覧会カタログが付属しています(ディスクは見開き式の厚紙に別途収納されている)。112ページ型ハード・カヴァー・ブックでは、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』が完成するまでをポール本人やエルビス・コステロ、ヘイミッシュ・スチュアートなどの関係者へのインタビューと、貴重な写真・資料で詳しく知ることができます。エルビスとはどのように共作曲を書いていったのか?複数のプロデューサーの個性をセッションでどう生かしたのか?ファンなら誰もが知りたかったことを教えてくれます。ファンクラブ会報「クラブ・サンドイッチ」より、アルバムやプロモ・ヴィデオを詳細に特集した記事が転載されているのはうれしい所。また、アルバムのアートワークに使用されたものも含め主にリンダが撮影した多くの写真や、当時発売されたシングルのジャケットなども掲載され、視覚的にも制作過程をうかがい知ることができます。巻末にはアルバム本編の収録曲の歌詞と、ボーナス・トラックを含めた全曲の詳細なレコーディング・データがあります。
32ページ型ノートブックには、ポールが作詞中に作った手書きの歌詞シート(12曲分)や、日々のアイデアをつづったメモが掲載され、歌詞の変遷だけでなくアレンジの煮詰め方まで垣間見ることができます。複製の付録として、ポール直筆の歌詞シート3枚(「ディス・ワン」「ディストラクションズ」「フィギュア・オブ・エイト」各1枚)と、ポールが描いたシングル「プット・イット・ゼア」のジャケット用イラスト1枚、それにエルビスがポールに宛てて書いた手紙1通(1987年のものと思われる)が挟み込まれているのも見逃せません。
64ページ型フォト・ブックは、2種類制作された「ディス・ワン」のプロモ・ヴィデオを特集したもので、これまで見ることのできなかった両ヴァージョンの撮影当日の写真を多数掲載しています。また、エスニックな世界広がる「ヴァージョン1」の監督ティム・ポープと、サイケデリックに仕上げた「ヴァージョン2」の監督ディーン・チェンバレンがコメントを寄せていて、それぞれポールとの出会いから現場でのエピソードまで懐かしい思い出を感慨深く語っています。
そして最後に、32ページ型展覧会カタログには、アルバム・ジャケット用にリンダが撮影し、1989年11月〜12月にロンドンのメイヤー・ギャラリーで展示されたチバクローム写真を20点収めています。実際にジャケットに採用されたもの以外の作品も、みな色鮮やかで情熱的。巻末のコメントでは、ジェームズ・メイヤー(メイヤー・ギャラリー代表)とダニー・ポープ(写真現像を担当)がリンダの写真家としての側面や、印刷にあたっての工夫について振り返ります。
【管理人の評価】
以上見てきたように、全曲がデジタル・リマスタリングされて高音質に生まれ変わっただけでも、「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズの『フラワーズ・イン・ザ・ダート』は以前の再発盤に比べて断然お勧めできます。「スペシャル・エディション」では未発表のオリジナル・デモも追加収録されています。しかしより強力で、よりお勧めなのは「デラックス・エディション」。初登場の1988デモが収録されたことでエルビス・コステロとのセッションを完全網羅できますし、アルバム未収録曲や未発表のカセット・デモを無料ダウンロードでき(「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズの代用になります)、入手困難なものを多く含んだ貴重な映像を収録したDVDに、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』の歴史を詳細に凝縮した4つのブックまでも付いてくるのですから、ファンなら必携のアイテムです!完全生産限定盤のため今後入手が困難になる上、他の仕様に比べて価格も高めですが(さらに輸入資材の関係で、日本盤の「デラックス・エディション」はリリース前に発売日の延期と1万円もの値上げに遭っている)、苦労して手に入れる価値は十分あります。「なかなか手を出しづらいと思っている」、あまりディープに聴き込んでいない方や、これからポールのソロ・アルバムを集めようとしている方も、せめて「スペシャル・エディション」を入手するようにしましょう。
『バンド・オン・ザ・ラン』に始まり『フラワーズ・イン・ザ・ダート』までもグレードアップして甦らせた「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズでは、キャピトルに移籍した今後もポールの旧作品を継続して再発売するとのこと。数々の名盤が新たなマテリアルと共に帰ってくることを皆さんで期待しましょう!
アルバム『フラワーズ・イン・ザ・ダート』発売20周年記念!収録曲+aを管理人が全曲対訳!!
【曲目解説】
CD 1
曲目解説はこちらをごらんください。
CD 2
1.ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー
本ボーナス・ディスクには、1987年9月〜10月にポールとエルビス・コステロがサセックスにあるポールの私設スタジオ「ホッグ・ヒル・ミル・スタジオ」で制作したデモ・ヴァージョン(オリジナル・デモ)を9曲収録している。この頃精力的に共作に取り組んでいた2人は、スタジオの階上にあるオフィス部屋でライティング・セッションを行い、曲が完成するとすぐさま階下のスタジオに入りデモを録音するというルーティーンを取っていたが、まさにその時の音源である。うち「ふりむかないで」を除く8曲は'90年代にテープが外部に流出し、「The McCartney/MacManus Collaboration」などのタイトルでブート化されてきたためマニアの間ではすっかり知られていたが、30周年を迎える今回初めて公式発表されるに至った。
「ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー」は『フラワーズ・イン・ザ・ダート』への収録を見送られ、次作『オフ・ザ・グラウンド』(1993年)でリメイクされた曲。このオリジナル・デモではポールがアコースティック・ギターを、エルビスがピアノを弾いている。曲構成は同じだが、キーは公式テイクより全音高い。とりわけ耳に残るのはポールのヴォーカルであろう。バラード・タイプの曲で、なんと!荒々しく腹の底から叫ぶように歌っているからだ。エルビスにとっては衝撃だったようで、ビートルズ・ナンバー「アイム・ダウン」を引き合いに出して「ポールのソロ・キャリア史上屈指の名演」と絶賛している。これを聴いてしまうと公式テイクがおとなしすぎて物足りなく思えてしまう・・・ポールのロック魂がひしひし伝わるテイクです。なお、このデモはポールがDJをつとめたラジオ番組「ウーブ・ジューブ」(1995年)で一部抜粋して放送されたことがある。ブートではアコギが「ジャン!」と締めて終わるが、ここではその1音はカットされている。
2.トミーズ・カミング・ホーム
ポールとエルビスの共作のうち、今回のリマスター盤で初めて陽の目を浴びた3曲の未発表曲の1つ。ただし、この曲に関してはエルビスが2014年6月にライヴで一度だけ披露していた。エルビスのアイデアによる物語風の詞作で、戦死したトミーの未亡人が行きずりの男に誘惑される光景を皮肉交じりに描く。第4節の「ピカーディの涙(tears of Picardy)」は音楽用語「ピカルディ終止(tierce de Picardie)」のもじり。オリジナル・デモはポールとエルビスがアコースティック・ギターを弾きながら終始デュエットするだけのシンプル極まりない仕上がりで、牧歌的なフォーク・ソングのようにも聞こえる。曲構成は粗方完成しているが、イントロとエンディングはこの時点では存在しない。ライヴ・レコーディングならではの、2人の歌い回しの微妙な違いに耳を澄ましてみるのも一興であろう。
3.トゥエンティー・ファイン・フィンガーズ
続いてもこれまで未発表だった曲で、ブートでは「Twenty-Five Fingers」と誤記されていた。ノリのいいロックンロールで、エルビスによると「パッズ・ポウズ・アンド・クロウズ」(エルビスのアルバム『スパイク』収録)と同日に書かれたという。この曲はアコースティック・ギターのほかに、一連のオリジナル・デモでは例外的にドラムスが加えられ(演奏は恐らくポール)、通常のバンド・スタイルに近くなっている。後の1988デモと比べてアレンジが練られていない分、中途半端かつ乱暴にカウントが導く歌い出しや、ミドルエイト以外ぶっ通しで疾走してゆくリズムがより痛快だ。ポールとエルビスも全編にわたって一緒に歌い続ける。エンディングが決まっていないため、ここでは“Wish you were mine”を繰り返しながらフェードアウトする。個人的にはブートで聴いた時からお気に入りだったので、今回公式発表されたのが特にうれしいですね。
4.ソー・ライク・キャンディ
この曲は最終的にエルビスのソロ・ナンバーとして仕切り直され、アルバム『マイティ・ライク・ア・ローズ』(1991年)に収録された。同年にはアルバムからの第2弾シングルに選ばれている(チャート・インせず)。また、エルビスのライヴでは息の長い曲である。キャンディという名の少女との失恋を歌ったほろ苦いラヴ・バラード。このオリジナル・デモでは再び2本のアコースティック・ギターのみの伴奏で、メロディの持つ陰鬱なテイストを強調している。これまたポールとエルビスが終始一緒に歌い、主旋律をカヴァーするエルビスとその上を行くポールとの対比が美しい。イントロがないものの、構成は既にほぼ公式テイクと同じである。一方で、エンディングは5回目のタイトルコールであっけなくフェードアウトしてしまう。ブートでは終盤ステレオの中央がずれて音が不安定になるが、ここでは最後まで問題なく聴くことができる。
5.ユー・ウォント・ハー・トゥー
『フラワーズ・イン・ザ・ダート』では唯一ポールとエルビスのデュエットを楽しめる曲だが、オリジナル・デモも2人の息の合ったデュエットがフィーチャーされている。シニカルな返答の部分を誰が歌うかで二転三転したことが知られているが、このデモでは公式テイク同様エルビスが担当(一部をポールも歌う)。中間部をエルビスとポールの輪唱にする面白い試みは、完成形に至る過程でボツになってしまった。他にも、回転木馬風のイントロとエンディングの欠落や、中間部での合間の拍数といった公式テイクとの様々な違いが見られる。使用楽器はここでもアコースティック・ギター2本のみ。ブートでは最後の1音にアコギと思われる雑音が入っていたが、公式発表にあたり消されている。
6.ふりむかないで
この曲だけは、一連のオリジナル・デモを収録したブートから漏れていたためこれまで一切聴くことができなかった。まさに今回完全初登場を果たしたレア音源である。「ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー」と同じく、ピアノとアコースティック・ギターによるシンプルな演奏で聞かせる。エルビスの祖母を題材としエルビスの貢献度が高い1曲で、エルビスがリード・ヴォーカルを取るヴァージョンもザ・フェアフィールド・フォーとの共演(1997年)として残されているが、このデモは初公開となるポールとエルビスの対等なツイン・ヴォーカルであり、その点でも貴重と言えよう。2人がそれぞれ、公式テイクでは採用されていないメロディ・ラインを歌ったり歌わなかったりするので、公式テイクに聴き慣れている耳には新鮮に響く。曲構成は固まっているものの、エンディングはタイトルコールが2度余分に増えている。
7.ケアレス・ラヴに気をつけて
オリジナル・デモから公式テイクへと最もドラスティックに姿を変えたのがこの曲。無機質なシンセ・サウンドが特徴的な公式テイクに対し、このデモは純粋なアコースティック・ギター弾き語りで印象が全く異なる。しかもテンポを大幅に落としゆったりと演奏していて、まるで暖炉の前に腰かけ歌うのを聴いているかのようである(キーも半音高い)。ポールとエルビスのデュエット・ヴォーカルも奇をてらわず、公式テイクに漂う不気味さは感じられない。歌詞を反映したメロとサビの温度差は曖昧ですが、曲本来の魅力を再確認できるシンプルさで、公式テイクにとっつきにくさを覚えた方もネガティブな先入観が払拭されることでしょう。曲が始まる前の息を吸う音は、ブートではカットされていたため今回が初登場。
8.マイ・ブレイヴ・フェイス
シングル・ヒットとなったこの曲もまた、オリジナル・デモではポールとエルビスがアコースティック・ギターを弾きながら2人で歌うスタイルである。ポップで若々しさみなぎる公式テイクにも負けない溌剌としたデュエットが楽しく、上機嫌で録音に臨む姿が容易に想像できる。曲構成は公式テイクと大体変わりないが、出だしや節間のつなぎにタイトルコールを加えるアレンジはまだない。逆に、後半“housewife”を強調する一ひねりが確立されているのは面白い。エンディングは、ブートではなぜか第1節の末尾に連結された上でフェードアウトしていたが、ここでは元々の音源通りにタイトルコールできれいに締めくくる。また、ブートでは第1節で音が途切れがちになっていた箇所も問題なく楽しめる。オリジナル・デモの中でも私が特にお気に入り&お勧めの1曲です。冒頭の軽妙な掛け声もポイント高いですね!
9.プレイボーイ・トゥ・ア・マン
「ソー・ライク・キャンディ」と同じく『フラワーズ・イン・ザ・ダート』セッションでお蔵入りになった後、エルビスがポール抜きで再録音し、『マイティ・ライク・ア・ローズ』で発表した曲。同作ではエルビス自作の小曲「インタールード:クドゥント・コール・イット・アンエクスペクティッドNo.2」とのメドレー形式で登場する。ポールのポップ・センスとエルビス特有のパンク風味を融合させたようなロック・ナンバーだ。このオリジナル・デモで使用されている楽器はピアノとアコースティック・ギターで、前者が演奏を引っ張っている。後続の1988デモと公式テイクではピアノは一転して脇に回っているのでなかなか興味深い。またまたポールとエルビスが対等にデュエットし、どちらがリード・ヴォーカルか判別できないほどのユニゾンを聞かせる。
〜デラックス・エディションのみシークレット・トラック〜
* ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー(ジェフ・エメリック・ミックス)
「デラックス・エディション」では、「プレイボーイ・トゥ・ア・マン」が終わった後に18秒の無音部分を挟んでこの曲が収録されている(前曲と同じトラックに収められているため頭出しはできない)。タイトルがクレジットされていないシークレット・トラックで、レコーディング・データもブックレットに掲載されていないので詳細は不明だが、特典でダウンロードできる高音質楽曲データでは「ジェフ・エメリック・ミックス」と銘打たれていることから、ジェフ・エメリックがミキシングに携わったのは確実と言える。エメリックはご存知の通りビートルズ以来ポールの作品を幾度となく手がけてきた名エンジニアで、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』でも収録曲の一部を任せられていた。
このミックスは今回が初の公式発表となる音源である上に、これまでブートでも出回っていなかった。ベースになっているのはオリジナル・デモ(本ボーナス・ディスクの1トラック目)で、ここではポールとエルビスのヴォーカルはそのまま残しつつ、ピアノをよりシャープな音色で手数の多い演奏に差し替えている。ざっと聴き比べた限りでは、アコースティック・ギターはオリジナル・デモと同一であろう。さらに、オリジナル・デモにはなかった要素として多重コーラスと、公式テイクでも取り入れられる力強いドラム・ビートがオーバーダブされている。曲の最後には、“All of the clocks have run down(時計はすべて止まった)”という一節をイメージさせる時計の針の音も。オリジナル・デモでのポールのロック・ヴォーカルが絶品なだけに、ラフさも改善されたこのミックスで発表に至らなかったのが非常に惜しまれますね・・・。個人的には公式テイクの何倍もこちらの方が好きです。
CD 3
1.ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー
「デラックス・エディション」のみ付属しているCD 3には、1988年1月〜3月にポールとエルビスが9つの共作曲をバンド・スタイルで正式にレコーディングした際のアウトテイク(1988デモ)が収録されている。2人の共同プロデュースのもとホッグ・ヒル・ミル・スタジオで行われたセッションには、後にポールのツアー・バンドの一員となるヘイミッシュ・スチュアート(ギター)とクリス・ウィットン(ドラムス)に加え、デヴィッド・ボウイなどのサポートで有名なケヴィン・アームストロング(ギター)が招集された。キーボードも多用されているが、誰が弾いているかはクレジットがない。1988デモはポールとエルビスの音楽的見解の相違が顕在化したことから未完成のまま棚上げされ、今回のリマスター盤で陽の目を浴びるまでずっとお蔵入りの憂き目に遭っていた。全曲がブートにも流出したことのないレア音源で、極端に情報が少なく謎だらけだったセッションの全貌はマニアにとっても新鮮で大変興味深い。
「ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー」はこの段階でも公式テイクよりキーが全音高く、ベース、ドラムスと控えめなエレキ・ギターが追加されるもののオリジナル・デモの延長線上にある。1988デモは総じて公式発表にも耐えうる程度に作り込まれているのが特徴だが、この曲に関してはポールが1993年のインタビューで「本当に上手く行かなかった」と振り返るように、軽く流すような演奏にとどまっている。ポールのヴォーカルも、抑え気味な序盤から徐々に叫ぶような歌い方を交えてゆくが、オリジナル・デモでのテンションをイマイチ再現できていない。エルビスは不参加で、そのせいかオリジナル・デモで聴かれたコーラスは一切なし。この後、クレア・フィッシャーがスコアを書き下ろしたオーケストラ・アレンジも試されたそうだがボツとなり、結局は『オフ・ザ・グラウンド』で根本的にアプローチを見直して一からリメイクされる運びになった。
2.トミーズ・カミング・ホーム
オリジナル・デモは純粋なアコギ弾き語りだったが、1988デモはゲート・リバーブをかけたドラムスによるリズムにのせてシンセサイザーやチューブラーベルが色を添える明るいポップ・ソングに進化し、がらりと印象が様変わりしている。さらにモダンな音処理を施せば『スパイク』に収録されても違和感なさそうだ。若干整理されているがエルビスとのデュエットは健在で、絶妙にブレンドされたハーモニーを堪能できる(ポールの「ラララ・・・」というコーラスが新たに追加されている)。イントロとエンディングも完成し、歌詞の舞台である列車内の喧噪を想起させる効果音や掛け声が印象的。ブートでオリジナル・デモに聴き親しんでいたファンなら殊更驚愕するヴァージョンですが、私の場合この1988デモが嗜好にドンピシャで、この曲に全く関心のなかった昔とは打って変わっていまや病みつきです(笑)。
3.トゥエンティー・ファイン・フィンガーズ
既にオリジナル・デモの時点で準バンド・スタイルだった曲にもかかわらず、1988デモではそのアレンジを踏襲せずコミカル寄りの路線に転換。オリジナル・デモの醍醐味たる勢いこそ弱まったものの、今回はイントロにも持ってきた“Think it over, think it over baby”という勇ましいコーラス(ポールとエルビス、ヘイミッシュ、ケヴィンが担当)とその後のギター・フレーズが楽しい。終盤の“Wish you were mine”の繰り返しに呼応するタイトルコールもおふざけ度増し増しだ。リード・ヴォーカルはポールで、エルビスが要所でバッキング・ヴォーカルを入れる。ミドルエイトにはピアノとスネア・ドラムをフィーチャー。当初はエンディングが未定だったが、1988デモはフェードアウトせずかっこよく締めている。
4.ソー・ライク・キャンディ
ポールが単独でリード・ヴォーカルを取るという、その事実も今まで知られていなかった驚きのヴァージョン。1988デモは、エルビスがソロ・ヴァージョンを録音するにあたり参考にしたであろう多くの共通点(「ジャーン」1音のみのイントロ、チェレスタの使用、アウトロでの追っかけコーラス)が見受けられる反面、キーを半音上げテンポをかなり速めに改めている点が(オリジナル・デモとも)決定的に異なる。エルビス・ヴァージョンはメロトロンなど様々なキーボードを重ねているが、このデモではステレオの中央と左右に分散して配したギター(エレクトリック2本とアコースティック1本)中心にさっぱりと聞かせる。コーラス面でも違いがちらほらあり、サビには他のヴァージョンにないエルビスのシャウト・ヴォーカルが入る。そのサビがいささか元気すぎるのが引っかかりますが、メランコリックな音作りのメロはなかなかいい味出していて正解だと思います。
5.ユー・ウォント・ハー・トゥー
この曲の1988デモは一部が公式テイクに再利用されていて、それゆえにデュエットの割り振りを始め大まかな所は公式テイクに似ている。回転木馬風のイントロとエンディングも既に出来上がっている(ただし音量が小さく、エンディングはビッグバンドの演奏がかぶらない)。曲前半はそのまま公式テイクの土台となり、(エフェクトをかける前で生々しく響くが)ヴォーカルも同一のようだ。一方、公式テイクに採用されなかった中盤以降はまだまだ粗削りで、中間部での輪唱や1回余分なブレイクなどはオリジナル・デモの面影を残す。第3節では、公式テイクだとポールとエルビスがハイテンションで掛け合う箇所も他と同様に落ち着いている。全体的に見ると、この後オーバーダブされる数々のきらびやかなシンセを欠くため、バンド・サウンドであることが強調されたミックスだ。最終段階でオフにされてしまったギター・フレーズも聴くことができ、フェードアウトが遅いおまけ付き。
6.ふりむかないで
「ユー・ウォント・ハー・トゥー」に続き、この曲も公式発表されたものは1988デモが基になっており、こちらは全編が同じテイクである。ポールのリード・ヴォーカルとヘイミッシュのバッキング・ヴォーカルも全く同じ(やはりエフェクトがなく生々しい)。逆に、この時点では葬送曲を意識したブラス・セクションと、オルガンなどのキーボード類が追加される前の状態で、コーラスも含め圧倒的に音が薄い。公式ヴァージョンはニッキー・ホプキンスがピアノを弾いているが、1988デモのピアノはそれとは別の演奏の模様(誰が弾いているかは不明)。サビでは公式ヴァージョンに登場しないギター・フレーズが左側から聞こえる。ちなみに、ポールとエルビスの間で曲想の乖離がとりわけ激しく、本デモのセッション中にヒューマン・リーグ風のシンセ・サウンドを提案してきたポールにエルビスがひどく気分を害され、2人でレコードを作ることに限界を感じたという逸話が残る。
7.ケアレス・ラヴに気をつけて
この曲についてポールは「エルビスと制作したテープが今一つだったので再録音したけど、ヴォーカルは気に入っていたから流用した」と発表当時コメントしていたが、これがその当初のヴァージョン。発言を裏付けるように、ポールが1テイクできめたリード・ヴォーカルと4声のハーモニー(ポール、エルビス、ヘイミッシュ、クリス)は公式ヴァージョンと完全に一致する。大きく異なるのがバッキング・トラックで、公式ヴァージョンが第1節&第3節の冒頭を除きフル・バンドであるのに対し、1988デモではメロはパーカッションのみ、サビはドラムス、ベースとわずかなキーボードのみが使用され、演奏もほぼ総入れ替えと言ってよい。悪夢をイメージさせる公式ヴァージョンの無機質かつ不気味な雰囲気も捨て難いですが、1988デモのせわしない音作りは歌詞の主人公の焦燥感を上手く表現できていますし、'80年代臭も軽減されて聴きやすくなり、個人的にはこの曲で今一番好きなヴァージョンだったりします。
8.マイ・ブレイヴ・フェイス
『フラワーズ・イン・ザ・ダート』に収録された他の共作曲では1988デモを何らかの形で再利用したのとは対照的に、8ヶ月後にすべて録り直したリメイク・ヴァージョンが公式テイクとなったため、一度却下されたこの1988デモが顧みられることはなかった。とはいえ、この時点で基本的な構成やアレンジは固まり、ややルーズな演奏ながら公式テイクをほうふつさせる。これまた'80年代特有の豪華絢爛な装飾が足される前段階で、公式テイクほどしつこくない味付けだ。最大の魅力は全編を通して披露されるポールとエルビスの相性抜群なツイン・ヴォーカルで、公式テイクではエルビスが不在なだけに余計うれしい。その2人と共にコーラスを入れるヘイミッシュはセミ・アコースティック・ギターを弾いている。'60年代っぽい音色のオルガンや、後半“As I clean away another untouched TV dinner”の箇所だけハーフ・タイムになるドラム・パターンもユニーク。
9.プレイボーイ・トゥ・ア・マン
1988デモはポールがメインで歌いっぱなしという事実上のソロ・ヴァージョンで、コアなファンですらその存在を知る由もなかった。エルビスがソロで取り上げた際はオリジナル・デモを手本にしたパンキッシュな仕上がりだったが、ここではストレートなギター・ロックに生まれ変わっていて、キーが半音高いのもあいまってまるで別の曲みたい。ヴォーカル・スタイルもまたストレートで、突き抜けるかのような高揚感をサビに与えている(なお、エルビス・ヴァージョンは酔っ払いさながらのひねくれた歌い方である)。演奏面では、ポールがビートルズ時代に愛用し、この頃エルビスの助言を受けて久々に手にしたヘフナーのバイオリン・ベースを弾いている点は特筆すべきであろう。「マイ・ブレイヴ・フェイス」のように跳ねるようなプレイが心地よい。アウトロ前の1回を除きドラム・ビートが途切れないエルビス・ヴァージョンと比べ、1988デモは節が終わるたびにブレイクを挟むのも特徴的だ。
DVD
〜ミュージック・ヴィデオ〜
1.マイ・ブレイヴ・フェイス
メニュー「ミュージック・ヴィデオ」には、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』発売当時に制作された8曲分のプロモ・ヴィデオを収録している。先行シングル「マイ・ブレイヴ・フェイス」のプロモ・ヴィデオは、1990年度ブリット・アワードの最優秀ブリティッシュ・ヴィデオ賞にノミネートされるなど割と有名な作品である。監督はロジャー・ラン。ポール関連の品々を手に入れるためにはどんな手段も厭わないコレクターの日本人男性が登場し、窃盗を繰り返した末にポールのヘフナー・ベースを盗んで逮捕されるという筋書きは、「9年前の日本での逮捕劇への意趣返しか?」「何でも買いあさるバブル期の日本人を皮肉った?」と物議を醸した。これについてポールは「監督の人選で他意はなく、何人でもよかった。警官役も日本人にするよう強く要請したよ」と釈明している。演奏シーンは1989年4月10日と翌11日にロンドン(リバプールという説もあり)で撮影され、結成されたばかりのツアー・バンドのメンバー(ポール、リンダ、ヘイミッシュ、クリス、ロビー・マッキントッシュ、ポール・“ウィックス”・ウィッケンズ)が映像作品では初めて一堂に会した。
先述のコレクターが「私はポール・マッカートニーのものに関する収集家として日本一に違いありません」うんぬんと日本語で情熱を語る寸劇からプロモは始まり(台詞の英訳が字幕で表示される)、彼が「最新の取得物」と称して再生するヴィデオがこの曲の演奏シーン・・・という流れとなる。演奏シーンは基本モノクロで、時折カラーが交ざる。ポールはアルバムと同様ヘフナー・ベースを弾く。合間には、コレクターが窃盗団を雇って集めたという設定で(主に初期ビートルズの)メモラビリアや秘蔵フィルムが多数映し出されファンなら必見だ。うち前者は『サージェント・ペパー』の軍服を筆頭に映画「ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!」の台本や黎明期ザ・クオリーメン時代の名刺、後者はビーチで水着を着て臨んだフォト・セッションでの映像(1963年7月。ジョン・レノンのダンスに注目!)などを確認できる。アルバム『ヴィーナス・アンド・マース』制作のため渡米中のウイングス(ポールとリンダ、ジョー・イングリッシュが映る)や、この曲の共作者エルビスの姿も。コレクターは終盤とうとうヘフナー・ベースを盗み出すが、自慢する間もなく日本人警官に御用になってしまう。悪事をずっと監視してきた防犯カメラがパナソニック製なのがまた皮肉的。最後はポールがしたり顔で満面の笑みを浮かべる。大変滑稽だけど、日本のファンは複雑な気分にならざるをえないですね・・・(汗)。
このプロモは既にプロモ・ヴィデオ集「The McCartney Years」にも収録されているが、今回は天地をカットせず1989年当時に忠実な画面サイズとなっている。また、「The McCartney Years」では曲が始まる直前にヴィデオをデッキに挿入する音とTVのノイズが加えられていたが、ここでは元通り無音に戻されている。一方、「The McCartney Years」ほどはノイズ除去等は徹底されていない。
2.マイ・ブレイヴ・フェイス(ヴァージョン2)
ロジャー・ランが手がけたプロモ(=「ヴァージョン1」)と比べ知名度がぐっと低い「ヴァージョン2」は、「The Making Of My Brave Face」「The Making Of The Promo Promo」とも呼ばれる通り、「ヴァージョン1」の演奏シーン撮影時の模様を捉えたメイキング・ヴァージョンと言ってよい内容である。こちらの監督はセバスチャン・デュースベリー。「ヴァージョン2」の大きな特徴として、(日本での放映を考慮してか)日本人コレクターが一切登場しないことと、全編カラーである点が挙げられる。「ヴァージョン1」よりもポールたちのパフォーマンスに集中でき、ギターやキーボードを弾く手つきも随時クローズアップされるのがうれしい。ポールとリンダがメイクを施してもらったり、休憩中にメンバー間で雑談したり、歌いながらカメラに顔を突っ込むポールを別のカメラで映したりと、普通ならまずカットされそうな面白い一こまもふんだんに取り入れている。「ヴァージョン1」とは違い「The McCartney Years」には収録されなかったため、この「ヴァージョン2」は今回が初ソフト化となる(ブートでは出回っていたものの)。
3.ディス・ワン(ヴァージョン1)
贅沢にも、「ディス・ワン」は内容の全く異なるプロモ・ヴィデオが2種類制作された。この「ヴァージョン1」はティム・ポープが監督をつとめ、インドの宗教画にインスパイアされた曲と歌詞の世界を直接的に題材としている。撮影日は1989年6月28日と翌29日。本作でポールは1人2役を演じていて、片方は東洋の桃源郷と思しき庭園のセットで瞑想にふけっている。ほとんど目を閉じたままなので盲人の設定なのかもしれない。シングル・ジャケットにも描かれた白鳥に乗るハレ・クリシュナ(の人形)や周囲に漂うお香の煙、そして民族衣装をまとった女性ダンサーたちがインドにいるような雰囲気を出している(ちょっと安っぽい気もするけど・・・)。ポールの傍らには、リンダを始めツアー・バンドのメンバーが静かに控えている。
もう1人のポールは暗闇をさまよっていて、桃源郷につながる扉を開け盲人のポールと出会う。大きく見開いた目のインパクトが強烈だが、これは上まぶたにメイクで目を描き、実際の目を閉じて演技することで実現している。盲人の対極を表現したのだろうが、何だか怖い顔で意図せず面白い。ミドルエイトではバンドの面々までもがそのメイクをして、しかも高速で踊ったり跳ね回ったりとさらに笑いを誘う。ハードな曲調に転じるエンディングでは急に舞台が嵐の如く暗くなり、全員が怖いメイク顔で一心不乱に演奏していてますます混沌極まりない。既に「The McCartney Years」にも収録されているが、今回は天地をカットせず1989年当時に忠実な画面サイズとなっている。一方、「The McCartney Years」ほどはノイズ除去等は徹底されていない。
4.ディス・ワン(ヴァージョン2)
1989年7月に、ツアー・リハーサルに使っていた納屋で12日かけて撮影した「ヴァージョン2」ではエスニック要素を排し、万華鏡を覗いているかのようなサイケデリック調に仕上げた。監督はディーン・チェンバレン。このプロモではカメラ・オブスキュラ(写真機の原型)の原理が応用され、真っ暗な部屋で撮影対象にライトを当てつつシャッター・スピードを遅くして撮ることにより、コマ送り再生風の映像にすると共に、カラフルな光の軌道や模様を描くライト・ペインティングも多用している。ポールとツアー・バンドのメンバーは、シークレット・サービスみたいな黒スーツや18世紀ヨーロッパの貴族の衣装を着て歌ったりポーズを取ったりしており、「ヴァージョン1」よりも断然笑顔が多い。監督は「僕らがバンドだってことを忘れないで」とポールから念を押されたそうだが、ポールとリンダ2人きりの仲睦まじいシーンもばっちり見られる。こちらは「The McCartney Years」未収録だったため、公式にソフト化されるのは今回が初めて。
5.フィギュア・オブ・エイト
この曲は1989年9月に始まったワールド・ツアー(通称「ゲット・バック」ツアー)のオープニング・ナンバーに抜擢されたので、プロモ・ヴィデオもコンサートの模様をそのまま使ったシンプルなものになった。監督は後に「明日への誓い」(1993年)のプロモも手がけるアンディ・モラハン。曲はシングル・ヴァージョンが採用されている。映像の方は10月30日のスイス・チューリッヒ公演(本番と、観客を入れずに事前に撮ったステージ・シーンの両方)がメインで、初日・9月26日のノルウェー・オスロ公演を一部織り交ぜている。ウォルの5弦ベースを弾きながら熱唱するポール(タイトル通り8の字形に回る姿も)、間奏でギター・ソロを堂々と披露するロビー、直後のコーラスでポールと1本のマイクを分け合うヘイミッシュ、軽快なドラミングを繰り出すクリス、にこやかにタンバリンを振るリンダ、そして変顔を一瞬見せる(笑)ウィックスと、六者六様のステージを堪能できる。観客も両手を上げ手拍子して既にノリノリの反応。
シングル・ヴァージョンは5分強の完全版と約4分のショート・ヴァージョンが存在し、それを受けてこのプロモも2種類の尺が用意されたが、今回は前者の完全版のみが収録され、後者のショート・ヴァージョンは初ソフト化を果たせなかった。完全版は既に「The McCartney Years」にも収録されているが、今回は天地をカットしていない上に、1989年当時の放送用にレターボックス化する前の画面サイズとなっている(ブートも含め初登場)。一方、「The McCartney Years」ほどはノイズ除去等は徹底されていない。
6.パーティ・パーティ
TV放映用に制作されたもののどこにも取り上げてもらえず、ブートでのみ流通していたといういわくつきの作品。監督はピーター・ブルックス。ダンサブルなパーティー・ソングであることを踏まえ、飲酒・演奏・ダンスに興じる人々や賑やかな夜の街を描いたアニメーションが大半を占めている。これが実にサイケデリックで、しかもめまぐるしく動き回るので目を痛めそうだ(LSDを服用した時の幻覚はこんな感じなのかしら)。ともあれ、3人のアニメーターから成るチームが、12日かけて16ミリフィルムに約4,500枚を直接手描きしていったのだからすごい。ポールたちツアー・バンドのメンバーも実写で時々登場するが(ドキュメンタリー作品「プット・イット・ゼア」撮影時の映像)、そこにもアニメが描き加えられている。曲の方は、非売品のプロモ盤『ポール・マッカートニー・ロックス』収録のエディット・ヴァージョンで、後半が大幅にカットされる代わりに誰かの話し声が冒頭に追加されている。このプロモは今回が初のソフト化。ブートでは画質が非常に悪かったので、視聴に十分耐えうるレベルで観られるのは大歓迎ですね。
7.太陽はどこへ?
1989年7月に制作されたこのプロモ・ヴィデオ(監督はデヴィッド・ロッジ)を面白いと思わない人はそうはいないであろう。当時隆盛を極めていたファミコン・ゲームの世界が舞台の大変楽しい内容なのだから!左から右にキャラクターが移動するアクション・ゲームを模したアニメーションが中心で、主人公の男性が敵を倒しながら遺跡や海を冒険してゆく。敵キャラや背景、主人公が放つビームのチープぶりにファミコン世代なら懐かしさを覚えるはず。背景には実写のポールも現れ、歌いながら主人公の無事を見守る。終盤はラスボスのドラキュラと一騎打ちになるが一撃であっさり勝ってしまう(苦笑)。ゲームをクリアした主人公は、メキシカンハットをかぶったポールに祝福される。一方で、間奏では実写パートも挿入され、アフリカの原住民のダンスやディスコ・ホールのイメージをバックにポールとツアー・バンドのメンバーが陽気にメチャクチャ踊りまくるのが負けじと楽しい。顔だけ出して箱に入れられたメンバーたちを、リンダがのこぎりで挽いてゆく手品さながらのシーンも。曲はアルバム・ヴァージョンを使用している(ただしフェードアウトが30秒ほど早い)。このプロモも今回が初の公式ソフト化となる。
8.プット・イット・ゼア
ポールの亡き父ジェームズが握手する時にたびたび口にしてきた言葉を基に書かれたゆえに、この曲のプロモ・ヴィデオは父親と幼い息子の親しい関係をテーマにしている。監督はニール・マッケンジー・マシューズ。映像は終始セピア調で、1人アコースティック・ギターを弾くポール(1990年1月22日に撮影)と、2組の父子の日常生活を交互に映す。一緒に自転車を直したりトランペットを吹いたりボール遊びをしたり・・・どのシーンでも親子は仲良く、そして象徴的に握手を交わし、どこを切り取っても心温まる家族愛にあふれている。最後にはポールとその顔に落書きする長男ジェイムズのツー・ショットも。既に「The McCartney Years」にも収録されているが、今回は天地をカットせず1990年当時に忠実な画面サイズとなっている。また、「The McCartney Years」では青系の色合いに変更されていたが、ここではセピア調に戻されている。一方、「The McCartney Years」ほどはノイズ除去等は徹底されていない。ポールのアコギ弾き語りだけをフィーチャーした別ヴァージョンも存在するが、「The McCartney Years」に続き再度未収録に終わってしまったのは残念。
9.ディストラクションズ
元々はドキュメンタリー作品「プット・イット・ゼア」(本DVDにも収録)のワン・シーンとして撮影された映像を抜粋して、単体のプロモ・ヴィデオに再編したもの。監督も無論ジェフ・ウォンフォー。「プット・イット・ゼア」ではイントロにポールのインタビュー映像がかぶさり、最後は早めに暗転するため、ここではその箇所は静止画で穴埋めしている。シーンの大半はレコーディング・セッションの再現で、スタジオ入りするポール、ヘイミッシュ、クリスの3人をモノクロで捉える。ポールがウォルの5弦ベース(間奏ではアコースティック・ギターも)をどのように弾いているかよく分かるのがうれしい限り。休憩中のポールの姿もカラーで随所に挟まれるが、その気だるくやるせない表情が曲調・詞作にお似合いだ。曲の方は、アルバムとは各楽器のバランスやステレオ配置が異なる別ミックスで、全体的にオーケストラの音量を抑えている。中でも第2節の“And they'll disappear(みんな引き払うよ)”の直後はほとんどの楽器とヴォーカルが2小節にわたりオフになり、ベース・ソロに近い状態に(5弦独特の低音がスリリング)。これまでブートでプロモと称して出回っていた映像は「プット・イット・ゼア」からそのまま切り出してきたものだったので、この形では今回が完全初登場である。
10.幸せなる結婚
この曲は一時期シングルカットが検討されたため、進行中の「ゲット・バック」ツアーをテーマにしたプロモ・ヴィデオが1990年3月に準備された。監督はウイングスの諸作品のアートワークを手がけたヒプノシスの元メンバーで、当時はツアーのクリエイティブ・ディレクターに就いていたオーブリー・パウエル。「フィギュア・オブ・エイト」と同じくコンサートのシーンは本番と、事前に撮った擬似ライヴを使い分けていて、うち前者は直近の米国・インディアナポリス公演(1990年2月14日と翌15日)と日本・東京公演(同年3月3〜13日)を確認できる。最初のサビが終わった直後の1'03"付近で、東京公演を見に来た石橋貴明(とんねるず)が偶然映るのは特筆に値するトリビア(苦笑)。各地の会場外の風景も頻出するが、ポールとリンダを乗せたリムジンがやって来るのを待ち続け、その到着後はポールに花を贈ったりサインを求めたりするファンの熱烈な歓迎は今と変わらない。曲はラジオ局向けに配布されたエディット・ヴァージョンを使用し、後半が何ヶ所かカットされアルバム・ヴァージョンより1分ほど短くなっている。このプロモが公式にソフト化されるのは今回が初めて。
〜クリエイティング・フラワーズ・イン・ザ・ダート〜
1.ポールとエルヴィス
未発表映像。1988年初頭にホッグ・ヒル・ミル・スタジオで、ポールとエルビスが1988デモ(本リマスター盤のCD 3)のレコーディングに勤しむ様子を記録したドキュメンタリー・フィルムである。'70年代からの付き合いで、ポールを技術面で長く支えてきたエンジニアのエディ・クラインによる撮影。CD 3の項で前述した通り、セッションにはヘイミッシュ、クリスとケヴィン・アームストロングが招かれており、彼らも映像に登場する。「マイ・ブレイヴ・フェイス」のエルビス・ヴァージョンのみドキュメンタリー作品「プット・イット・ゼア」で断片的に見ることができたが、それ以外のシーンはすべて初公開で、音源共々今まで謎に包まれていたセッションのさらなる解明に寄与する貴重な資料と言えよう。
映像は、ポールとエルビスが「愛犬家の皆さん」に向けてバイオリンとキーボードで即興演奏(ポールいわくエジプト風)を披露するおふざけで始まる。続く「マイ・ブレイヴ・フェイス」ではなんと!エルビスがリード・ヴォーカルを取っている。それだけでもレアなのに、ここではテンポを上げてパンク寄りに解釈するばかりか、ポールがキーボードを担当しているのだからこの上なく珍しい。全員が同じ部屋に集まっての「トゥエンティー・ファイン・フィンガーズ」は、まずポールが主導してスローな弾き語りで曲構成を途中まで確認。その後、クリスの意見も聞きつつイントロのリズムやコーラスのタイミングを詰めてゆく。この時は2小節のドラム・ソロの後にコーラスを開始する案で落ち着き、早速通しで試している(CD 3収録の最終テイクではドラム・ソロはカットされた)。通常のドラム・セットとは異なるクリスのパーカッションが面白い。ここまでの2曲は両方とも完奏しているのがうれしい所。
「トミーズ・カミング・ホーム」は既にベーシック・トラックが完成していて、ポールとエルビスが歌入れに臨む。だんだんおふざけに転じてゆく練習(アカペラによるハーモニーが美しい!)を経て本番に2度挑戦しているが、エルビスの要請でいずれも中断。次のシーンでヴォーカルを一部録り直すなど真剣な態度のエルビスに対し、ポールは冗談やわざとらしい仕草で場を和ませている(笑)。ベーシック・トラックの方は、イントロで最終的にオフにされるクリック音やカウントが聞こえるのが興味深い。続いては再び「マイ・ブレイヴ・フェイス」のエルビス・ヴァージョンに戻るが、ポールは今度はベースを弾いている。また、エルビスが歌い出しでトチって別のギターに持ち替えたり、ベースのグリッサンドに笑いを誘われグダグダになったりとNG集のような趣がある。そこにポールもすかさず立ち上がりカメラに向かってお尻振り振り。最後の「マイ・ブレイヴ・フェイス」は一転してCD 3収録の最終テイクと同じアレンジで、ポールとエルビスがベーシック・トラックに歌入れを行っている。歌唱中は基本的に両手でヘッドホンを押さえているが、サビの終わりではクリアのポーズを取るのが面白い。別ブースではヘイミッシュが控え、部分的にハーモニーを加える。一通り録音後、失敗した箇所をどうするか議論している最中に突如ヴィデオが巻き戻るという演出で映像は終わる。
2.スタジオで芽吹くつぼみ
未発表映像。エルビスとの1988デモが棚上げになった後の時期を中心に、ポールのソロ・プロジェクトの側面から『フラワーズ・イン・ザ・ダート』セッションに迫ったドキュメンタリー・フィルムである。こちらも舞台はホッグ・ヒル・ミル・スタジオで、エディ・クラインによる撮影。これまでは「プット・イット・ゼア」のシーンのみ、一部をドキュメンタリー作品「プット・イット・ゼア」で見ることができた。
冒頭でポールが「愛犬家の皆さん」に挨拶している辺り、本作は「ポールとエルヴィス」からのシリーズものを想定していたと思われる。1曲目の「モーター・オブ・ラヴ」ではキーボードをオーバーダブしている所が映されるが、当時は最新鋭のコンピュータも今では時代を感じさせる。続く「ケアレス・ラヴに気をつけて」は不気味なコーラスのない制作途上で、ヘイミッシュとクリスもレコーディングに参加。共同プロデューサーのニール・ドーフスマンが作業する傍らでベースを弾くポールがシュールに見えてしまう。4曲を共同プロデュースしたトレバー・ホーンとスティーヴ・リプソンをユーモラスに紹介するシーンを挟んで、「プット・イット・ゼア」のオーバーダブ・セッションの模様が続く。バディ・ホリーの「エヴリデイ」を参考に膝をたたく音を入れるものの、期待通りの音が出せずに行き詰まっている。ドーフスマンらの提案でポールはズボンをまくり生脚でたたいてみるが、途中からお遊びモードとなり、指や口でおかしな音を鳴らしてコントロール・ルームにいる一同を爆笑させる(笑)。
「ディス・ワン」はこの時点ではスローなバラードで、ミドルエイトで始まる点も含め1986年末に録音したデモ・テイク(本リマスター盤の発売に合わせてポールの公式サイトで無料公開された)の面影を残す。曲構成をおさらいした後にピアノとヴォーカルのオーバーダブに臨むが、すぐにソウルフルなアドリブでふざけ始めてしまう(ポールいわく「無意識の暴走」)。コントロール・ルームで楽しく談笑するポールたち(ヘイミッシュ、ドーフスマンのほかにアシスタントのジョン・ハメルの姿も)のBGMとして流れる「ハウ・メニー・ピープル(チコ・メンデスに捧ぐ)」はまだまだラフな仕上がりで、コーラスや間奏のフリューゲルホルン・ソロも欠いている。ホーンとリプソンをスタジオに招いたポールが「来週はもっとお見せしますよ」と締めくくると、最後は再び「プット・イット・ゼア」セッションへ。プレイバックを聴き終えたポールがビートルズ・ナンバー「ハロー・グッドバイ」のコーダを歌っていて、「ゲット・バック」ツアーで披露された2曲のメドレーのアイデアがレコーディングの段階から存在していたという事実は興味深い。
3.メイキング・オブ「ディス・ワン」(ディーン・チェンバレン監督)
未発表映像。サセックスにある納屋で行われたプロモ・ヴィデオ「ディス・ワン(ヴァージョン2)」制作の模様を、ポールとディーン・チェンバレン監督の解説と、撮影現場の貴重な映像で振り返ったメイキング・ドキュメンタリーである。撮影はまたもやエディ・クライン(一部をポール自ら撮っている)。
まず、第2節冒頭で黒スーツを着たポールが電話をかけるシーンを、実際の撮影風景と完成版とで比較。前者ではチェンバレン監督が登場し、照明の動作をスタッフに指示している。次にポールが、当プロモで監督が導入した撮影方法とカメラ・オブスキュラの原理との類似性を、写真誕生の歴史と共に説明する。ポールが語る通り、カメラ・オブスキュラを基に作られた最初期の写真機(ジルー・ダゲレオタイプ)は15分以上もの露光時間を要したため、動きのあるものはぶれ、道路を行き交う人馬などは当時の写真には写っていない。この特徴を監督がプロモでのコマ送り再生風の映像やライト・ペインティングにどのように応用しているかを、ポールの解説と実際の手順動画で確認できる(ライトを操作する監督は高速で動き回るためカメラに捉えられない)。解説の合間には撮影中の一こまが散りばめられているが、曲後半でのポールとヘイミッシュの横滑りは実はスケーターに乗ることで実現しているのが分かる。
続いてチェンバレン監督がインタビューに答え、「僕にとっては撮影というより絵を描いている感じ。色や色調も自分で考えるよ」とコメント。ポールによる総括と、終盤のシーンの撮影風景(天使の翼を羽ばたかせるヘイミッシュがキュート)を経て、監督が再度インタビューを受ける。元々は写真家だった監督は、先述のテクニックをかれこれ15年は実践しているとのこと。また、きっかけは雑誌で目にしたカメラ・オブスキュラだったとも話す。ビートルズについて感想を聞かれると、「死ぬまで話しているかも」と答えた上で「いつもどこでもビートルズ・ナンバーを口ずさんでしまう。僕の人生の一部なんだろう」と一介のビートルズ・ファンであることを認める。ラスト・シーンはツアー・バンドのメンバーによるジャム・セッションで、みんな揃って貴族の衣装を着たまま演奏している(楽器はエレクトリックだがアンプラグド状態なのが面白い)。
〜プット・イット・ゼア〜
1.プット・イット・ゼア・ドキュメンタリー
1989年4月にホッグ・ヒル・ミル・スタジオで撮影された、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』を特集したドキュメンタリー作品。監督はビートルズの「ザ・ビートルズ・アンソロジー」やポールの「イン・ザ・ワールド・トゥナイト」などを後年手がけるジェフ・ウォンフォー、インタビュアーはジャーナリストのトレイシー・マクラウド。久々のコンサート・ツアー(後の「ゲット・バック」ツアー)を控えたポールがツアー・バンドのメンバーと共に重ねていたリハーサル・セッションの模様を、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』に関するポールへの直接インタビューと交互に映し出してゆく。1989年6月10日に英国BBCで約50分のダイジェスト版が放送された後、同年9月には約1時間の完全版がVHS及びLDとして一般発売された(当時の邦題は「フラワーズ・イン・ザ・ダート・スペシャル」)。また、2003年にはDVD化も果たしている。今回のリマスター盤には過去の商品と同様に完全版が収録されているが、頭出しは6ヶ所(約10分おき)でしかできない。以下では、便宜上曲ごとに区切って解説を掲載してゆきます。
- C・ムーン
オープニングでは、TV画面越しにポールのインタビューがいくつか抜粋される。「ジョン・レノン以上の相棒はいない」「バンドの一員であることはロールス・ロイスを所有するより贅沢だね」といった発言が印象的。続いて1曲目に登場するのは、1972年に「ハイ・ハイ・ハイ」との両A面シングルとして発売されたウイングス・ナンバー。ポールとリンダのお気に入りで、ウイングス時代にもライヴで取り上げていたが、1989年以降はコンサートのリハーサルやサウンドチェックでの定番曲になってゆく。ここではポールがピアノを、ヘイミッシュがベースを弾き、シロホンやトランペットのフレーズはウィックスがキーボードで再現している。楽しげにタンバリンを振るリンダはウイングスの頃をほうふつさせる。2分未満の断片的収録なのが残念。
- マイ・ブレイヴ・フェイス
「C・ムーン」に連結されて最後のサビから始まるのは、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』からの先行シングルで、「ゲット・バック」ツアーでは最新ヒットとして披露された。曲がいったん終わると、タイトル表示と共に最初のインタビューへ。新作の仕上がりについて問われると「満足している。でもツアーを前に曲の本質をより理解しようと、多くのことを試しているよ」とポール。その一例として、ポールがヘイミッシュとロビーと一緒に3声のハーモニーを練習する光景が紹介される。その後、共作者のエルビスがヘフナー・ベースを使用するよう勧めたという有名なエピソードや、エルビスとジョンの共通点について語る。途中挿入されるエルビスがヴォーカルを取るヴァージョンは本DVDの「ポールとエルヴィス」でより長く聴くことができるが、映像はカメラ・アングルが一部異なる。
ビートルズっぽさの話題から「懐かしく感じる箇所がある」と指摘されると、ポールは“Take me to that place”のくだりを挙げ「僕とジョンらしいだろう」と誇らしげ。先のハーモニーの練習からその節が抜粋される。最後は曲調やテンポががらりと変わるエルビス・ヴァージョンとリハーサル・テイクをつなげて比較。前者は短いながら「ポールとエルヴィス」には未収録の部分で、後者は先ほどよりも長めに収録している(映像も随所で異なる)。ここでようやくウィックスの顔が映る(苦笑)。
- ラフ・ライド
『フラワーズ・イン・ザ・ダート』収録曲で、これまた「ゲット・バック」ツアーでセットリスト入りした。この曲を含め4曲を共同プロデュースしたトレバー・ホーンとスティーヴ・リプソンについて「シングル1枚に3ヶ月かけると噂に聞いていたけど、僕のやり方に合わないので2日で完成させるよう依頼したよ」と話す。その後、曲想の源になったリフをアコースティック・ギターで爪弾いてみせる。1チャプター目はここまで。ライヴでの再現が難しそうな1曲だが、続くリハーサル・テイクはスタジオ・ヴァージョンを忠実にコピーしている。ヘイミッシュとロビーのギターさばきや、ウォルの5弦ベースを弾くポールの手つきをじっくり観察できるのがうれしい。緊張感漂う演奏の中、終盤には笑みもこぼれる。なお、このテイクのオーディオ・トラックはCDシングル「フィギュア・オブ・エイト」(一部仕様のみ)と来日記念盤『フラワーズ・イン・ザ・ダート -スペシャル・パッケージ-』に収録されており、そちらはイントロ/アウトロ共に完奏する。
- フィギュア・オブ・エイト
「一緒に歌える歌にしたかった」とポールが振り返るのは、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』収録曲で「ゲット・バック」ツアーのオープニング・ナンバー。「当初は低い音程で歌っていたけど、少し高めにしてみたんだ。ヴォーカルとドラムスはライヴ・レコーディングだよ」とポールは語る。この曲は1989年9月にシングル用のリメイク・ヴァージョンが録音されるが、その5ヶ月前のリハーサルの時点でシングル・ヴァージョン及びライヴ・ヴァージョンと同じ曲構成が確立されていることが分かる。眉間にしわを寄せてシャウト・ヴォーカルを繰り広げるポールが何ともかっこいい。ロビーのスライド・ギターによる間奏のソロもばっちり映る。映像は終始青系のモノトーンで、最後の“stuck”が編集で2回繰り返されるおまけ付き。2チャプター目はここまで。
- フール・オン・ザ・ヒル
1987年に始まったビートルズのアルバムのCD化を念頭にポールが「CDのおかげでまた聴いてもらえるんだ」と語るこの曲は、アルバム『マジカル・ミステリー・ツアー』(1967年)収録のビートルズ・ナンバー。「ゲット・バック」ツアーでも引き続き演奏されたが、このリハーサルは本番とほぼ同じアレンジで、ライヴ用に付け加えられた長いアウトロも既に存在する。ポールはピアノを弾き語り、ウィックスがキーボードでフルートやリコーダーの音を代奏している。クリスが一部シンバルを電子ドラム・パッドでたたいているのも確認できる。間奏でポールの映像が無数にぐるぐる回る(spinning 'round)演出がやや古くさいものの効果的。
- 今日の誓い
続いてもビートルズ時代の曲で、アルバム『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』(1964年)より。この曲を含め、「ゲット・バック」ツアーからはビートルズ解散後意識的に避けてきたビートルズ・ナンバーを積極的に演奏するようになるポールだが、そのことについて「昔の友達に再会した気分になる」と話す。ここではポールはアコースティック・ギターに持ち替えている。オリジナル・ヴァージョンではポール自ら加えていたハーモニーはヘイミッシュが担当。第2節のみの抜粋なのがあっけないですね・・・。あと、左右でミラー反転している映像(左がモノクロ、右がカラー)は見づらいです(汗)。
- アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア
さらに時を遡ってビートルズのデビュー・アルバム『プリーズ・プリーズ・ミー』(1963年)収録曲。「プリンス・トラスト」10周年記念コンサート(1986年6月20日)でオリジナル・キーで歌えたことがステージ復帰への自信につながった1曲だけあって、「ゲット・バック」ツアーでもこのリハーサル・テイクでもロック魂みなぎる熱唱を聞かせる。ポールが弾いているのはビートルズの頃と同じヘフナー・ベースだ。一緒に演奏するヘイミッシュやクリスも笑顔を見せて楽しそう。「今日の誓い」に連結され、第2節〜間奏手前のみが収録されている。映像はまたもや左右でミラー反転している(今度は左がカラー、右がモノクロ)。
- ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード
ビートルズのラスト・アルバム『レット・イット・ビー』(1970年)収録曲。冒頭でポールがビートルズについて「スフレは温め直せない」という表現で後戻りできないと語るのが印象に残る。これも「ゲット・バック」ツアーでセットリスト入りした曲で、ポールはウイングスでの再演と同様ピアノを弾き、ベースはヘイミッシュが座って演奏。ビートルズ・ヴァージョンのオーケストラ・アレンジにポールが激怒したというエピソードが語り草だが、ここではウィックスが控えめにシンセ・ストリングスを奏でる。残念ながら間奏までの収録だが、完奏するオーディオ・トラックを7インチシングル「ディス・ワン」、CDシングル「フィギュア・オブ・エイト」(いずれも一部仕様のみ)及び来日記念盤『スペシャル・パッケージ』で聴くことができる。
- ハウ・メニー・ピープル(チコ・メンデスに捧ぐ)
『フラワーズ・イン・ザ・ダート』収録曲で、1988年12月に凶弾に倒れたブラジルの環境保護運動家チコ・メンデスに捧げられた。「作曲後にメンデスの死を知り、歌詞で伝えたいことに合うと思ったので彼の献身を広めようと捧げた」と説明し、「みんな環境保護についてもっと話すべきだよ」と訴える。3チャプター目はここまで。続くリハーサル・シーンは、ツアーのセットリストから漏れたことを踏まえると貴重なテイクである。打ち込みを使用したスタジオ・ヴァージョンよりも生のバンド・サウンドになっていて聴きやすい。ポールがピアノを、ヘイミッシュがベースを弾く。第2節からはリンダとヘイミッシュがコーラスを入れ(特にリンダの“One too!”が目立つ)、その姿もアップでよく映るが、曲は間奏に入った所でフェードアウトしてしまう。曲の前後にはメンデスの写真が「R.I.P.」の文字と共に登場する。
- ふりむかないで
『フラワーズ・イン・ザ・ダート』収録曲。共作者のエルビスがライヴでたびたび取り上げているのに対し、ポールはこの曲を一度も人前で披露したことがない。それゆえに、第2節のみながら大変レアな演奏シーンと言える。スタジオ・ヴァージョンよりもスローで、葬送曲らしい物悲しさが強調されている。またまたポールがピアノを、ヘイミッシュがベースを担当。ウィックスがキーボードでブラス・セクションを再現する。ヘイミッシュとウィックスは手つきもクローズアップされるのがおいしい。ポールは時折メロディを崩しながらソウルフルに歌い上げる。
- ディス・ワン
「いつも“この瞬間”を大切に生きればもっとよくできる。“今”がすべてなんだよ」という格言の後に始まるのは、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』からのセカンド・シングル。当然ながら「ゲット・バック」ツアーで演奏された。本番よりもだいぶテンポを落としてゆったりと聞かせる。ウィックスの力量ならインド風の各楽器も再現できそうだが、そうした音はあえてそぎ落としている(ハーモニカのメロディはロビーがギターで代奏)。終盤の追っかけコーラスはもちろん、ヘイミッシュがバッキング・ヴォーカルで存在感を発揮している。この曲ではタンバリンに専念するリンダが微笑ましい。
- プット・イット・ゼア
『フラワーズ・イン・ザ・ダート』収録曲にして本ドキュメンタリーのタイトル・ソング。ポールの父親ジェームズの口癖に着想を得たというファンならご存知の話に触れ、「歌詞としては歌いにくかった」と振り返る。リハーサル・セッションよりサビの一部が抜粋された後(4チャプター目はここまで)、アクセントとして膝をたたく音を入れたことを実演を交え解説。次のオーバーダブ・セッションの模様は本DVDの「スタジオで芽吹くつぼみ」でより長く見ることができる。最後は再びリハーサルに戻り、今度は完奏する。ポールはアコースティック・ギターを弾きながら軽やかに歌う。またしてもヘイミッシュがベーシストの役割を担っている。キーボードの出番がほとんどないため、リンダは間奏を除き手持ち無沙汰だ。エンディングは「ゲット・バック」ツアーと同じく「ハロー・グッドバイ」のコーダにつなげ、それまでモノクロだった映像がカラーに切り替わる。
- トゥエンティ・フライト・ロック
1987年に録音し、翌年にソ連限定で発売したロックンロールのカヴァー・アルバム『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』(本ドキュメンタリーの放送当時は英米では未発表)へと話題は移る。「ミュージシャンを集めてジャムをしていたら、昔愛聴していたロックンロール風だって気づいた。既存の曲のカヴァーを通じて、ジャムの気持ちよさをスタジオで出そうと考えた」とポール。なお、クリスにとってはそのセッションがポールとの初仕事であった。次のリハーサル・シーンで演奏される「トゥエンティ・フライト・ロック」はエディ・コクランのカヴァーで、ポールは『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』で取り上げたのみならず、「ゲット・バック」ツアーでも堂々とセットリストに加えている。ロビーがギター・ソロをプレイする間、ポールは体を揺らしながらヘフナー・ベースを弾いてノリノリ。とても楽しそうなだけに、間奏1回分のみの収録なのが惜しまれますね・・・。
- ジャスト・ビコーズ
ここからは『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』収録曲が4曲続けざまに登場する。まずこの曲は'20年代のネルストーンズ・ハワイアンズがオリジナルだが、ポールが参考にしたのは最も成功したエルビス・プレスリーのヴァージョン。インタビューではエルビスの大ファンを自認するポールが彼の魅力を熱く語る。1956年の主演映画(「やさしく愛して」のことと思われる)が大好きだと明かしたり、同年の「アイ・ウォント・ユー、アイ・ニード・ユー、アイ・ラヴ・ユー」を真似して歌ってみたり・・・。一方のリハーサル・テイクは恐らく最初の1節分がカットされて始まる。これが実に愉快な仕上がりで、ポールも「トゥエンティ・フライト・ロック」以上に体を動かしてニコニコ。他のメンバーのノリも最高で、1989年以降しばらくサウンドチェックで定番化した理由がよく分かる。ポールはロビーと2人でギターを弾いているが、そのトーンは『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』よりもカントリー色が濃い。フェードアウトせずに締めるエンディングもきまっている。
- サマータイム
ジョージ・ガーシュウィンがオペラ「ポギーとベス」のために書いた曲で、数多くのアーティストがカヴァーしてきたスタンダード・ナンバー。『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』では渋いブルース・ロックに解釈されたが、今回もそのアレンジを基本的に踏襲している(オルガンの代わりにピアノとシンセ・ストリングスを使用)。ポールはリード・ギターを買って出て、間奏では険しい表情でソロに没頭する。歌っている時の余裕綽々な顔つきとのギャップが激しい。1分強の断片的収録なのが物足りない所です。この曲は「ゲット・バック」ツアー開始前のミニ・ライヴで何度か演奏されたが、その後はサウンドチェックにとどまった。
- ルシール
オリジナル・アーティストはリトル・リチャードで、ビートルズでもウイングスでもカヴァーしたポールのお気に入りナンバー。「ジャスト・ビコーズ」に続き前半がカットされている。『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』ではブランクからのリハビリ途上で本調子ではなかったポールのヴォーカルもすっかり感覚を取り戻して、リトル・リチャード直伝の絶叫を堪能できる。演奏面では、『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』と同様1度目の間奏はギターを、2度目の間奏はピアノを前面にフィーチャー。ウィックスが繰り出すピアノ・テクニックの妙を間近で味わえるが素晴らしい。
- エイント・ザット・ア・シェイム
オリジナルはミリオン・セラーを達成したファッツ・ドミノの代表曲。カヴァー曲ながら「ゲット・バック」ツアーでは本番で取り上げられた。このリハーサル・セッションとツアーではウィックスのキーボードによるブラス・セクションが派手に加わり、原曲に近いニューオーリンズの雰囲気を醸し出している。ポールがピアノを弾く時は必ずヘイミッシュがベースに回る。堅実かつ力強いクリスのドラミングにも注目。『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』でも相当シャウトしていたポールだが、ここではさらに輪をかけてテンションを上げ、後半に向けてどんどん感情を爆発させてゆく。5チャプター目はここまで。
『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』シリーズ明けのインタビューで「スタジオでは楽しんでいますか?」と尋ねられると、「もちろん。でも大変な時もある」と答える。しばらくぶりに「マイ・ブレイヴ・フェイス」のエルビス・ヴァージョンが2つ挿入されるが、ポールがキーボードを弾いている方は「ポールとエルヴィス」収録の演奏とは別テイク。ポールがベースを弾いているNGシーンは「ポールとエルヴィス」でより長く見ることができる。それらの映像を踏まえ、「緊張をほぐすため時にはすごいバカをやるよ。僕らは楽しんで音楽を作る」とポールは続ける。
- ディストラクションズ
締めのインタビューで、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』で新たなファンの獲得を考えているか聞かれたポールは「それは僕の考えることじゃない。みんなが気に入ってくれるといいな。クソ野郎もね」とユーモラスに切り返す。続く『フラワーズ・イン・ザ・ダート』収録曲「ディストラクションズ」の映像は、前述のように両端を除き本DVD収録のプロモ・ヴィデオと同じ内容である。最後の質問「人生で音楽をやめる時が来たら後悔するか?」に対しては「興味も持てない質問だ」とばっさり。「命の続く限り生きて、音楽も続けてゆくつもりだ」と語るが、それから28年が経った2017年も現在進行形で精力的に音楽活動をこなすポールを思うととても感慨深い。
- パーティ・パーティ
「プット・イット・ゼア」のオーバーダブ・セッションよりポールの「これが精一杯」というコメントを挟んで登場するのは、この頃ツアー・バンドのメンバー全員で作り上げた即興曲。正式なスタジオ・テイクは半年後の1989年10月に録音され、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』の限定盤「ワールド・ツアー・パック」の付録シングルで発表された(本ドキュメンタリーの放送当時は未発表曲だった)。ここではジャム・セッションが2分ほど収められているが、理路整然とした音作りの公式テイクとは打って変わってロック色が強く並々ならぬ熱量を感じる。ポールは楽器を持たず腕をぶんぶん振って踊りながらアドリブ・ヴォーカルを自由自在に繰り広げる。各メンバーのオフ・ショットも多数盛り込まれるが、その表情やポーズがいちいち面白おかしい。よく見るとプロモ・ヴィデオの素材に後日使用されるカットもちらほら。ポールがスタジオの外に出て、扉を閉じた所で曲は唐突に終了する。
- レット・イット・ビー
ビートルズの同名アルバムに収録された超有名曲。エンド・クレジットのBGMとしてリハーサル・テイクが間奏から流れる。演奏・ヴォーカル共に、「ゲット・バック」ツアーで実際に披露された時のようにソウルフルに聞かせる。途中からは画面の左半分にポールがアップで映し出され、崩し歌いで熱唱する姿を堪能できる。最後はなぜか「ディストラクションズ」でベースを弾くポールのスローモーションで、それが静止画になり約1時間のドキュメンタリーは終わる。
Download only
〜Bサイズ、リミクシーズ・アンド・シングル・エディッツ〜
1.バック・オン・マイ・フィート
1987年11月に発売されたシングル「ワンス・アポン・ア・ロング・アゴー」のB面で、アルバム未収録曲。1993年に『フラワーズ・イン・ザ・ダート』が「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズで再発売された際にボーナス・トラックに追加された。ポールが温めていた曲を、エルビスから詞作面の助言を受けて完成させている。その後、1987年春にフィル・ラモーンをプロデューサーに迎えた未発表アルバム(通称『The Lost Pepperland Album』)のセッションで録音された。歌詞は物語風で、愛を拒絶するホームレスの男の孤独を演劇仕立てで描く。
2.フライング・トゥ・マイ・ホーム
1989年5月に発売されたシングル「マイ・ブレイヴ・フェイス」のB面で、アルバム未収録曲。1993年に『フラワーズ・イン・ザ・ダート』が「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズで再発売された際にボーナス・トラックに追加された。シャッフル調のリズムとポールの一風変わったリード・ヴォーカルが印象的なギター・ロック。オートハープとシンセサイザーがタイトル通り空を飛んでいるかのような高揚感を与える。レコーディングにはヘイミッシュ、クリス、リンダが参加している。
3.ザ・ファースト・ストーン
1989年7月に発売されたシングル「ディス・ワン」(一部仕様を除く)のB面で、アルバム未収録曲。これまでシングル以外に収録されたことがなく、「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズでもボーナス・トラックから漏れたため長い間正規での入手が困難であった。ポールとヘイミッシュの記念すべき初共作曲(2人は後に「キープ・カミング・バック・トゥ・ラヴ」などを共作)で、エレキ・ギターをガンガン鳴らしまくったハードエッジなロック・ナンバー。途中でレゲエ調になったり、コーラスがステレオの左右を行き来したりするのがユニーク。ジャーナリズムを辛辣に揶揄した歌詞も痛烈だ。しまいには聖書の一節「罪のない者だけが石を投げよ」も引用される。ポールのセルフ・プロデュースで、1988年7月に録音された。
4.グッド・サイン
1989年7月に発売された12インチシングル「ディス・ワン」(第2弾のみ)のB面で、アルバム未収録曲。これもシングルでしか聴くことができなかった曲で、かつ未CD化である(それだけに今回もCD化を逃してしまったのが痛い・・・)。当時流行っていたハウス・ミュージックをポールなりに解釈したダンサブルな1曲で、華やかなブラス・セクションやパーカッションが楽しい。ヘイミッシュのハーモニーもいい味を出している。ダンカン・ブリッジマンのプロデュースで1988年6月に録音され、クレア・フィッシャーがアレンジしたブラス・セクションが12月にオーバーダブされた。『フラワーズ・イン・ザ・ダート』の収録曲候補には最終段階まで残っていたが、土壇場で外されてしまった。一方で、クラブDJ向けにプロモ・シングルが200枚限定で配布され、そのB面には「groove mix」という名のリミックス・ヴァージョンが収録されている(これは超レア音源)。
なお、今回ボーナス・ダウンロード・トラックとなったものは、当時のシングルとは曲の長さが異なる。具体的には、商品化にあたってカットされてしまった第1節直前の4小節が復活している(1'12"〜1'20"に該当。この箇所はブートも含め完全初登場)。また、シングルではアウトロのパーカッション・ソロがいったんフェードアウトしきった後に数秒だけ小音量で戻ってくるという意図不明のミックスが施されていたが、ここではカットされている。ポール・マニアの頭を悩ませる新たなヴァージョン違いです(汗)。いずれにせよ、この手のダンス・ナンバーではとっつきやすくお勧めな上に個人的には「太陽はどこへ?」と並んで病みつきな曲なので、入手が一気に容易になったことを歓迎したいですね!
5.ディス・ワン(クラブ・ラヴジョイズ・ミックス)
1989年11月に発売された12インチシングル「フィギュア・オブ・エイト」(一部仕様のみ)B面に収録された、「ディス・ワン」のリミックス・ヴァージョン。英国では500枚限定のプロモ・シングルが出回ったほか、一部ヨーロッパではオリジナルを本リミックスに差し替えた12インチシングル「ディス・ワン」が発売された。また、2007年に『フラワーズ・イン・ザ・ダート』がiTunesで発売された際にボーナス・トラックとして入手できるようになったが、現在も未CD化のままである。当時重用されていたエンジニアのマット・バトラーによるミックスで、ほとんどの楽器を取り払いインド色を消した上で、単調なドラム・ビートに乗っけている。イントロの印象はオリジナルとはがらりと変わり、「ワインカラーの少女」さながらにブルージー。歌い出しのヴォーカルは電話を通して歌っているかのように加工されている。後半は1節増やし、間奏ではタイトルコールを小刻みに繰り返したりピッチをいじったりして遊んでいる。よほどの酔狂でない限り退屈してしまう、これで踊れるかと言われると疑問符が付くクラブ・ミックスですね・・・。
6.フィギュア・オブ・エイト(12インチ・ボブ・クリアマウンテン・ミックス)
1989年11月に『フラワーズ・イン・ザ・ダート』からの第3弾シングル(英国42位・米国92位)となった際に収録されたシングル・ヴァージョン。このヴァージョンはアルバム発売後の1989年9月に新たに録り直されたもので、アルバム・ヴァージョンとは内容が全く異なる。共同プロデューサーは「モーター・オブ・ラヴ」でタッグを組んだクリス・ヒューズとロス・カラムで、ボブ・クリアマウンテンがリミックスを行った。ツアー・バンドのメンバーが全員揃っての生のバンド・サウンドで、無機質に響くアルバム・ヴァージョンとは好対照を成す。ラフだった曲構成も練り直され、ロビーがスライド・ギターでソロを披露する間奏が追加された。
追って制作されたプロモ・ヴィデオにはシングル・ヴァージョンが採用されている。なお、6種類の仕様で乱発されたシングル「フィギュア・オブ・エイト」のうち、アナログ盤(7インチ・12インチ)及び3インチCDには5分強のフル・ヴァージョンを、5インチCDには約4分のショート・ヴァージョンを収録しているが、今回ボーナス・ダウンロード・トラックに選ばれたのは前者のみで、ショート・ヴァージョンは収録を見送られ、現在も入手困難なままである。今一つ盛り上がらない感のあるアルバム・ヴァージョンよりも躍動感が大幅に向上したシングル・ヴァージョンを推薦してきた身としては、やっと日本でも公式発表を果たしたことは大変ありがたいですね。
7.ラヴリエスト・シング
1989年11月に発売された5インチCDシングル「フィギュア・オブ・エイト」のカップリングで、アルバム未収録曲。既に来日記念盤『スペシャル・パッケージ』に収録されていた上、1993年に『フラワーズ・イン・ザ・ダート』が「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズで再発売された際にボーナス・トラックに追加された。ニューヨークに滞在中の1986年8月にフィル・ラモーンのプロデュースで録音されたピアノ・バラードで、ビリー・ジョエルのバック・バンドがサポートする。甘さとほろ苦さが同居するせつないラヴ・ソング。
8.太陽はどこへ?(12インチ・ミックス)
1989年7月に米国と一部ヨーロッパで発売された12インチシングル「太陽はどこへ?」に収録された、同曲のリミックス・ヴァージョン。この「12インチ・ミックス」は同年11月に12インチシングル「フィギュア・オブ・エイト」(一部仕様のみ)B面に再録されるものの、現在も未CD化である。「太陽はどこへ?」は公式発表されたものだけでも4種類のリミックスが存在するがいずれも、'80年代のダンス・ミュージック・シーンを牽引した名リミキサーのシェップ・ペティボーンが補プロデュースとリミックスを、日本のGOH HOTODAがリミックスを手がけている。
「12インチ・ミックス」は一連のリミックスの中でも最も凝った出来で、演奏時間は7分にわたる。のっけから後半の低音ヴォーカルとの掛け合い(しかもアカペラ状態)で始まるのが最高に面白い。ウエ、ウエー、レソレ、レソレー♪歌が入るまでの2分間だけでも先の低音ヴォーカルをメチャクチャに編集してやりたい放題。タンスタンタンタンタン、タンスタンタンタンタン、タンスタンタンタンタン、タンスタンタン、ウエー♪その後も、次から次へと真新しい展開が(低音ヴォーカルをふんだんにサンプリングしながら)繰り広げられるので、グルーヴに身を任せて踊っていたら7分もあっという間でしょう。事実私もこのリミックスの大ファンです(笑)。
9.太陽はどこへ?(タブ・ダブ・ミックス)
12インチシングル「太陽はどこへ?」B面に収録された、同曲のリミックス・ヴァージョン。これも12インチシングル「フィギュア・オブ・エイト」(一部仕様のみ)B面に再録されたが、現在も未CD化である。「タブ・ダブ・ミックス」最大の特徴は、オリジナルにはない「ディンダ、ディンダ」という謎のヴォーカルの繰り返し。ほぼベースとドラムスによる斬新なバッキング・トラックと共に耳を奪われる。キーボードのリフで「太陽はどこへ?」だと認識できるものの、リード・ヴォーカルもなく前半はまるで別の曲を聴いているかのよう。2分半を過ぎてようやくオリジナルに近づいたと思ったのも束の間、今度は突然のパーカッション乱打と例の低音ヴォーカルが混沌に追い打ちをかける。「12インチ・ミックス」より前衛的に攻めつつも、最後はオリジナル通りのエンディングを迎えて聴く者をほっとさせる。
10.太陽はどこへ?(7インチ・ミックス)
シングル「フィギュア・オブ・エイト」(一部仕様を除く)B面に収録された、「太陽はどこへ?」のリミックス・ヴァージョン。こちらはアナログ盤(7インチ・12インチ)のみならずCDにも収録されていたほか、来日記念盤『スペシャル・パッケージ』で聴くことができた。「7インチ・ミックス」は一連のリミックスでは最もオリジナルのアルバム・ヴァージョンに近く、曲構成やヴォーカルなどは原形をとどめている。メインのドラム・ビートは軽快なものに差し替えられ、明瞭なシンセ・サウンドもいろいろ加えられている。間奏には「タタータラタ、ターター」というコーラスを新たにフィーチャー。クラブ・シーンにはオリジナルよりもぴったりかもしれませんが、イントロがずいぶん大仰になってしまったのは流れが悪くて玉に瑕ですね(汗)。
11.太陽はどこへ?(インストゥルメンタル)
12インチシングル「太陽はどこへ?」B面に収録された、同曲のリミックス・ヴァージョン。他のシングル/アルバムへの再録はなく、ポールの母国・英国ですらこれまで未発表の入手困難音源であった。現在も未CD化。「インストゥルメンタル」と銘打たれている通り、ほぼインスト状態のミックスである(厳密には途中「タタータラタ、ターター」が入る)。曲構成はオリジナルと大体同一。とはいえ純粋なカラオケ・ヴァージョンではなく、オリジナルよりもダークなサウンドに変貌している。おなじみのキーボードのリフが擦り切れそうな高音になっているのが奇妙極まりない。また、このリミックスのみ独自のエンディングを迎える。皆さんもぜひカラオケ気分でポールの代わりに「ウエー!」と歌ってみてください(苦笑)。
12.パーティ・パーティ(オリジナル・ミックス)
1989年11月に『フラワーズ・イン・ザ・ダート』が「ワールド・ツアー・パック」として再発売された際に、豪華な付録と共に付いてきた1曲入りシングル(7インチまたはCD)に収録された曲で、アルバム未収録曲。日本では来日記念盤『スペシャル・パッケージ』でも聴くことができた。ツアー・リハーサル中のジャムから発展してできた曲で、ツアー・バンドのメンバー全員が作曲者にクレジットされている。ファンキーなビートをバックにポールがアドリブ風に熱唱し、他のメンバーがタイトルコールや騒ぎ声で加わる賑やかなパーティー・ソングだ。
13.パーティ・パーティ(クラブ・ミックス)
1989年に英米とドイツのクラブDJ向けに200枚限定で配布されたプロモ・シングル「パーティ・パーティ」B面に収録された、同曲のリミックス・ヴァージョン。一般発売はなく、数量限定生産だったこともあり正規での入手は到底無理なレア中のレア・アイテムになっていたが、今回初めて商品化を果たした。オリジナルでプロデューサーをつとめたDJのブルース・フォレストによるミックス。この「クラブ・ミックス」は全体的にベースとドラムスを強調していて、1分続くイントロで特にそれを体感できる。リバーブのかけ方やドラム・ソロの挿入はいかにも'80年代お約束といった所か。最初の間奏ではオリジナルにはない大胆なオルガン・ソロが入り新鮮。他にもオリジナルでは埋もれていた楽器や騒ぎ声がクリアに聞こえて、新たな発見がいっぱい。こっちの方がグルーヴィーでかっこいいですよね。ポールには「もう一声!」で「グッド・サイン」の「groove mix」も網羅してほしかったですが・・・コアなファンでもなかなか手の届かない音源を引っ張り出してくれたことに感謝したいです。
〜カセット・デモズ〜
1.アイ・ドント・ウォント・トゥ・コンフェス
ここから3曲はポールとエルビスの共作で、1987年秋に2人がホッグ・ヒル・ミル・スタジオで制作したデモ・ヴァージョン(カセット・デモ)である。CD 2収録のオリジナル・デモと同じくライティング・セッションと並行しての録音だが、そちらがスタジオの設備を使用しているのに対し、ここではカセット・テープに直接演奏を吹き込んでいる。他の共作曲よりも優先度が低かったせいか、翌年に始まる1988デモのレコーディング・セッションでは3曲とも俎上に載らなかった。また、テープが外部に流出しなかったためブート化されず、そもそもデモの存在すら全く知られていなかった。今回のリマスター盤で初めて陽の目を浴びる完全初登場の音源である。なお、この3曲入りのカセット・テープの復刻版が、米国を中心としたレコード店による年次イベント「レコード・ストア・デイ」の一環で2017年4月22日に発売された。
「アイ・ドント・ウォント・トゥ・コンフェス」は、カセット・デモの録音後ポールもエルビスも再度取り上げた形跡がなく、今までずっとお蔵入りになっていた未発表曲。前述のようにブートでも一切聴くことができなかった上に、タイトルも1994年11月にBBCのラジオ番組でエルビスがひっそり言及したのみで、マニアですらこの曲を把握できていたのはごくわずかであった(逆に「Indigo Moon」という曲の存在が噂されていた)。メランコリックなメロディを持ち、2本のアコースティック・ギターが憂いを増幅させている。歌い出しのタイミングが思うように合わないのが微笑ましいが、その後のヴォーカルは息ぴったり。ミドルのメロディがなかなか秀逸なだけに、デモのまま放置されてしまったのがもったいない限りですね・・・。もし正規にレコーディングされていたらどのように成長していたか、想像してみるのも一興かもしれません。
2.シャロウ・グレイヴ
この曲はエルビスが1995年からライヴで演奏し始め、翌1996年にはソロ・アルバム『オール・ディス・ユースレス・ビューティー』でスタジオ・ヴァージョンを発表した(ポールは不参加)。「タイトルを含め僕よりもポールが多くの歌詞を書いたよ。彼のスタイルじゃないけどね」とエルビスは回顧する。エルビスはアップテンポのロック・ナンバーに仕立てたが、カセット・デモの時点ではテンポはゆっくりで、歌い方も歌詞を確認するかのように丁寧だ。アコースティック・ギターとヴォーカルはエルビスが左チャンネル、ポールが右チャンネルに配されている。短いソロも登場する弾き語りだが、公式テイクでの重々しさは微塵も感じさせない。この曲をポールが歌っているのを聴けるのは初めてのことで、それだけでも必聴。
3.ミストレス・アンド・メイド
「ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー」と同じくエルビス抜きで再録音され、『オフ・ザ・グラウンド』で陽の目を浴びた曲。公式テイクは明るめの曲調のバンド・サウンドに仕上がっているが、このカセット・デモは公式テイクよりキーが2音半も低く、アコギ弾き語りなのもあいまって終始どんよりした雰囲気が漂う。ただし、チャリティ・コンサート「ポール・マッカートニーとその仲間たちの夕べ」(1995年3月23日)でポールとエルビスが再演した際はこのキー&アレンジなので、こちらの方が自然な形なのかもしれない。2人がユニゾンで歌うが、各節の冒頭だけはポールが1オクターブ上の音程をなぞっている。歌詞はほぼ完成しているが、オチにあたる“I'm not your mistress and maid(私はあなたの愛人兼メイドじゃないのよ)”はまだなく“I'm just your mistress and maid(私はあなたの愛人兼メイドに過ぎないのよ)”を繰り返している。半分音割れしているのがいかにもカセットに直接録音した音源らしい。
ディスコグラフィへ