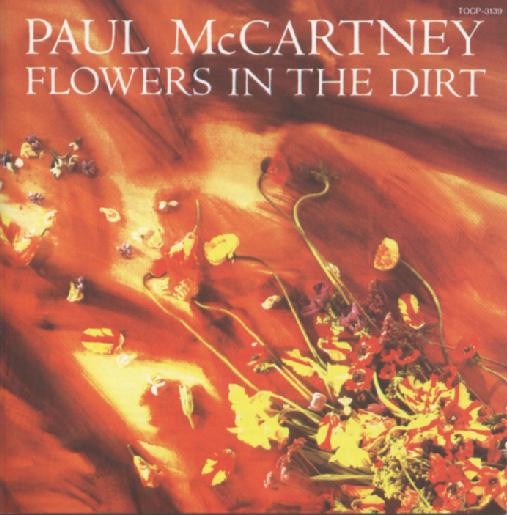| Paul McCartney/ポール・マッカートニー |
| Flowers In The Dirt/フラワーズ・イン・ザ・ダート |
| ザ・ポール・マッカートニー・コレクション (16) |
|
| 1.My Brave Face マイ・ブレイヴ・フェイス 3'17" |
| 2.Rough Ride ラフ・ライド 4'43" |
| 3.You Want Her Too ユー・ウォント・ハー・トゥー 3'11" |
| 4.Distractions ディストラクションズ 4'39" |
| 5.We Got Married 幸せなる結婚 4'56" |
| 6.Put It There プット・イット・ゼア 2'07" |
| 7.Figure Of Eight フィギュア・オブ・エイト 3'24" |
| 8.This One ディス・ワン 4'10" |
| 9.Don't Be Careless Love ケアレス・ラヴに気をつけて 3'17" |
| 10.That Day Is Done ふりむかないで 4'18" |
| 11.How Many People ハウ・メニー・ピープル(チコ・メンデスに捧ぐ) 4'13" |
| 12.Motor Of Love モーター・オブ・ラヴ 6'18" |
| 13.Ou Est Le Soleil 太陽はどこへ? 4'44" |
| 〜ボーナス・トラック〜 |
| 14.Back On My Feet バック・オン・マイ・フィート 4'21" |
| 15.Flying To My Home フライング・トゥ・マイ・ホーム 4'13" |
| 16.Loveliest Thing ラヴリエスト・シング 3'58" |
| (13はアナログ盤未収録) |
|
| 発売年月日:1989年6月5日(英国・Parlophone PCSD 106) |
| チャート最高位:英国1位・米国21位 |
| 全体収録時間:66'31" |
| 本ページでの解説盤:1995年再発売版(日本・東芝EMI TOCP-3139) |
| 最新リマスター盤:こちら |
|
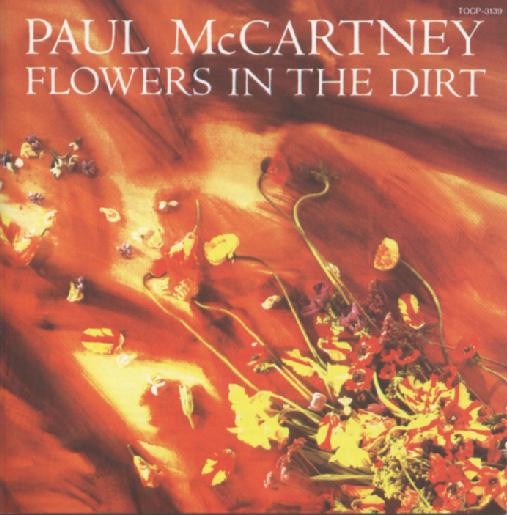 |
このアルバムの収録曲中1〜13はオリジナル版に収録されていた曲で、14〜16は1993年の「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズでの再発売に合わせて追加されたボーナス・トラックです。英国ではアナログ盤とCDの同時発売がすっかり定着していましたが、13はCDにのみ収録されたボーナス・トラックでした。この曲は、アナログ盤では同時期のシングルに回され、リミックス・ヴァージョンを聴くことができました。一方、「ザ・ポール・マッカートニー・コレクション」シリーズでのボーナス・トラック3曲(14・15・16)は1986年〜1988年に録音され、いずれもシングルのB面/カップリングに収録された曲です。
収録曲のうち4曲(1・3・9・10)がポールとエルビス・コステロの共作で、残りがポール1人で作曲した曲です。エルビスは、作曲者としては本名の「デクラン・マクマナス」名義でクレジットされています。
【時代背景】
開始早々に親友ジョン・レノンの死とウイングス解散を経験したポールの'80年代は、決して順風満帆なものではありませんでした。特にアルバムのセールスと評価は、スタジオワークに専念しての制作にもかかわらず徐々に下降線をたどってゆき、ソフトなイメージからの脱却を図ったアルバム『プレス・トゥ・プレイ』(1986年9月発売)もエレクトリック・ポップ色の強い音作りが災いして売上不振を加速させる結果に。さらに、ポールの右腕的存在になっていたエリック・スチュワートとも、セッション中の不和が原因でパートナー関係を解消してしまいました。そんな暗黒時代の真っ只中に、ポールはチャールズ皇太子主宰の慈善事業「プリンス・トラスト」10周年を祝した記念コンサート(1986年6月20日)に出演します。ロンドンのウェンブリー・アリーナにエルトン・ジョン、エリック・クラプトン、ティナ・ターナー、ロッド・スチュワート、フィル・コリンズなどオールスターの顔ぶれが集結したこの日のステージで、トリを任せられたポールは「アイ・ソー・ハー・スタンディング・ゼア」「のっぽのサリー」「ゲット・バック」の3曲を(うち前者2曲はオリジナル・キーで)熱唱。ひさしぶりに人前で痛快なロックンロールを歌えた感動はひとしおだったようで、当時のインタビューでは「陶酔しちゃったよ。最高の気分で、毎晩やってもいいくらい。だからバンドがほしいんだ」と興奮気味に語っています。「プリンス・トラスト」に促される形で、ポールはウイングス解散後遠ざかっていたライヴ活動を再開させてスタジオワークの行き詰まりを打破しようと考え始めました。
スランプにあってもポールの音楽活動は休みなく続けられます。8月には、『プレス・トゥ・プレイ』のプロモーションで渡米した際に出会ったフィル・ラモーンの提案で16と「ビューティフル・ナイト」の2曲を一晩で録音。ラモーンはビリー・ジョエルを手がけたことで有名で、ポールも過去にアルバム『ラム』やシングル「スパイズ・ライク・アス」で一緒に仕事したことがありました。ここで手ごたえを感じたのか、翌1987年からは彼をそのままプロデューサーに据え、サセックスにあるポールの私設スタジオ「ホッグ・ヒル・ミル・スタジオ」でニュー・アルバムを念頭に置いたセッションが始まっています。ティム・レンウィック(ギター)、チャーリー・モーガン(ドラムス)らが参加し4月まで断続的に10曲ほどが取り上げられましたが、生のバンド・サウンドにしたいラモーンと実験的アプローチを試みるポールとの間でやがて軋轢が生じ、一説には殴り合いの喧嘩までした末にアルバム制作は頓挫してしまいました。ビートルズの名盤『サージェント・ペパー』発売20周年を記念した曲「Return To Pepperland」が中核だったことから『The Lost Pepperland Album』の通称で知られる幻の未発表アルバムからは、結局「ワンス・アポン・ア・ロング・アゴー」と14がシングルで発表されるにとどまりました(お蔵入りになった残りの曲も大半が後年引っ張り出されたものの)。
夏になるとポールは一転して、バンドのメンバー探しと自らの原点の再確認を兼ねた週末のジャムに没頭しますが、7月の第3週にはミック・グリーン(ギター)、ミッキー・ギャラガー(ピアノ)、クリス・ウィットン(ドラムス)らと共にロックンロールのカヴァー曲を中心に計22曲を2日間で録音。この時の音源はカヴァー・アルバム『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』としてまとめられ、ポールのアイデアで冷戦下のソ連国内のみ・40万枚限定生産での異例のリリースが実現しました(1988年10月発売)。一方で11月には、水面下で進められてきた未発表曲集『コールド・カッツ』の計画を凍結した上で、ポールのソロ・キャリアで2枚目のベスト盤『オール・ザ・ベスト』が発売されます。こちらは英国で2週連続2位を記録したほか、同月にシングルカットされた先述の新曲「ワンス・アポン・ア・ロング・アゴー」が全英10位まで上昇しています。
【アルバム制作】
この頃ポールが新たな作曲パートナーに指名したのが、エルビス・コステロ。彼との共作を勧めたのはマネージャーのリチャード・オグデンでした。一回り年下で、以前はスタジオやコンサートで何度か会ったことがあるだけのエルビスについて、「同じリバプール出身で、共通項もたくさんあるし上手く行くと思ったよ」とポール。ライティング・セッションはホッグ・ヒル・ミル・スタジオの階上にあるオフィス部屋で行われ、最初は各自が作りかけの曲を持ち寄り2人で仕上げました(ポールの14とエルビスの「ヴェロニカ」)。それから1987年秋に、意見を出し合いながら次々と新曲を一から書き上げてゆきます。曲が完成するとすぐさま階下のスタジオに入り、シンプルなアコースティック・デモを制作するというルーティーンが取られました。ポールが「新鮮だった」「ジョンとやっていた頃を思い出すよ」と振り返るエルビスとの共作曲は公式発表されたものだけでも15曲となり、その中から4曲が最終的に新作に収録されるに至ります。また、14と「ミストレス・アンド・メイド」「ザ・ラヴァーズ・ザット・ネヴァー・ワー」がポール側で、「ヴェロニカ」「パッズ・ポウズ・アンド・クロウズ」「ソー・ライク・キャンディ」「プレイボーイ・トゥ・ア・マン」「シャロウ・グレイヴ」がエルビス側で順次発表されたほか、2017年に『フラワーズ・イン・ザ・ダート』が「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズで再発売された際には「トミーズ・カミング・ホーム」「トゥエンティー・ファイン・フィンガーズ」「アイ・ドント・ウォント・トゥ・コンフェス」が陽の目を浴びました。
当初は正式なレコーディングもエルビスが全面的に関与する予定でした。年が変わると、2人の共同プロデュースのもと一連の共作曲をバンド・スタイルで録音するセッションに着手。今回は『バック・イン・ザ・U.S.S.R.』以来ポールのお気に入りドラマーだったクリス・ウィットンに加え、元アヴェレイジ・ホワイト・バンドのヘイミッシュ・スチュアートと、デヴィッド・ボウイなどのサポートで知られるケヴィン・アームストロングをギタリストに招いています。しかし、ほどなくポールとエルビスの音楽的見解の相違が顕在化し、相変わらず実験好きなポールの発想にエルビスが気分を害される場面もありました(エルビスいわく「曲を書いた時と同じ気軽さと楽しさで一緒にレコードを作れないと思った」)。ポールもそれを認め、エルビスとの共演よりも新たなバンドでのアルバム制作を優先することに。こうして、9曲を終えた所で1988年3月にエルビスとの共同作業は棚上げになってしまいます。
他方、ご破算になり中断されていたポールの単独作のレコーディングは1987年10月に再開されます。'80年代は1人のプロデューサーにアルバム全体を委ねてきたポールですが、そのことが前作『プレス・トゥ・プレイ』では収録曲の没個性化につながってしまった点を反省し、ここでは基本的にポールのセルフ・プロデュースで、曲によって適材適所で複数の外部の人間とタッグを組み色付けしてゆくというポールのキャリア史上初の試みが実践されました。まず声をかけたのが、当時フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドやグレイス・ジョーンズを手がけ一世を風靡していたトレバー・ホーンとスティーヴ・リプソンのコンビ。最新テクノロジーを駆使した音作りにしたい4曲(2・7・11・13)を担当させました。続いてポールのセルフ・プロデュース曲を集中的にこなした後、1988年10月からはミッチェル・フルームとニール・ドーフスマンとの共同プロデュースでエルビスとの共作曲(1・3・9・10)をリメイク。フルームは『キング・オブ・アメリカ』(1986年)以降エルビスの作品にたびたび参加していた間柄でした。さらに、1984年にデヴィッド・フォスターを迎えて録音していた5に手を加えたほか、セッション終盤にはポールがティアーズ・フォー・フィアーズを聴いて腕を買ったというクリス・ヒューズとロス・カラムと共に12でコンピュータ・プログラミングに挑戦しています。
これらのレコーディングのほとんどはすっかりおなじみのホッグ・ヒル・ミル・スタジオで行われ、かたやミキシングは大部分をロンドンのオリンピック・スタジオで、ドーフスマンに依頼して済ませました。演奏面ではヘイミッシュとクリスが引き続きポールを支え、そこにギタリストのロビー・マッキントッシュ(元プリテンダーズ)もクリッシー・ハインドの勧めで合流。リンダも一部の楽曲でコーラスを入れています。ヘイミッシュが「スタジオには最高のスピリット、最高の雰囲気があった」と語るように、4人が意気投合してポールのバンドにメンバー入りするのは時間の問題でした。約1年半じっくり作り上げていったアルバムは1989年2月に完成し、その期間中に20曲を超える新曲が録音されました。うち「グッド・サイン」は最終段階まで収録曲候補に残っていたものの、土壇場で見直されシングルB面送りに。また、15や「ザ・ファースト・ストーン」「ドント・ブレイク・ザ・プロミセズ」「セイム・ラヴ」も同じくシングルに落ち着きます。
アルバム・タイトルは10の歌詞の一節から拝借したもの。それをイメージしたアルバム・ジャケットは、アルバム『タッグ・オブ・ウォー』以来の起用となるブライアン・クラークがコンセプトを考え、油絵具でキャンバスに背景を描きました。その上に花を置いてリンダが撮影した写真(未使用のものも含め、1989年11月〜12月にロンドンのメイヤー・ギャラリーで展示)が使われ、ピーター・サヴィルが全体をデザインしています。インナー・スリーブは黄一色。そして各曲の歌詞と演奏者クレジット、スタジオでリハーサル中のポールとバンドを捉えた写真(カメラマンはハーマン・レナード)、地球環境問題に取り組む人々への謝意と支持のメッセージが印刷された全4ページのブックレットが付属しました。
『Flowers In The Dirt』セッション早見表
【発売後の流れ】
音楽業界に嫌気が差し距離を置いていた元ビートルズの旧友ジョージ・ハリスンが、アルバム『クラウド・ナイン』(1987年)で一足早く衝撃的なカムバックを果たしていただけに、ポールの新譜への期待は高まるばかりでした。そんな中、まず1が先行シングルとして発売されます(1989年5月)。以前のような勢いこそなかったものの、全英18位・全米25位と健闘。そして翌月、ベスト盤やソ連盤を除けば実に3年ぶりとなるアルバム『フラワーズ・イン・ザ・ダート』がついに世に送り出されました。英国では見事1位の座を獲得。これは5年前のアルバム『ヤァ!ブロード・ストリート』以来の快挙でした。米国では最高21位と伸び悩みますが、それでも1年にわたりチャートに居座り続け、ゴールド・ディスク認定されています。シカゴ・トリビューン紙が「全部が素晴らしいとは言わないまでも歓迎すべき復帰」と賞賛するなど評論家たちの間でも軒並み好評で、ポールも「ビートルズ以降の僕の頂点だと言ってるのはお世辞だと思うけど、自分では『バンド・オン・ザ・ラン』くらいのいい出来だと思ってるよ」とご満悦でした。なお、アルバムからの第2弾シングルとして8が、第3弾シングルとして7が、さらに第4弾シングルとして6が発売されていますが、英国では8が18位まで上昇した反面、米国では「ポールは売れない」と判断したキャピトル・レコードがカセット・テープのみでリリースした影響もありすべて不発に終わっています。
アルバムが完成するとポールは早速、来るコンサート・ツアーに向けたリハーサルをホッグ・ヒル・ミル・スタジオで開始します(この時の模様はドキュメンタリー・フィルム「プット・イット・ゼア(フラワーズ・イン・ザ・ダート・スペシャル)」で見ることができる)。ツアー・バンドのメンバーとして招集されたのはリンダ、ロビー、ヘイミッシュ、クリスと、この頃ロビーとクリスの紹介で加入したキーボディストのポール・“ウィックス”・ウィッケンズの5人。そして入念な準備を経た9月26日、ノルウェー・オスロ公演を皮切りに計13ヶ国・全102公演にも及ぶ過去最大規模のワールド・ツアーがいよいよ幕を開けました。ウイングス時代から一新されたセットリストには、演奏することを意識的に避けてきたビートルズ・ナンバーがふんだんに盛り込まれ、初めて人前で披露する「ヘイ・ジュード」「バック・イン・ザ・U.S.S.R.」や『アビイ・ロード』メドレーなどが大変話題となりましたが、一方でヒットを続ける最新作からも6曲(1・2・5・6・7・8)が投入されポールの自信がうかがえます。1990年3月に実現した悲願の日本公演を含め各地のファンの反応は熱狂的で、最終日・1990年7月29日の米国・シカゴ公演を迎えた頃には累計観客動員数は284万人を突破していました。こうして、『フラワーズ・イン・ザ・ダート』とワールド・ツアーの大成功でポールは'80年代の混迷からの鮮やかな復活を成し遂げたのでした。
ワールド・ツアーの販促のため、このアルバムは2度再発売されています。1つは「ワールド・ツアー・パック」(1989年11月23日発売)で、新曲「パーティ・パーティ」を収録したシングルと、様々な付録(ポスター、ツアー日程表、バンドのファミリー・ツリー、ステッカー、ポストカード6枚)が封入されていました。もう1つの『フラワーズ・イン・ザ・ダート -スペシャル・パッケージ-』(1990年3月2日発売)は日本限定リリースの来日記念盤。こちらは、ポールから日本のファンへのメッセージや、ここでしか聴くことのできない「P.S.ラヴ・ミー・ドゥ」など9トラックを収録したボーナスCD付きでした。
【管理人の評価】
仕上げの段階でポール色が薄まってしまったことが売上不振を招いた『プレス・トゥ・プレイ』と、プロデューサーとの確執から頓挫してしまった『The Lost Pepperland Album』。これらの失敗から学んだ教訓を生かして、久々のヒット作『フラワーズ・イン・ザ・ダート』は制作されています。まず前述の通り、複数のプロデューサーから曲ごとに最適な人材を割り当てている点。前作ではミキシングも含め1人にすべてを任せた結果、必ずしも適切なアレンジが施されたとは言えない曲が少なくありませんでしたが、今回はエルビス・コステロとの共作曲なら彼をよく知るミッチェル・フルーム、モダンな味付けならトレバー・ホーンとスティーヴ・リプソン・・・といったように明確に役割分担することでアルバムのカラーが単調になるのを防いだのです。それでいて散漫な印象がなくポールらしさも保てているのは、ポールが全曲でプロデュースに関わったのが秘訣でしょう。
それからエルビスという「物言うコラボレーター」の存在。『プレス・トゥ・プレイ』でエリック・スチュワートが陥ったように、作曲パートナーが「天下のポール・マッカートニーだから・・・」と過度に遠慮してしまうのがポールの悩みでしたが、エルビスは一癖違いました。彼はビートルズ時代の相棒ジョン・レノンのようなタイプで、リスペクトの対象たる人にも臆せず自分の考えをしっかり表明し、時にはポールが持ってきた曲を「これはゴミだ」とまで言い放ったのです。そんな態度がポールに強い刺激を与えたのは想像に難くありません。無論エルビスの意見が全部採用されたわけではなく、レコーディング中途にはむしろポール寄りの解釈に修正されたものの、ともすれば迷走しがちなきらいもあるポールに歯止めをかけ、長らく触っていなかったヘフナーのバイオリン・ベースを再び使うよう勧めるなど積極的にアイデアを出し、エルビスは対等な関係のパートナーとしてアルバムに大きな貢献を果たしました。また、一連の共作曲には屈折したほろ苦いメロディや、豊富な語彙を駆使した意味深な詞作といったエルビスの嗜好が色濃く反映されており、ポール単独では書けない異質の新境地を見せています。
ポールが直後に重要なコンサート・ツアーを控える時にライヴ映えを意識したアルバムを作るのはウイングス以来の傾向ですが、このアルバムでは単にライヴ感あふれるバンド・サウンドであるだけでなく、ビートルズっぽい要素が随所に取り入れられているのが特徴的です。ヘフナーのベースを引っ張り出した1やインド風アレンジが光る8が代表例で、特にライヴ活動をしていた時期のビートルズ・ナンバーをほうふつさせるキャッチーさと懐かしさを感じさせます。一説によるとそれは当時のマネージャーの戦略であり、一緒に作業したエルビスや新たなバンドのメンバーがビートルズを愛聴して育った世代という事実も影響していると考えられますが、何よりポール本人が過去のわだかまりを捨ててビートルズを見つめ直し、その長所を肯定するようになったことが最大の要因でしょう。ビートルズ流のポップ・センスが他系統の収録曲(9・11など)にも浸透しているのは面白い副作用です。
バラエティ豊かで手抜きなしの曲目、その個性を生かしたプロデュース、そして巷の不安を吹き飛ばす溌剌とした演奏とヴォーカルを堪能できるこのアルバムは、ポールの復活劇が遠い昔となった現在もその魅力を輝かせ続けています。シングル・ヒット1・8はもちろん、辛口のスパイスを利かせたエルビスとの共作曲やノリノリのダンス・ナンバー群(2・7・13)、それに年の功と言える味わい深いバラード(4・6・12)とチェックしておきたい強力な曲がいっぱい。明るい曲調が多く全体的に生き生きとしているので、そうした作品を聴きたい方にはうってつけですし、これからポールのソロを聴こうと考えている方にもとっつきやすいと思います。ともあれ、'80年代ポールのスタジオワークのマスト・アイテムとして『タッグ・オブ・ウォー』に続き広くお勧めします。強いて難点を挙げるとすれば、ミッチェル・フルームが反省しているようにミキシングの過程で施された'80年代特有の音処理が今聴くと若干古くさく響くのが玉に瑕なのですが・・・(汗)、雰囲気をぶち壊すほどの違和感はないはずです。ちなみに、私は1・4・5・8・9・11・13(ボーナス・トラックだと15・16)が特に好きです。
なお、このアルバムは2017年にリマスター盤シリーズ「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」の一環としてキャピトルから再発売されました。初登場の未発表音源がたっぷりのボーナス・ディスクが追加されているほか、関連映像を収録したDVDやボーナス・ダウンロード・トラックも付いてくるので(一部仕様のみ)、今から買うとしたらそちらの方がお勧めでしょう。解説はこちらから。
アルバム『フラワーズ・イン・ザ・ダート』発売20周年記念!収録曲+aを管理人が全曲対訳!!
【曲目解説】
1.マイ・ブレイヴ・フェイス
ポールとエルビス・コステロの共作。2人で白紙から書き上げた最初の曲で、ポールいわく「'60年代風のフィーリング」あふれるビートルズっぽいポップ・ナンバー。1988年2月にエルビスと初期ヴァージョンを録音したがボツとなり、同年10月にミッチェル・フルームとニール・ドーフスマンとの共同プロデュースでリメイクした。ポールはビートルズ時代のトレードマークだったヘフナーのベースを23年ぶりに披露している。他にヘイミッシュ・スチュアートとロビー・マッキントッシュがギターで、クリス・ウィットンがドラムスで参加。
アルバムに先行してシングル発売され、英国で最高18位・米国で最高25位とポールの復調を印象付けた。プロモ・ヴィデオにはポールに関するものなら何でも持っていると豪語する日本人の収集家が登場し、盗みを働いた挙句に逮捕されてしまうという皮肉たっぷりな筋書き(苦笑)。1989年〜1990年のワールド・ツアー(通称「ゲット・バック」ツアー)と1991年の一連のシークレット・ギグ(一部公演を除く)では最新ヒットとして取り上げられた。ベスト盤『ザ・グレイテスト』にも収録。このアルバムで私が一番好きな曲です。何物にも代え難い!
2.ラフ・ライド
ファンキーなギター・リフが耳に残るダンス・ナンバー。打ち込みドラムスを使用した凝った音作りだが、共同プロデューサーのトレバー・ホーンとスティーヴ・リプソンは、仕事に時間をかけるのを嫌ったポールに依頼されわずか2日で完成させている。フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッド風のミックスも用意されたとのこと。ライヴでの再現が難しい曲調ながら1989年〜1990年の「ゲット・バック」ツアーでセットリスト入りした。本作の来日記念盤『スペシャル・パッケージ』にはツアー・リハーサル音源も収録(初出はCDシングル「フィギュア・オブ・エイト」)。
3.ユー・ウォント・ハー・トゥー
ポールとエルビスの共作で、作中で唯一エルビスとのデュエットを堪能できる。恋煩いする男の脳内でささやく天使(ポール)と悪魔(エルビス)の声を対立させた詞作で、ロマンティックなフレーズに辛辣な返答をぶつける手法はビートルズ時代のジョン・レノンとの共作に通じる。一時は両パートをポールが歌う予定だったが見直された。回転木馬をイメージしたイントロとエンディングがユニーク。プロデューサーはポール、エルビス、フルーム、ドーフスマンの4人。
4.ディストラクションズ
「サムボディ・フー・ケアーズ」「フットプリンツ」の系譜を継ぐ枯れた味わいのあるアコースティック・バラードで、ポールのセルフ・プロデュース作。間奏のソロ以外のアコギを弾いたヘイミッシュがお気に入りに挙げている。ポールが「ドリス・デイの映画みたい」と評するオーケストラ・アレンジはクレア・フィッシャーが担当。その名前からポールは金髪のロサンゼルス娘だと想像していたが、実はグレーのひげを生やした50代の紳士だと分かった途端リンダ(架空の女性に嫉妬していた?)が突然絶賛し始めたという面白いエピソードも残る。ヘイミッシュやクリスと共にスタジオ入りするポールを捉えたプロモ・ヴィデオを、ドキュメンタリー・フィルム「プット・イット・ゼア」で見ることができる。
5.幸せなる結婚
デヴィッド・フォスターをプロデューサーに招いた1984年秋のセッション(他に「アイ・ラヴ・ディス・ハウス」「Lindiana」を録音)で半分ほどできていた曲に、ドーフスマンの補プロデュースで1988年12月にオーバーダブを加えて仕上げた。エレキ・ギターはピンク・フロイドのデヴィッド・ギルモア、ドラムスはデイヴ・マタックス。前半はスパニッシュだが、中盤から重厚なロックに曲調が切り替わり好対照を成す。自らの経験を踏まえて結婚とは何かを示す歌詞も重い。
アルバムからシングルカットされる計画もあったが、エディット・ヴァージョンを収録したプロモ・シングルが配布されたにとどまり実現しなかった。そのためプロモ・ヴィデオも存在し、ステージでの演奏シーンとツアー会場各地の模様を交互に映している(とんねるずの石橋貴明が、来日公演の映像で一瞬登場)。1989年〜1990年の「ゲット・バック」ツアーで演奏された。
6.プット・イット・ゼア
アコギ弾き語りを基調としたポールお得意の小曲。ポールのセルフ・プロデュースをドーフスマンが手伝っている。ストリングス・スコアをジョージ・マーティンが書き下ろし、エンジニアにはジェフ・エメリックと懐かしい顔ぶれが揃う。バディ・ホリーの「エヴリデイ」を参考に、ポールは膝をたたく音をパーカッションに用いた。タイトルの“Put it there if it weighs a ton(1トンもするなら/それをそこに置いてごらん)”は、亡き父ジェームズが握手する時にたびたび口にしてきた言葉。
1990年2月にアルバムからの第4弾シングルとなり、全英32位まで上昇した(米国ではチャート・インせず)。プロモ・ヴィデオでは様々な父親と幼い息子の親しい関係が描かれている。1989年〜1990年の「ゲット・バック」ツアーで披露した際には、エンディングにビートルズ・ナンバー「ハロー・グッドバイ」のコーダをくっつけていた。アナログ盤はここまでがA面。
7.フィギュア・オブ・エイト
このロック・チューンもまた、ホーンとリプソンを共同プロデューサーに迎え短期間で完成させている。完璧主義の2人を前に、ポールはあえてエンディングを定めずラフに歌った。元々の演奏時間は5分以上あったが、アルバム収録にあたり短く編集している。リンダがウイングス以来久々にムーグ・シンセを弾く。
1989年〜1990年の「ゲット・バック」ツアーではオープニング・ナンバーに抜擢され、ツアーを象徴する1曲に成長した。アルバムからの第3弾シングル(1989年11月発売)でもあり、ファン泣かせの6種類の仕様(B面もジャケットもすべて異なる)で乱発したが、英国で最高42位・米国で最高92位と振るわず。シングル・ヴァージョンはポール・“ウィックス”・ウィッケンズを含むツアー・バンドで1989年9月に再録音したもの。ライヴの模様を楽しめるプロモ・ヴィデオでもシングル・ヴァージョンが採用された。個人的には、アルバム・ヴァージョンより躍動感のあるシングル・ヴァージョン(もしくはライヴ・ヴァージョン)の方をお勧めします。
8.ディス・ワン
“this one(今この時)”と“this swan(白鳥)”の言葉遊びから、白鳥に乗るヒンドゥー教の神ハレ・クリシュナを想起して書いた曲。同時に、疎遠状態にあった旧友ジョージ・ハリスンへのラヴ・ソングでもある。当初はスローなバラードだったが、テンポを上げてインドっぽいアレンジを施した。東洋の管楽器にも似た音色のハーモニカはジャド・ランダーが吹いている。リンダ、ロビー、ヘイミッシュ、クリスが勢揃いし、中でもヘイミッシュのソウルフルな追っかけコーラスは聴き所。プロデューサーはポール。
1989年7月にアルバムからの第2弾シングルとして発売され、米国では94位止まりだったものの全英18位のスマッシュ・ヒットとなった。一方、12インチシングル「フィギュア・オブ・エイト」(一部仕様のみ)にはクラブ・ミックスを収録(未CD化)。プロモ・ヴィデオは曲のイメージをそのまま再現したエスニックなものと、ライト・ペインティングを多用したサイケデリックなものの2種類が制作されている。1989年〜1990年の「ゲット・バック」ツアーでセットリスト入りした。
9.ケアレス・ラヴに気をつけて
ポールとエルビスの共作。エルビスが「2人で書いた曲で最も奇妙かも」と述懐するように、美しいコーラスを擁するメロとマイナー調の不気味なサビとを行き来する。プロデューサーはポール、エルビス、フルームでドーフスマンが部分的に補佐。エルビスも参加した1988年2月の初期ヴァージョンが上手く行かず、同年10月にバッキング・トラックのみ総入れ替えする形でリメイクした。夜になると行き先も知らせず外出する恋人のことがあまりに心配で、暴漢に襲われてはいないかなどと夜通し妄想を繰り広げる情けない主人公が登場する歌詞が、私のお気に入りポイントだったりします。
10.ふりむかないで
ポールとエルビスの共作。病状が悪化していた祖母の葬式に出られない可能性への不安を、エルビスが遠回しな表現でつづる(その予感は後に的中)。それゆえエルビスの思い入れが非常に強く、ポールがヒューマン・リーグ風のサウンドを提案してきた時には怒りに駆られたという。結局はエルビスが意図していたものに近い、ニューオーリンズの葬送曲を意識したアレンジに落ち着いた。ビートルズの「レボリューション」にも参加したニッキー・ホプキンスがピアノを弾いている。プロデューサーはポール、エルビス、フルーム、ドーフスマンの4人。最後の一音でノイズが左側からザザッと聞こえてくるのですが、これって私のCDだけですか?(2017年のリマスター盤『フラワーズ・イン・ザ・ダート』では消えている)
11.ハウ・メニー・ピープル(チコ・メンデスに捧ぐ)
以前から憂えていた地球環境問題を訴えた曲。チコ・メンデスはブラジルで熱帯雨林の保護に尽力した運動家で、1988年12月に彼の暗殺を知ったポールは制作中だったこの曲を捧げ、その死を悼んだ。また、地球サミットを記念したオムニバス・アルバム『アースライズ〜ロックが地球を救う』(1992年6月発売)にも提供している。陽気なレゲエ・アレンジなのはジャマイカで休暇中に書かれたからとのこと。共同プロデューサーはホーンとリプソンで、ドーフスマンが補プロデュース。フリューゲルホルン・ソロはポールが演奏している。
12.モーター・オブ・ラヴ
アナログ盤のラストを飾るのは、暖かく美しいバラードの大作。レコーディング(1989年1月)は収録曲中最後に行われ、行き詰まっていた未完成のテープを共同プロデューサーのクリス・ヒューズとロス・カラムに委ねた。ミドルエイトはポールがセッション中にあっという間に作り上げ、ヒューズを驚嘆させたという。前作『プレス・トゥ・プレイ』以上に緻密な打ち込みサウンドが展開されるが、作業の煩雑さと退屈さにアナログ人間のポールは再び懲りてしまった。神への感謝を題材にした曲想から、クリスマス・ソングとしてのシングル発売も検討されていた。
13.太陽はどこへ?
当時流行していたハウス・ミュージックをポールなりに解釈したダンス・ナンバーで、共同プロデューサーのホーンとリプソンの影響も色濃い。リプソンのアイデアによるベーシック・トラックに、ポールが'70年代から温めていたと言われる3文のフランス語の歌詞を乗っけた。デジタルを前面に押し出す中、ポールがのこぎりを挽く音がSEに使用されている。
この曲はCDにのみ収録されたボーナス・トラックで、アナログ盤としてはシングル「フィギュア・オブ・エイト」のB面でリミックスを聴くことができる。リミックスは公式発表されたものだけでも4種類存在し、先述のシングルや来日記念盤『スペシャル・パッケージ』に収録されたほか、米国や一部ヨーロッパでは単独でシングルカットされた(チャート・インせず)。ファミコン・ゲームの世界が舞台のプロモ・ヴィデオが曲に負けじと大変楽しい。数あるマッカートニー・ナンバーでも指折りにダンサブルかつ異色で、私にとってはある意味「マイ・ブレイヴ・フェイス」よりも病みつきな1曲です(笑)。特に後半の低音ヴォーカルとの掛け合いが大好きですね。ウエ、ウエー、レソレ、レソレー♪
〜ボーナス・トラック〜
14.バック・オン・マイ・フィート
1987年11月16日に発売されたシングル「ワンス・アポン・ア・ロング・アゴー」のB面だった曲。ポールが粗方書いていたものにエルビスが歌詞の手直しを加え、2人の共作曲の中では最初に発表された。主人公にホームレスの男を据えた演劇仕立ての詞作がシニカル。1987年春にフィル・ラモーンをプロデューサーに招き、『プレス・トゥ・プレイ』に続くアルバム(通称『The Lost Pepperland Album』)の制作を目的としたセッションで録音された。エレキ・ギターはティム・レンウィック、キーボードはニック・グレニー=スミス、ドラムスはチャーリー・モーガン。2017年に「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズで再発売された『フラワーズ・イン・ザ・ダート』ではボーナス・ダウンロード・トラックとなっている。
15.フライング・トゥ・マイ・ホーム
シングル「マイ・ブレイヴ・フェイス」のB面だった曲。アカペラのタイトルコールで始まり、一転してハードなギター・ロックへと展開してゆく。ポールの鼻にかかったリード・ヴォーカルが風変わりで面白い。『フラワーズ・イン・ザ・ダート』セッション中の1988年5月にポールのセルフ・プロデュースで録音され、ヘイミッシュとクリスが演奏で、その2人とリンダがコーラスで参加。2017年に「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズで再発売された『フラワーズ・イン・ザ・ダート』ではボーナス・ダウンロード・トラックとなっている。この曲のシャッフル調のリズムが、私が愛聴するDREAMS COME TRUEのシングル曲「WHEREVER YOU ARE」のそれによく似ているなぁと常々思っている次第です。
16.ラヴリエスト・シング
CDシングル「フィギュア・オブ・エイト」(一部仕様のみ)のカップリングだった曲で、来日記念盤『スペシャル・パッケージ』にも収録されていた。1986年8月21日にニューヨークのパワー・ステーションでレコーディングされ、フィル・ラモーンがプロデューサーをつとめた(当日は「ビューティフル・ナイト」の初期ヴァージョンも録音)。ラモーンの人脈でビリー・ジョエルのバック・バンドからデヴィッド・ブラウン(ギター)、リバティ・デヴィート(ドラムス)とデヴィッド・レボルト(シンセサイザー)が演奏に加わる。シンプルで粗削りながらも味わい深い、ポールの甘くせつない歌声に心打たれるラヴ・バラードだ。2017年に「ポール・マッカートニー・アーカイブ・コレクション」シリーズで再発売された『フラワーズ・イン・ザ・ダート』ではボーナス・ダウンロード・トラックとなっている。
ディスコグラフィへ