
Jooju Boobu 第95回
(2006.2.04更新)
How Many People(1989年)

更新が遅れて申し訳ございません。今回の「Jooju Boobu」は、『Distractions』『Back On My Feet』に続いて(後者はボーナス・トラックですが・・・)再び1989年の名盤「フラワーズ・イン・ザ・ダート」から取り上げたいと思います。「Jooju Boobu」の序盤ではなかなかこのアルバムの収録曲を紹介する機会がなかったので、この辺で反動が来ています(苦笑)。今回ご紹介するのは、アルバムではB面、後半に位置する『How Many People』です。この曲は何と言ってもポールが大好きなレゲエのリズムを用いているのが特徴的であり、ひときわ印象に残るのですが、この一見して陽気な曲の裏側には「ある事柄」に対するポールの確固たる考えが見え隠れしています。それはどんなものなのか?ポールはどんな思いでこの曲を作ったのか?その辺を中心に、この曲の特徴・魅力を語ってゆきましょう。
この曲が収録されているアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」自体に関しては、少し前にも『Distractions』の項で取り上げているので解説を省略してもいいのですが・・・(笑)、一応このページからご覧になった方のために簡単に概要を振り返っておきます。「もう読み飽きた!」という方はこの部分は読み飛ばしてください(汗)。


「フラワーズ・イン・ザ・ダート」の一連のレコーディングが始まったのは1987年中旬のこと。ご存知のように、当時のポールは深刻な売上不振に陥っており、音楽活動全体においてスランプ状態でした。ヒュー・パジャムをプロデューサーに迎えた前作「プレス・トゥ・プレイ」は見事玉砕し、その後フィル・ラモーンと組んで制作していたアルバムのセッションも頓挫し幻に終わってしまいます。この窮地を脱しようと、ポールは従来の考えを大幅に転換します。アルバム全体を誰か1人にプロデュースさせていたことが結果的に収録曲個々の魅力をそいでしまっていたのを反省して、曲ごとに一番ふさわしいプロデューサーを選ぶことにしたのです。また、「プレス・トゥ・プレイ」での無機質一辺倒のアレンジがリスナーのポール離れを招いたことを考慮し、実験的なテイストは一部残しつつも、全体的にはよりライヴ感あふれるバンド・サウンドに仕上げています。折りしも、しばらくやめていたコンサート活動の再開をもくろんでいたこともあり、「元気がなくなった」と評論されていたポールに溌剌としたキャッチーなポップやロックが戻ってきました。当時異色のコラボレーションとして話題を集めたエルビス・コステロとの共作&共演はその傾向をさらに後押しし、エルビスの辛辣さ含んだ助言はポールにビートルズ時代のスタイル(特にコンサート活動にいそしんでいた初期の頃)を見直させるきっかけにもなりました。このように'80年代の凝ったスタジオワークから、ライヴでの演奏やビートルズ時代を積極的に意識したストレートな音作りに回帰したポールの新譜─つまりこれこそ「フラワーズ・イン・ザ・ダート」─は、じっくり腰をすえた長期間のレコーディングを経てセッション開始から約2年が経過した1989年6月に世に放たれました。そして、ポールの方針転換はしっかりと実を結びます。英国1位をはじめ世界中で大ヒットしたのはもちろん、相次ぐシングルカットやそれに合わせた活動も注目され、ポールはミュージック・シーンの中心に鮮やかに返り咲いたのでした。その好況の中、アルバムのセッションに参加したミュージシャン仲間とバンドを結成してウイングス以来久々のワールド・ツアー(悲願の来日公演含む!)に出てますますブームに乗ったのはいまだ記憶に新しいでしょう。ポールは「評論家がちやほやと褒めるのはお世辞だと思う」と謙遜していましたが、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」がポールのソロ・キャリアにおいて今なお燦然と輝き続ける名盤であることは、誰もが肯定することでしょう。ポールが長い長い混迷期を抜け出してようやく華麗な復活を遂げた、その何よりの証しです。
・・・と、ありきたりな解説を今一度してみました(笑)。まぁ、ポール・ファンの皆さんなら既にご存知の話ですよね。そして、そんな渾身の1枚に収録されているのが今回取り上げる『How Many People』です。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」は先述のように、ポールらしさが満開したキャッチーなポップやロックと、'80年代テイストが満開した実験的なダンスナンバーが程よく共存し、さらには円熟味を帯びたスロー・バラードや屈折感たっぷりのエルビス・コステロとの共作曲があって、実は「プレス・トゥ・プレイ」に負けず劣らずのバラエティ豊かなラインアップが揃っています。こうした多彩な曲たちを1人のプロデューサーに委ねなかったのが勝因なのですが、『How Many People』はこの多彩ぶりにさらに拍車をかけている張本人なのでは、と私は思います。というのも、この曲はリズムに、誰もが一目置いてしまう特筆すべき異色のスタイルを持ち合わせているからです・・・!典型的なポップやロック、バラードとは違うものを・・・。
それが何であるかは、この曲を聴いたことのある方には説明不要でしょう。冒頭でも触れたように、「レゲエ」です。『How Many People』と言えばすぐにレゲエを連想する方がきっと大勢だと思われるほど、この曲に鮮烈なイメージを与えています。ポールがレゲエのリズムを取り入れた楽曲の代表例として挙げてもいいくらいでしょう。・・・と、ここでポールをよく知らない方は「なぜポールがレゲエ?」と疑問を持つに違いありません。確かに、世間一般的なポールのイメージからすると接点のなさそうなジャンルです。ラテン系の伝統的なリズムにロックが融合して、'60年代後半にジャマイカで誕生したレゲエ。独特の拍を伴う癖の強いビートは、'70年代になって政治的なメッセージを込めた歌詞と共にジャマイカ国内のみならず世界的な注目を得るようになり、いまや様々なミュージック・シーンに顔を出すほどの影響力を持っています。日本では、最も有名なレゲエ・アーティストであるボブ・マーリーを思い浮かべる方が多いでしょう。と来ると、ますます「ポール・マッカートニーとボブ・マーリーに一体どんな接点が!?」と思えて仕方ないでしょうが(汗)、実はポールとレゲエには思った以上に深い関係があるのです。以下に説明してみましょう。
昔から今まで、様々なジャンルの音楽に幅広く関心を示し曲作りに生かしているポールですが、もちろんレゲエも例外ではありません。実はポール、そして妻リンダは知る人ぞ知る大のレゲエ好きです。特にボブ・マーリーのファンだそうで、マーリー没後に制作された名曲『One Love』のプロモ・ヴィデオに出演しているほどです。また、ポールがDJをつとめたラジオ番組「ウーブ・ジューブ」(1995年)ではマーリー以外にもジャマイカのレゲエ・アーティストの曲がたくさん流されました。レゲエゆかりのジャマイカには別荘まで持っていて、ちょくちょく休暇に訪れるそうです。そしてポールは、単にレゲエを好んで聴いているだけではなく、時折レゲエに影響を受けた曲を自ら書いてもいます。ビートルズ時代の『Ob-La-Di,Ob-La-Da』はレゲエが注目されていなかった頃に前身であるスカのリズムをいち早く取り入れた曲ですし、ウイングス〜ソロを通じて『C Moon』『Good Times Coming』『Simple As That』などでレゲエを下敷きにした曲を発表しています(リンダのシングル『Seaside Woman』もそうですね)。また、カヴァー曲『Love Is Strange』『赤鼻のトナカイ』や自作の『Tomorrow』『Silly Love Songs』までもをレゲエ・アレンジで演奏したこともあり、レゲエはポールの数ある音楽の引き出しの中でもしばしばよく使われるものとなっています。このような背景を見れば、ポールがレゲエをやっていても実は何の驚きもないんですね(苦笑)。


そんな生粋のレゲエ・フリークであるポールが、'80年代も終わりに差し掛かった頃に『How Many People』で再度レゲエに手を染めた、というわけです。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」セッションで未発表になってしまった音源の中には、ジョニー・キャッシュとの共作『New Moon Over Jamaica』やエリック・スチュワートとの共作『Don't Break The Promises』のようにレゲエ・アレンジで演奏した曲があり、この頃のポールもレゲエ熱が冷めやらず・・・といった所でしょうか(ちなみに2曲とも共作者による公式発表版ではレゲエを取り入れていないのが面白い)。この『How Many People』については、ポールによるとなんでもジャマイカに滞在中に書いたそうです。海外で休暇を楽しんでいる間に曲想を得るのはポールにとって珍しくない出来事ですが、この時は「あそこに行ったらレゲエをやらないわけにはいかないよ」というコメントを残しています。ずいぶん単純な発想ですね(汗)。レゲエの本場でレゲエナンバーを書くことへの並々ならぬ気合いが入ってか、この曲はそれまでにないほど“典型的な”レゲエに仕上がりました。誰が聴いてもまさに「これぞレゲエの王道!」と思う、こてこてのリズムです。かつてレゲエに挑戦した『Ob-La-Di,Ob-La-Da』『C Moon』があくまでレゲエを“彷彿させる”程度にとどまっているのに対し、こちらはステレオタイプ的な視点でレゲエを捉えてみました、という感じです。3拍目にアクセントを置くのは当然のこと、レゲエ・ビートを形式的に模写したかのようです。これはポールに劣らずレゲエ好きだったジョン・レノンがフィーリング一発でレゲエを解釈したのとは正反対のアプローチですし、ある意味、マーリーなど現地のレゲエ・アーティストの曲よりも「レゲエ」しています。ポールのレゲエへの敬愛ぶりが十分に伝わってきますが、あまりにも理路整然としていて本場レゲエに見られる泥臭さ・粘っこさが微塵も感じられないのは否めません(汗)。結果的にはいかにも西洋人がレゲエを模倣してみました、という感じになっていて、さすがのポールも奥深い雰囲気までは研究し切れなかったのかな、と思わせます。まだ『C Moon』の方が理屈っぽくなく、その辺をつかめていたかもしれませんね・・・。まぁ、英国生まれの人ですから仕方ないですか。しかし、レゲエうんぬんはひとまず置いておいて、この曲のメロディの持つ親しみやすさはやはりポールにしか書けない所があります。単純明快なコード進行も聴きやすいですし、思わず一緒に歌ってしまいそうな覚えやすさが光っています。レゲエとしては不十分な面がありますが、ポップナンバーとしては申し分ない出来です。
理路整然さを強調しているのが、レゲエ・ビートを刻むドラムスです。実は、この曲ではドラムスは生演奏ではなくコンピュータ・プログラミング、つまりいわゆる打ち込みドラムが使用されています。'80年代からどんどん押し寄せてきたデジタル化の波にポールも「プレス・トゥ・プレイ」前後から積極的に乗り出していたのでなるほど理解できますが、この曲をプロデュースした面子を見ればますます納得できるはずです。この曲でポールと共同プロデューサーを務めたのは、トレバー・ホーンとスティーヴ・リプソン。コンピュータ・サウンドによる斬新なアレンジをレコーディングに導入して一世を風靡した2人です。特にトレバーは、元々在籍していたイエスや、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドなどをプロデュースしたり、前衛音楽のプロジェクト「Art Of Noise」を立ち上げたりと、画期的な試みが話題を呼んでいました。新し物好きのポールは「フラワーズ・イン・ザ・ダート」セッションで彼らを招き入れ『Rough Ride』『Ou Est Le Soleil?』のプロデュースを任せていますが、そんな打ち込み主体のファンキーで実験的な曲が得意な陣営の手によって、この曲の命運は決定付けられました。さて話を戻すと、ただでさえ形式ばったレゲエのリズムをしている上に、無機質な音色で正確なビートを刻む打ち込みドラムなので、「本場のレゲエ」ぽくなくなるのも無理のない話です。レゲエ特有の持ち味が薄れてしまい、イマイチ面白みに欠けている感もあります(汗)。ポールのレゲエ好きが分かるだけに、肝心のベーシック・トラックを打ち込みにしてしまったのは惜しいです。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」でもこればかりは人選ミスだったかも・・・?ドラムス以外のトラックも非常に整頓されていて、トレバーが手がけたシンセ・サウンドが目立ちますが、これも曲調にちょっと合っていない気がします。ぽわーっとした暖かみのある音なのが幸いですが・・・。
また、打ち込み以外の面ではポールがほとんどの楽器をワンマン・レコーディングしている点も特異です。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」ではバンド・サウンドへの回帰を目指すべく、後にポールのツアー・バンドのメンバーとなるミュージシャンたちと一緒にセッションをした・・・というのは先にお話しましたが、ここではその路線を無視しているかのようです(ギタリストのヘイミッシュ・スチュワートがコーラスのみの参加というのは少し異常事態)。後のツアー・バンドのメンバーでは他にクリス・ウィットンがシンセドラムで参加しているのみです。挙句にリンダさんからタンバリンまで取り上げているほど(苦笑)。折角仲間を従えているのだから、この曲はバンド編成で、基本生楽器でやったらレゲエらしい泥臭さが出て効果的だったのでは?と思ってしまいますが、ポールは整然とした感じにしたかったのでしょうね。打ち込みドラムと共に曲の基調となるのは、そんなポールが弾くピアノとギター。ビートが3拍を強調しているのに対し2拍・4拍を強調・・・というのはレゲエのツボをついた演奏で、そこはさすがポール。分かっていますな。ややハードなギター・フレーズはポールか、それともスティーヴ・リプソンか?ピアノは後半アドリブも飛び出します。多様な楽器の中で特筆すべきなのは、間奏に登場するフリューゲル・ホルンでしょう。実はこれもポールが自ら演奏しています!金管楽器を演奏するイメージがないのと、素人っぽさを感じさせない演奏なので、改めてそのマルチ・プレイヤーぶりに脱帽してしまいます(まぁ後に「裏庭の混沌と創造」を作ってしまう人ですから、ね)。この曲についてポールは「もっと複雑にしなきゃと思った」と語っていますが、シンプルにして正解だったと思います。打ち込み主体で複雑で難解なサウンドにしていたら、もはやレゲエなんてどこかに飛んでしまっていますから・・・(汗)。アレンジ的に不十分とはいえ、ポールらしいポップな側面を前面に出すことに成功しています。
演奏以上にポップな側面が出ているのがヴォーカル面です。ここでのポールのヴォーカルは陽気そのもの。実に明るく楽しそうに歌っています。これは、ポールから思い描くレゲエのイメージに沿っているのでしょう、きっと(笑)。我々日本人もレゲエやボブ・マーリー、ジャマイカと言うとカリブの陽気な雰囲気を想像してしまいますが・・・それと同じ思考ですね(実際はそれほど陽気一色でもないのは言うまでもなく)。ポール流の“典型的”レゲエには図らずもぴったりはまっていますし、キャッチーなポップとして考えても的確なスタイルです。そんな中でも場所によって細かに声質を変えているのは気が利いています。ハスキーだったり、のびのびと歌ったり、力強く歌ってみたり。間奏のアドリブはマーリーを意識したか?と思わせますね。マーリーにはあまり似ていませんが(苦笑)。コーラスにはリンダ、クリス、トレバーの他にレゲエ・アーティストのジャー・バニーを参加させるという力の入れようで、変な所で本格的です。でもホント楽しそうですよね。そして、セカンド・ヴォーカルとしてクレジットされているのがヘイミッシュ。楽器こそ弾いていないものの、第2節以降その渋い喉でポールと肩を並べる存在感をアピールしています。


ここまで、この曲の一番の特徴であるレゲエの側面から語ってきましたが、それだけではこの曲の存在意義を半分しか知ったことになりません。陽気で楽しいレゲエの裏側に、ポールが込めたある思いが隠されているからです。これを読み解かないと、この曲の魅力を味わい尽くしたことにはなりません。・・・そうです、もう1つ重要な側面は、詞作です・・・!
ポールが紡ぎ出す歌詞と言えば、主に楽観的な恋愛を歌ったラヴソングや、物語性あふれるキャラクター・ソングが一般的であり、これらは私たちがポールに抱く典型的なイメージともなっています。しかし、ポールは常にこういう他愛のない詞作ばかりを手がけていたわけではありません。ポールは時々、イメージとは正反対の内容を含んだ歌詞も書くことがあるのです。それが、社会性を帯びたメッセージ・ソングです。ビートルズでの相棒であったジョンが平和を訴えた曲をたくさん世に送り出したこともあり、ポールのメッセージ・ソングというのはなかなか想像がつきにくいですが、社会的・政治的なテーマを取り上げた曲は決して多くはないものの存在します。特に、ポールの場合多いのが、長年提起している環境問題・動物愛護についてのメッセージ・ソングです。スコットランドの田舎に農場を持ち、犬や馬や羊を飼っている動物好きのポールは、'70年代初頭にリンダの影響でベジテリアン(菜食主義者)になり、以降ことあるごとに動物虐待への反対を表明し菜食主義を広めていますが、そうした姿勢をポールは音楽活動においても示すことがあるのです。代表的な例がウイングス時代の『Wild Life』(1971年)でしょう。この曲では動物を酷使する人間社会に警鐘を鳴らし、動物愛護の重要性を訴えています。ところが、この時はあまり話題になりませんでした。当時のポールの窮状や、収録されたアルバムが不発に終わったことも一因ですが(汗)、何より'70年代当時は現在に比べて世間が環境問題・動物愛護に関心を持っていませんでした。ポールが打ち出したメッセージは画期的だったのですが、残念ながらその詞作が注目されることはありませんでした。こうした無反応ぶりにショックを受けたのか、ポールは以降一部の例外を除いてメッセージ・ソングをほとんど書かなくなります。
やがて時は流れ'80年代後半。世界はようやく地球環境問題にまなざしを向けるようになりました。地球温暖化や大気汚染、酸性雨やオゾン層破壊といった人間社会が及ぼした様々な弊害が深刻に悪化してきたからです。それを受けて各国政府は重い腰を上げ、地球規模で一丸となって拡大防止に取り組もうという動きが出つつありました。もちろん、ポールもこうした事態を憂慮していました。そして「『Wild Life』の頃は無視されてしまったけど、今ならみんな訴えを聞いてくれる・・・」と、長年封印してきた環境問題を提起するメッセージ・ソングを再び書くことを決めたのです。そんな姿勢が形になったのが、この曲『How Many People』でした。

ポールがこの曲を捧げたブラジルの環境保護運動家、チコ・メンデス。
さて、日本での副題には「チコ・メンデスに捧ぐ」とあります。また、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」のブックレットにもこの曲の歌詞の前に「ブラジルの熱帯雨林保護運動家 チコ・メンデスの名声に捧げます」と記載されています。このチコ・メンデスという人物は、ブラジルで熱帯雨林の保護に尽力した運動家です(1944〜1988、シコ・メンデスとも)。ブラジル北西部にあり、約50万の人がゴム樹液の採取で生計を立てるアクレ州で育ったメンデスは、ごく普通のゴム樹液採取者でしたが、牧畜産業による熱帯雨林の伐採が地域の自然環境悪化につながることにいち早く気づきました(アクレ州では牧草地を広げるためにゴムの木が大量に伐採されていた)。そこでゴムの木の「採取保護区」を確立しようと、国内の同業者を結集してゴム樹液採取組織を設立し、そのリーダーになりました。彼が牧畜関係者に対して貫いた非暴力活動は国際的な注目を浴び、開発業者を告発してさらなる伐採を未然に防ぐなど具体的な成果も収めましたが、1988年12月に心無い人間の手により暗殺され、44歳の短い生涯を閉じます。メンデスの死は世界中に衝撃を与え、音楽界でも彼の活動をテーマにした曲がいろいろ作られ、その死を悼みました。そして遠く英国で、このことを何らかの形で知ったポールもまた深いショックを受け、強い憤りを覚えました。既に1988年初頭までにはレコーディングが済んでいたようですが、ポールはチコ・メンデスの活動を通して地球の環境保全を訴えるために、急遽この曲─『How Many People』をメンデスに捧げることにしたのでした。ブラジル人に捧げる曲がジャマイカで書いたレゲエナンバー、というのも微妙にニアミスした不思議な取り合わせですね(汗)。
この曲の歌詞は、直接的にチコ・メンデスに関することは歌っていませんが(録音時期を考えれば納得ですね)、奇遇にもメンデスが訴えてきた環境保護への思いをつづったメッセージ・ソングとなっています。自然破壊によって多くの人が犠牲になり不幸のまま暮らしている現実を見つめつつ、地球を守ってみんな平和に暮らそう、という提起が含まれています。「何人もの人々が/命を奪われたのだろう」「たくさんの権利を今すぐおくれ/普通の人々が平和に生きてゆくのを見たい」など、シンプルながら胸に強く響くメッセージです。誰しもが抱く、好環境下での幸福の追求が普遍的に歌われています。そんなシリアスなメッセージをハッピーなレゲエに乗せて歌うという所が、最後は楽観的な心の持ち主であるポールらしいですが、歌詞を吟味してから聴くと一見陽気にしか聞こえないそのヴォーカルも、地球環境への憂いを込めて切実に訴えているようにも捉えることができます。冒頭のせつなげなシャウトは、ポールの心からの叫びなのかもしれません。そもそもレゲエは、マーリーに代表されるように政府や日常生活への不満を歌にするスタイルが主流ですが、何かを訴求するという点はこの曲の詞作と符合します。きっとポールは本場レゲエの詞作になぞらえたのでしょう。さすが、単なるレゲエ好きに終わっていないようですね。
地球環境問題が深刻になる中、この曲を書き、さらに環境保護運動家であるチコ・メンデスに捧げたことは、ポールにとって大きな転換点となりました。元来より環境保護・動物愛護の主義者でしたが、これ以降ポールは音楽活動の面でも、それ以外の面でも積極的にこの分野で社会的影響を与える主張をするようになったからです。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」のジャケットに再生紙が用いられたり、同アルバムの来日記念盤で日本のファンに向かって「地球を守ろう!」というメッセージ(説教とも言う)を送ったのはその皮切りに過ぎません。1993年のアルバム「オフ・ザ・グラウンド」とその後のツアーは、そうした姿勢が顕著に現れた恰好の例です。動物実験を非難した『Looking For Changes』、毛皮のコートを否定する『Long Leather Coat』などなど・・・。妻のリンダも、屠殺に疑問を投げかけた『Cow』という曲を歌ったり、ベジテリアン向けの料理本を出すなど夫に負けない動物愛護ぶりを見せました。リンダ亡き後の新妻ヘザーも動物愛護の立場の人ですが、ポールがヘザーに惹かれたのも、そうした背景があるのかもしれません。いずれにせよ、この曲を境にポールの環境保護・動物愛護・菜食主義の熱烈なアピールが本格始動したのでした・・・。たとえばマクドナルドやケンタッキー・フライドチキンへの抗議とか、ですね。
ポールなりに環境保護を真剣に訴えたこの曲は、アルバムに収録されるだけでなく、その後もポール自らの手によってしっかりアピールが行われました。中でも、1992年6月にブラジル・リオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国際連合会議」いわゆる「地球サミット」を記念して発売されたチャリティ・アルバム「アースライズ〜ロックが地球を救う」(1992年・現在廃盤、入手困難)にポールがこの曲を提供したことは有名でしょう。ジュリアン・レノン(ジョンの息子!)をはじめU2やエルトン・ジョン、クイーンなどそうそうたる顔ぶれが楽曲を提供したこのオムニバスにおいて、この曲は知名度はないもののポールの確固たるメッセージを託したのでした。「アースライズ」は映像版も制作され、ヴィデオとして出回っていますが(未DVD化で現在入手困難)ポールはそちらの方にもこの曲を提供しています。ただし、ヴィデオではアマゾン川流域の現況を映像と字幕で紹介するシーンのBGMとして使用されているだけで、ポール本人は登場しません。普通のポール・ファンが見ても、あまり面白くない内容です(苦笑)。環境問題を訴えるために制作されたヴィデオなので無理はないですし、その趣旨は忘れてはいけませんね。ちなみに私はアルバム、ヴィデオ共に未入手です。これを揃えているポール・ファンは相当なマニアと言えます(笑)。


そして、当時ポールがコンサート活動の再開を目指していたことにあいまって、この曲は幾度ものリハーサルを経て各国のTV番組などのスタジオライヴで披露されました。「フラワーズ・イン・ザ・ダート」のプロモーションになるだけでなく、環境問題の喚起にもなるので、ポールにとっては大変都合のよい曲だったに違いありません。もちろん、この時はツアー・バンドのメンバー(ポール含めて6人)での生演奏です。ポールはピアノを弾き、ヘイミッシュがベースを代奏、リンダとポール・“ウィックス”・ウィッケンズがキーボード、ロビー・マッキントッシュがエレキ・ギター、クリスがドラムスを担当しています。基本的にはオリジナルのスタジオ・ヴァージョンに準じたアレンジで、シンセ・サウンドもウィックスが再現していますが、打ち込み主体だったオリジナルに比べて明らかに生き生きとした、レゲエっぽい演奏に生まれ変わっているのは気のせいだけではないはずです。無機質さは全くありません。こうなることなら、最初からバンドメンバーと共にすべて生楽器で録音しておけばよかったのに・・・(汗)。ポールもピアノを弾く振り(?)をしながらアドリブ交じりで歌って、とってもリラックスして楽しそうです。リハーサルやスタジオライヴでの音源・映像は現在入手困難ですが、公式ヴィデオ「Put It There」や各種ブートで楽しむことができます。また、1989年1月にヘイミッシュとクリスと3人で行ったリハーサルの音源はポールのラジオ番組「ウーブ・ジューブ」で放送され、これもブートで聴くことができます(「Flowers In The Dirt Sessions」などに収録)。ポールがピアノを弾いて曲を引っ張る形のシンプルなテイクで、ヘイミッシュとクリスのためにか途中でコードを歌いながら確認しています。その後は公式テイクが後付でつなげられているようですが・・・(汗)。このようにリハーサルやスタジオライヴといった準備期間で散々取り上げられたのにもかかわらず、なぜかコンサート本番では一度も演奏されていないのが不思議です。ポールは「フラワーズ・イン・ザ・ダート」を宣伝するために、1989年9月にスタートした一連のワールド・ツアー(通称「ゲットバック・ツアー」)では収録曲の多くを取り上げたのですが、この曲は漏れてしまっています。ポールにとってはファンに対して「地球を守ろう!」とアピールするこれ以上ない材料なだけに、本当に不可解な話です。ビートルズナンバーを少し削ってでも、この曲はセットリストに入れた方が自身の信念のためにもよかったのでは・・・?意外と、環境問題・動物愛護を前面に打ち出した「オフ・ザ・グラウンド」の時のツアーで演奏していたらはまっていたかもしれませんね。ドラマー以外は「ゲットバック・ツアー」と同じメンバーだし。
・・・と、今回は「レゲエ」と「地球環境問題」という2つのキーワードを元に『How Many People』を語ってきました。ポールの大好きなレゲエと、ポールが常々関心を持ち続けている地球環境問題。共にポールにとって重要な要素だけに、ポールの強い思い入れが伝わってきます。私個人的には、主に前者の点でこの曲が好きです。とっても陽気で楽観的な感じが素直に楽しめます。打ち込みサウンドがやや強調されすぎなのと、ポールのワンマンぶりは少し難点ですが(苦笑)。まぁ、ポールのレゲエ大好きぶりはよく分かります。『C Moon』ほどポール流に消化できてはいないですが、間違いなくポールのレゲエの代表格ですね。そして後者の環境保護の観点ですが、チコ・メンデスの非業の死に捧げたメッセージは心に残ります。いまだに各地で公害が発生し環境問題の絶えない地球ですが、解決には一人一人の意識が大切なんだ、ということを考えさせてくれます。ポールの環境保護・動物愛護の運動(特に強硬なベジテリアン節)や、自作曲にやたらと環境問題を持ち込んでくる姿勢には賛否両論あり、私も閉口する所も無きにしも非ず・・・ですが(汗)、この曲でポールが言わんとしていることはよく理解できます。「オフ・ザ・グラウンド」期の環境ソングのように曲と歌詞がミスマッチしていたり、妙に嫌味たらしかったりもしていないですし。元々レゲエは不満を述べる音楽ですから、ポールがメッセージ・ソングに仕上げたのは納得行きますね。それだけに、ライヴ本番で取り上げていないのが残念です。『Looking For Changes』よりやってほしいです(笑)。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「エスニックな宇宙空間」。ますますマニアックになりますが(苦笑)、お楽しみに!
(2010.12.01 加筆修正)
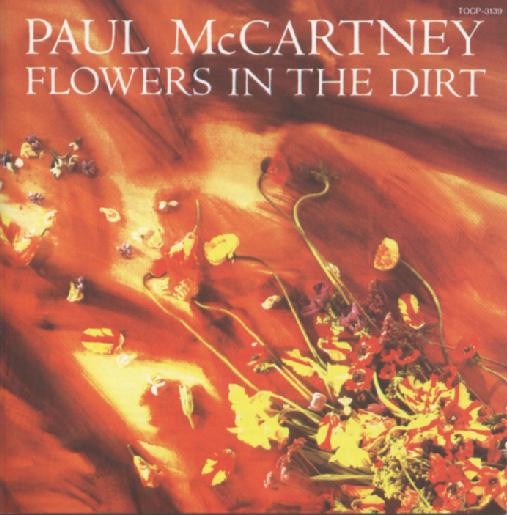
アルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」。ポールが復活を遂げた1989年の名盤!いろいろな趣の曲が、ポールらしいバンド・サウンドでまとまっています。