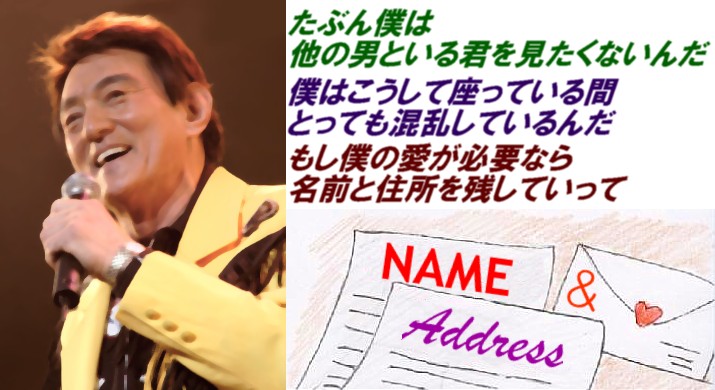
Jooju Boobu 第74回
(2005.11.21更新)
Name And Address(1978年)
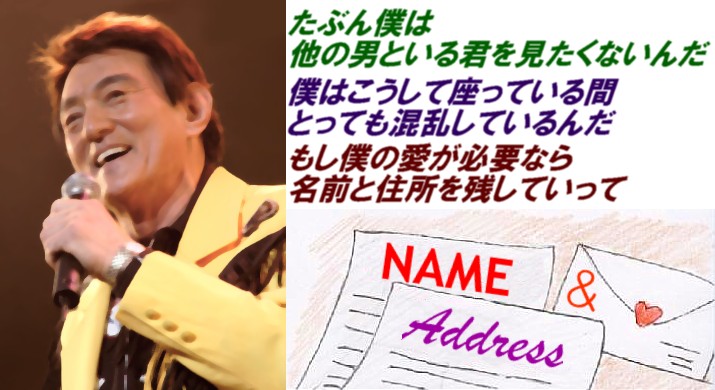
最近更新が遅れている「Jooju Boobu」です(汗)。期待されている皆様には本当に申し訳ないです!まぁ今回の場合は、日曜日が当サイトの1周年とかぶってしまって、そちら関連の更新を手がけていたもので・・・(苦しげな言い訳)。でも、がむしゃらでも更新してゆきますので、どうか今後もお付き合いの程よろしくお願いします・・・。
えぇー、話がそれました。さて、前回急にマニアック路線に戻ったこのコラム。今回もまた、マニアックな曲の紹介です!ポール・マニアが思わずにやりとしそうな曲を取り上げます(苦笑)。そして今回は再び、私のお気に入りのアルバム「ロンドン・タウン」(1978年)からの選曲です。既にもう何曲も(A面はほぼ全曲)紹介している所に私の思い入れの強さを感じさせます・・・!さて、変てこな『Backwards Traveller〜Cuff Link』が紹介済みの今、アルバム中最もマニアックな曲といえば・・・もうお分かりですね。そう、『Name And Address』です。実に無名でマニアックで、その内容ゆえかコアなファンからも目をつけられない悲しい曲ですが(汗)、ポールの遊び心というかトリビュートやパロディ精神のようなものと、ポールの混乱・混迷ぶりが同時に見て取れるという、何とも興味深い曲でもあります。今回は、そんなこの曲を語ってゆきます。相変わらず語ることが少なくてすぐ終わりそうですが、お付き合いください(笑)。
思えばビートルズ解散後のポールのキャリアで、「ロンドン・タウン」ほど様々な要素を抱えた複雑なアルバムはないでしょう。それは、一連のレコーディング・セッションの流れを見れば分かります。アルバムの制作開始当初のウイングスは、絶頂期を体験した5人編成でした。1977年春、世界中で注目されるバンドに一躍成長して成功の喜びにあふれる中、ポールはメンバーをスタジオに召集します。そして、始めは地元ロンドンで、その後休暇も兼ねてカリブ海はヴァージン諸島の洋上に浮かぶヨットでレコーディングを行います。「Water Wings」という仮題がつけられたニュー・アルバムは、順調に完成に向けた作業が進んでいるかのように見えました。しかし、カリブ海からロンドンに戻ってしばらくして、リード・ギタリストのジミー・マッカロクがグループを脱退。セッションの中休み中の出来事でした。脱退直前にジミーが不参加のまま行われたスコットランドでのセッション(1977年8月)では、あの名曲『Mull Of Kintyre(夢の旅人)』が録音されています。そして、この『Mull Of Kintyre』を最後に、ドラマーのジョー・イングリッシュも脱退してしまいます。相次ぐメンバーの脱退に困惑したポールですが、アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」以来の3人編成に戻ってしまったウイングスを建て直しアルバムを完成させるべく、居残ったデニー・レインと愛妻リンダと3人で残りの楽曲を録音しました(当時リンダは長男ジェームズの出産を控え産休に入っていたため、実質的にはポールとデニーの2人によるセッション)。さらに、ポールの一人録音『Cuff Link』も加えて、セッション開始から1年かけてようやく「ロンドン・タウン」は発表されるに至りました。
このように、ジミーとジョーの脱退を挟んでバンド編成が曲によってまちまちな「ロンドン・タウン」ですが、さらに曲の持つ印象もそれぞれ全く異なるので余計その内容は複雑化しています。全体的にはポールとデニーの共作活動で生まれた英国・アイルランドのトラッド(伝統音楽)風ナンバーが多い中で、5人編成で録音されたウイングスらしいダイナミックなロックやポップもあり、メンバー2人の脱退後の曲に見られるラフで中途半端な仕上がりのものもあり、さらに数年前にポールが書いていた『Girlfriend』や、ポールの一人多重録音の『Cuff Link』『I'm Carrying』もあり・・・。各曲の持つ表情は実に個性的で、出来上がるまでのプロセスも違うのですが、完成したアルバム「ロンドン・タウン」が、全体的に落ち着いた空気が流れる、タイトル通りに英国の香りが漂うまったりした雰囲気に統一されているのは大変不思議な結果です。これこそポールの、ウイングスのマジックなのでしょう。そしてこれぞ、紆余曲折の末に生まれた「ロンドン・タウン」の大きな魅力なのです。
そんな複雑な経緯を辿ってきた「ロンドン・タウン」において、今回紹介する『Name And Address』はどの系統に入るのでしょうか?この曲は、ジミーとジョーが脱退した後、1977年秋のロンドンでのセッションでレコーディングされています。つまり、この曲でのウイングスはポール、リンダ、デニーの3人編成です。そして、曲の持つカラーを見てみれば、『Backwards Traveller』と同じ部類の、「ラフで中途半端」な仕上がりの曲に当てはまります。不完全バンドという事実の影響をもろに受けてしまったような、未完成のまま世に出てしまった感の強い曲です。しかし、思い出してみてください。3人編成の時期に録音された曲でも、しっかりした演奏で完成度の高い状態で発表されたものもあることを。『Deliver Your Children』や『Children Children』、そして『Girlfriend』なんかがその例です。ということは、この曲が「ラフで中途半端」である理由は、不完全バンドの影響が100%というわけでは、決してないのです。あの名盤「バンド・オン・ザ・ラン」を完成させた3人ですから、よく考えれば疑いの余地のないことなのですが・・・(汗)。では、なぜこの曲は、『Deliver Your Children』などとは違いラフな格好で世に出ることになったのでしょうか・・・?
・・・その答えは簡単、ポール自身がそうなるよう狙っていたからです。そう、しっかり仕上げられるものをあえてラフなままアルバムに収録してしまったのです。この曲には、ラフであることの意義がちゃんと存在していた、ということです。この時点で、同じ「ラフで中途半端」カテゴリーに入る『Backwards Traveller』とは少し毛色が違うことが分かりますね。『Backwards Traveller』は、メンバー脱退の混迷の中、まるでやけくそになって半ば無意識的に未完の曲を放り込んだという流れですから。意図的か、意図的でないかの差は大きいです。それでは本題に戻って、ポールはなぜこの曲にラフなアレンジを施したのでしょうか?どんな理由でラフにする必要があったのでしょうか・・・?それは、冒頭でも触れた、この曲一番のキーワードである「パロディ」が教えてくれます。この曲、実は一種のパロディ・ソングであり、ラフさはそのパロディの味を引き出すためのスパイスだったのです!そして、そのパロディの元ネタとは・・・ずばり、エルビス・プレスリーでした。
ロックを聴く者なら誰もが知っている一大有名スター、エルビス・プレスリー。言わずもが、'50年代〜'60年代に独特の歌声で数々のヒット曲を生みロック・アイドルとして世界に君臨し、死後30年以上経っても今なお多くのファンに愛されているのみならず、そのスタイルやスタンダード・ナンバーの数々が後世のロック・アーティストに多大な影響を与えたことでも知られています。そんな中、もちろんポールにとってもエルビスはアイドル中のアイドルでした。ビートルズとエルビスと言えばジョン・レノンとエルビスの不仲の話が有名ですが(汗)、ポールはエルビスの楽曲を青年時代に聴き親しみ、バディ・ホリーやリトル・リチャード、チャック・ベリーなどと同じくらいの影響を受けていました。それは、ロックンロールのカヴァー・アルバム「CHOBA B CCCP」「ラン・デヴィル・ラン」をはじめビートルズ時代から現在に至るまで多くのエルビス・ナンバーをカヴァーしていることや(『That's All Right Mama』『It's Now Or Never』『All Shook Up』など)、自作曲(ぱっと浮かんだ所では『Lady Madonna』『That Would Be Something』『Eat At Home』辺り)でエルビス風ヴォーカルをしばしば取り入れていることからも明白です。
そんなエルビスが、1977年8月16日に42歳という若さで亡くなります。一時代を築き上げたスターの死は世界中にショックを与えた出来事でしたが、それはポールにとっても同様でした。ちょうどこの頃のポールといえば、「ロンドン・タウン」のヴァージン諸島でのセッションを終え、ロンドンで休暇を過ごしている時期でした。先述のジミーとジョーの脱退の1ヶ月前という頃です。・・・と来て、そろそろ接点が見つかりましたね。この曲『Name And Address』のセッションが行われるのが、それから2ヶ月経過した1977年10月からですが、どうもポールはこの曲をエルビスの死に触発されて書いたと思われるのです。そして出来上がったのが、これからお話しするようなエルビスっぽさたっぷりのスタイル。まさに、この曲は急逝したエルビスへのポールなりのトリビュートだったのです。ポールとエルビスの直接的な対面はビートルズ時代の一度きりでしたが、二度と会えなくなってしまったアイドルへの追悼を込めて、ポールはエルビス風の曲に再び取り組んだのでした。
さらに、この曲は単なるトリビュートでなく、そこから一歩踏み出す形となりました。それが、先述の「パロディ」です。ポールは、尊敬の念を抱いているエルビスを、ただ追悼するだけでなく、そっくり真似てしまおうと思ったのです。ポールのエルビスへの敬愛ぶりは「追悼」の一言で済ませられる程の伊達じゃなかったのです。こうして、エルビスの死後わずか2ヶ月で、ポールはエルビスのパロディ・ソング・・・他でもない『Name And Address』を生んでしまいます。短期間でさらさらとエルビスそっくりのスタイルの曲を書けてしまうとは、ポールの才能を感じさせます。まして、「単純なロックンロールほど書くのが難しい」(ポール・談)というのに・・・!

それでは、ここからはこの曲のどの辺りがエルビスのパロディなのかを、多方面から見てゆきたいと思います。まずは曲調とメロディ。この曲は、もちろんエルビスの歌いそうな曲・・・ということで、エルビスをほうふつさせるオールド・スタイルのロックンロールです。「ロック」ではなく、「ロックンロール」と言う言葉がぴったりの、昔懐かしい雰囲気です。それこそエルビスの昔のレコードから引っ張り出したような・・・そんな感覚が味わえます。その秘訣が、使用されているコードの少なさ。なんと、3コードで出来上がっているのです!ポールと言えば、ロックナンバーでもコードを極力減らして明朗さを出すことが多いですが、ここではロックンロール黎明期の再現に一役買っています。さすがエルビスの曲を貪り食うように愛聴してきただけある。メロディも、単純明快なものになっており、シンプルそのものです。「ラン・デヴィル・ラン」辺りに入っていてもおかしくないですね(苦笑)。
続いて演奏面ですが、ここでさっき論議した「ラフで中途半端」な作風が反映されています。この曲を聴けば誰もが感じると思いますが、アルバムで聴くことのできるこの曲の演奏は、完成テイクというよりは、まるでレコーディング中途のリハーサルでの演奏をそのまま入れたかのようなものがあります。同じロックナンバーの『I've Had Enough』とその迫力を比べてみれば違いは明らかです。緊張感なく、だらだらと力が抜けたかのように流している所は、「やる気あるのか?」と思わず言ってしまいそうです(笑)。また、曲構成もまだ練られていないかのように、曲後半では歌のないインスト・パートが多くなり未完成といった印象が強いです。普通なら、どこかの節を繰り返して歌う所なのに・・・。この辺は、短期間で書いたツケが回ってきたのかもしれませんが。そして、極め付けがエンディング。これが何とも出鱈目であります。唐突に、というよりぐだぐだのままあっけなく終わってしまう演奏は、「途中で投げ出しちゃいました」という感じ丸出しです(汗)。あっと驚くエンディングはポールらしいと言えばそうですが、ちょっとやりすぎな感があります・・・。さらには、各楽器のミックスも凝っておらず適当に済ませてしまったようです。他の曲と比べて一段と音質が悪いのがその証拠です・・・。このように、本来であればもっと磨いて『I've Had Enough』のような大迫力のロック・チューンに仕上げることもできたはずなのに、あえて中途半端な格好で「完成」としています。これは・・・、もう言わずもが。エルビスの歌うオールディーズの雰囲気を出すための演出なのです。'50年代のぶっつけ本番的レコーディングを再現すべく、ポールはこの曲をラフな形で録音し、未完成のまま世に出したのです。はい、ようやく結論が書けましたね(笑)。すべては、エルビスのパロディにするためにポールが狙って仕込んだアレンジだったのです。「ラフな方がエルビスらしいからこのまま入れよう!」とデニーに提案するポールの声が聞こえてきそうです。『Backwards Traveller』のラフさとは全く違う意図的な根源であることが、お分かりになりましたか?
演奏するのは、先述の通り3人編成の「不完全バンド」のウイングスです。そのため、デニーのギター以外のすべての楽器をポールが演奏しています(キーボードはリンダの可能性もなくはないですが・・・産休でしたからねぇ)。「バンド・オン・ザ・ラン」そしてこの時期に見られるポールのワンマン・レコーディングが、ここでも楽しめます。エルビスのパロディということで、ごくシンプルなバンドサウンドで構成されていますが、デニーとポールだけで演奏しているせいかスカスカでたどたどしい感もあって、これがまたいい味になっています。ギター・ソロは間奏で2回登場しますが、デニーでしょうかポールでしょうか?・・・多分ポールかも。バンドの危機的状況ではドラムスはいつもマルチ・プレイヤー・ポールの出番。たまに演奏できるチャンスをもらえる喜びからか、いつも以上にやる気が感じられるドラミングです。これが例のように素人ぽいけどツボは妙におさえている「ヘタウマ」状態で、間奏での盛り上げ方は上手だと思います。ベテランドラマーのジョーに比べると明らかに下手なのは確かですが(苦笑)、ロックンロールぽさが出ているからよしとしますか。途中からは、オルガンの音色のキーボードが入りますが、これがいかにも単調で素人っぽさたっぷりです。まるでリンダが弾いているみたいで微笑ましいです(これがポールの演奏だったら、リンダの弾き方を熟知していた!?)。
そして一番注目がヴォーカルです。ここで「エルビスのパロディ」の肝である、エルビス節が披露されているからです!ポールの歌うヴォーカル・スタイルは、まさにエルビス・プレスリーそのもの。ビートルズ時代からエルビスの曲を聴き、好んで歌ってきたポールらしく、見事に独特の声質を再現しています。本家に比べれば、ちょっと野太さが薄れて控えめに歌っている感じはしますが・・・(ポールの地声に若干近い)。それでも、聴けばすぐに「エルビスだ!」と分かる仕上がり。まるで、エルビスの物まねをしているか、カラオケで歌っているかのようなパロディぶりです。曲調にのせて軽く跳ねるように歌われていて、なんだか楽しそうです。後年ロックンロール・アルバムでエルビスの曲をカヴァーするポールですが、それらに負けず劣らず敬愛ぶりが伝わってきますね。蛇足ですが、実はもう1曲ポールがエルビスのパロディに徹底した曲があって、そちらはアルバム「マッカートニーII」に収録されています。言わずもが、『Bogey Music』なんですが(笑)。そちらはより「おふざけ」的で、何重にもエルビス風の太いヴォーカルを重ねて滑稽なオールド・ブギーにしていますが、こちらは実際のエルビス像に近いスタイルで歌われているので、本来の目的である「トリビュート」「追悼」の念はよく出ています。なお、コーラスはデニーの他に産休中のリンダも担当しているようです。部分的に登場しメリハリをつけていますが(特に“my love〜”が印象的)、ヴォーカルの陽気さを強調しているかのようです。このコーラスも、節によって入る箇所が異なったり、適当にハモっている所があったりと、リハーサルっぽさが出ています。ファンの間ではよく言われる話ですが、“my love〜”の部分は1999年の「ラン・デヴィル・ラン」のタイトル曲『Run Devil Run』でのコーラス“ラーァーァーァーン”をほうふつさせます。この曲の方は実際のリンダの声で、『Run Devil Run』はそうでないというのが面白いですね。
以上のように、エルビスのパロディが強く意識された曲調・演奏・ヴォーカルが展開されていて、それゆえのラフさ・中途半端さがあるのですが、ここで一筋縄で行かないのがこの曲のもう1つの隠された要素です。そして、その要素はまさに「ロンドン・タウン」セッション特有のものなのです・・・。それが露骨に表れたのが、詞作面です。この曲の歌詞は、一見ごく普通のラヴ・ソングで、エルビスや'50年代の歌手の歌うロックンロールにありがちな、ある意味ベタな失恋ソングなのですが、その中に「僕はこうして座っている間、とっても混乱しているんだ」というくだりが登場します。さらに、「僕は住所も持たないひとりぼっちさ」と孤独感をにじませる一節も出てきます。これらは、単なるラヴ・ソングで片付けることもできるのですが、どうも当時のポールの心境が吐露されたと思われるのです。それを裏付けるのが、この時期のポールの混迷ぶりです。この曲を書いた時期は、ウイングスが活動を休止していた頃。その最中に、例のジミーとジョーの相次ぐ脱退事件が起きるのですが、ウイングスの急激な環境の変化にポールがショックを受けたのは想像に難くないでしょう。前年に全米ツアーを成功させ世界の頂点に立った5人編成があっけなく崩壊してしまったのですから・・・。その予兆は、ポールたちがカリブ海で洋上セッションを行っていた頃に既に表れていましたが(ジミーはドラッグにおぼれトラブルを起こし、ジョーはホームシックに陥ったそうな・・・)、メンバーとの不和や脱退事件に対するショックの強さが「混乱している」「ひとりぼっちさ」という一節に出てしまったのではないでしょうか。思えば、同時期に書かれてこの曲のように未完成ぶりを見せる『Backwards Traveller』では「僕は時の旅人、歌いながら航海し、月に向かって泣きむせぶ」と歌われています。いつもは個人的な心情を歌詞に露出することのないポールですが、この時期は珍しく混乱が詞作に色濃く出てしまったのでした。思えば、「ロンドン・タウン」セッションで2人の脱退後に録音された曲は、詞作はともかくどこか内省的な雰囲気が漂います。これが、遊び心たっぷりのパロディ・ソングの裏側に秘められたいわば「影」の部分です。
次はマニアックな話を・・・と行きたいのですが、実はこの曲に関してはもう語ることがありません(汗)。アウトテイクも発見されていませんし、ライヴでも取り上げられていません。他に特筆すべき点がないのが、マニアック・ソングならではですね(笑)。そうそう、1つだけ強いて挙げるなら、この曲を誰か(すみません、詳細不明・・・)がカヴァーしているヴァージョンがあって、音源を持っているのですが、こちらはエルビスそのまんまの野太い声でポール以上にパロディしています。
聴いていて楽しいこの曲は、パロディを狙った安直さとラフさが災いしてか、アルバム「ロンドン・タウン」が再評価されつつある現在においても、注目されることがありません。それどころか、アルバムを散漫にしている張本人だと名指しされることもあります(汗)。しかし、「散漫さ」・・・言い換えて「多彩さ」はアルバムの制作の成り行き上どうしようもないものです。そして、先述のようにその多彩さがあるにもかかわらずアルバムのカラーが全体的に統一されているという不思議なマジックがあるため、この曲がアルバムを散漫にしているということはありません。かえって、アルバムのヴァラエティを増やしている点では、重要で貴重な存在です。「ロンドン・タウン」特有のトラッドナンバーばかりだと、確かにそれはそれでいいのですが、どこか冗長に思えませんか?この曲は、同じくアルバム内で「場違い」呼ばわりされる『I've Had Enough』と共に、アルバムのマンネリ化を防ぐ楽しいスパイスとなっているのです。こうした曲があるおかげで、「ロンドン・タウン」は程よく心地よいまったりムードが堪能できるのです。
そしてそんな難しい理屈抜きに、この曲は単純に楽しいのです。エルビス・プレスリーのパロディ・ソングなんですから。同じくエルビスのパロディである『Bogey Music』は完全におふざけであり、悪く言えば皮肉っていますが(汗)、この曲ではよい意味でのパロディ、「トリビュート」に近いパロディがされていて聴きやすいし、愛情も込めてあるし、大げさでない点純粋に楽しめると思います。ポールのエルビス好きにはホントに脱帽ですね。バディ・ホリーへの敬愛ぶりもすごいですけど、こちらも徹底的です。それほど、エルビスがポールに与えた影響は計り知れないのでしょう。最近はエルビス風の曲を披露しないポールですが、またこういった感じのパロディを発表してほしいですね。
ここからは個人的な話を。この曲は、ポールの諸作で一番のお気に入りであるアルバム「ロンドン・タウン」収録曲ということもあり、結構好きな曲ですね。アルバム自体聴くのでよく聴く曲でもあります。私は、どちらかと言うとお気に入りが『With A Little Luck』までの曲(つまり、A面と『With A Little Luck』)に固まっていて、B面の曲は地味な面もあってめちゃくちゃ大好きという所までは行かないのですが・・・、この曲はB面の諸作でも指折りに好きですね。『Don't Let It Bring You Down』よりも好きなのは確かです。はい、マニアックでしたね(苦笑)。そして、この曲の個人的イメージというのがありまして、毎回この曲を聴くと、私はなぜかポールでもエルビスでもなく、日本のロカビリー・シンガーの佐々木功(ささきいさお)を思い浮かべてしまいます(笑)。念のために紹介しておくと、あの「宇宙戦艦ヤマト」の歌の人です。なんか、最初聴いた時から佐々木功の顔が浮かんできて仕方ないんですよね。エルビスより日本のロカビリー・シンガーの声に近いからかもしれません。ヴォーカル的には尾藤イサオの方が近いかなと思いますが・・・(笑)。『Press』の場合は最初聴いた時からジャッキー・チェンが思い浮かんで消えませんし(苦笑)、私の感性はちょっとおかしいのかもしれません(汗)。
というわけで、前回に引き続いてのマニアック路線、いかがだったでしょうか?ライトなポール・ファンの皆さんはついてゆけなかったかもしれませんね(汗)。
さて、次回で私のお気に入りの第6層はいよいよ終了です。そんな次回の曲のヒントは・・・「スタート地点」。これまたマニアックです(笑)。お楽しみに!
(2009.11.28 加筆修正)

アルバム「ロンドン・タウン」。複雑なカラーを秘めながらも、全体的には英国の香りがする、まったりと落ち着いた雰囲気に仕上がった、ウイングスの隠れた名盤!