
Jooju Boobu 第73回
(2005.11.17更新)
Don't Be Careless Love(1989年)

今回から3曲、「Jooju Boobu」は連続してマニアックな選曲となります(苦笑)。第6層はこれまでもマニアックな曲が目白押しでしたが、そのラストスパートをかけるべくマニアックに臨みたいと思います!さて、その先陣を切るのは、ポールの「復活」作として知られる名盤「フラワーズ・イン・ザ・ダート」(1989年)で、恐らく一番マニアックではないかと思われるナンバーをあえて取り上げたいと思います。その曲とは・・・『Don't Be Careless Love』です。邦題は「ケアレス・ラヴに気をつけて」。東芝EMIの担当者さんにしてみれば素直な直訳だったかもしれませんが、実は正しくは「Don't Be Careless,Love」=「不用心にならないで、恋人よ」という意味であり、カタカナ言葉「ケアレス・ラヴ」は迷訳となってしまいました(笑)。
と、タイトルの話はどうでもいいとして、この曲は1つ特筆すべき事柄があります。それは、エルビス・コステロとの共作曲であるということです。'80年代後半、自らの音楽の方向性を見失っていたポールを軌道修正させ、復活に導く要因となったのがコステロとはよく言われますが、ポールの音楽活動にとってキーマンとなる人物との共作活動の中で、この曲は生まれました。そして、そのコラボレーションの成果はこの曲にも大きく影響したのでした・・・。コステロの影響がどのように入ってきたのか?その辺を中心に、今回はマニアックながらもどこか惹かれるこの曲について語ってゆきます。
このコラムでは、既にコステロとの共作曲を1曲取り上げています。そう、『My Brave Face』ですね。コステロとはどんな人なのか、そしてコステロとポールとの共作活動の経緯についてはその時に触れましたので、詳しいことは省きます。しかし、一応アルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」ができるまでの時代背景も含めてざっとおさらいしておきましょう。
'80年代後半をチャートでの不振の連続という苦難で迎えることとなったポール。様々なプロデューサーや共演者を招いて、試行錯誤のレコーディングを続けていましたが、いずれも上手くはいかず、セールス面でも苦戦しました。そんな中、ポールと知り合うこととなったのがエルビス・コステロでした。すぐに意気投合した2人は、やがて本格的な共作活動を始めます。ところがそのコステロが、これまでソロ・キャリアでポールが共作や共演をしてきた人たちとは明らかに違った性格と持ち味を備えた人物であったのは有名な話ですね。それまでの共演者はみんな天下のポール・マッカートニーを前にして「イエスマン」になってしまっていたのに、コステロだけは自分の意見をしっかり持ち、決してポールにこびることはありませんでした。一筋縄で行く人間ではなかったのです。いつぞやはポールが持ってきた曲を「ゴミだ」とまで言い放ったほどです。ポールにとってこれほど強烈な出来事はなかったでしょう。共同作業中には辛らつな言葉をかけられっぱなしですし、なかなか譲歩してくれないですし。これまで「裸の王様」状態で音楽活動をしてきたポールにとっては大ショックだったに違いありません。ここで並大抵の人間ならそのまま喧嘩別れになりそうですが、ポールは対応に苦慮しながらもコステロとパートナーシップを保ち、いい刺激を得たそうです。さすが天性のオプティミスト。コステロについてポールは「ジョン・レノンと共作しているようだった」と語っています。
また、コステロがポールの「ビートルズ回帰」路線に弾みをつけたことも有名ですね。ポールがヘフナー・ベースを再び手にするようになったのも、コステロの助言あってのことでした。彼の影響あってか、自信をつけたポールは次なる新作となる「フラワーズ・イン・ザ・ダート」ではビートルズっぽいバンド・サウンドを重視した明朗な作風を取り戻すこととなりました。ちょうどコンサートの再開を目指していた時期あって、ライヴ感が漂う仕上がりとなりました。また、コステロから大きな刺激を受けたポールは創作意欲を爆発させ、多くの新曲を生み出すことになります。新たなミュージシャン仲間との出会いも果たし、曲に合わせてプロデューサーを変えてゆくというやり方も功を奏し、蓋を開ければ久々に活気にあふれたアルバムが出来上がりました。こうして世に出たのが「フラワーズ・イン・ザ・ダート」で、発売されるや世界中で久々のヒットとなりました。その後ウイングス以来のコンサート・ツアーに出たこともあり、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」はポールが'80年代の低迷から「復活」した作品としてファンの心に深く残る名盤となったのです。その原動力に、コステロとの共作活動があったのは誰も否定できないでしょう。
さて、コステロが「曲のたたき台」と形容した2人の共作活動では、10数曲の新曲・・・つまり「McCartney-Mac Manus」ナンバーが生まれました(注:コステロの本名はデクラン・パトリック・マクマナス)。それらのほとんどは、ポールとコステロそれぞれのアルバムに収録されることになります。そんな中で、ポールの「フラワーズ・イン・ザ・ダート」に収録されたのは4曲です。『My Brave Face』『You Want Her Too』『That Day Is Done』、そして今回紹介する『Don't Be Careless Love』です。共作にあたって、どの曲でポールとコステロそれぞれの貢献度がどのくらいあるか詳しくは明らかになっていませんが、最初のうちは片方が持ち寄った曲を2人でアイデアを出しながら手直しするといった方法が取られたそうです。そして、徐々に最初から2人で共作するという例も増えていったようです。最初に発表された2人の共作『Back On My Feet』はポールが書いた曲をコステロが手直しした程度ですし、一方で『The Lovers That Never Were』辺りになるとコステロの貢献度もかなり大きくなってきています。
そんな中、この曲はポールが書いた部分とコステロが書いた部分を組み合わせてできたと推測されます。つまり、ビートルズ時代のレノン=マッカートニーの共作活動でいえば『We Can Work It Out』や『A Day In The Life』と同じやり方というわけです。本人のコメントがないので実際そうだという確証はありませんが(汗)、この曲を聴くとそう思えて仕方なくなるでしょう。「あっ、ここがポールで、ここがコステロか・・・」と思うはずです。その根拠となるのはもちろん・・・、ポールとコステロの作風の違いです。
それでは、コステロの作風とは一体どんなものか・・・?ということになりますが、お恥ずかしいことに私自身コステロの作品を多く聴いてきたわけではないので偉そうに言える立場にありません(汗)。しかし、ポールとの共作曲を聴いている限りではポールにはないある味が効いていることが分かります。それは、コステロがポールに見せ付けた性格を形にしたような、辛らつで、ひねくれていて、重苦しくて、ほろ苦い・・・そんなビター系の味です。元々パンクやニューウェーブ出身のミュージシャンらしい、一筋縄では行かない屈折した作風。それがコステロの作風なのです。[コステロ・ファンの皆様、間違っていましたらぜひ異議を唱えてください(汗)。]こうした作風は、いずれもポールが普段行っている曲作りにはない味です。ポールと言えばポップでキャッチーでポジティブなのが持ち味。それを考えればコステロとは正反対の作風と言えるでしょう。ポールの明るいスイート風味と、コステロの重々しいビター風味。この2つが、一連の共作曲ではぶつかり合っているわけですが、一見して両極端にある2つの味が交じり合って、何とも不思議な、一ひねりも二ひねりもされた独特の作風が生み出されるのです。2人の掛け合いデュエットが印象的な『You Want Her Too』がその代表格と言えるでしょう。
そんなポールとコステロの作風の違いは、一部の曲ではすっかり融合してしまい見分けがつかないほどになっている例もありますが、この『Don't Be Careless Love』では、その温度差が明確に出た、面白い例です。それが、先述した「ポールとコステロ各自が持ち寄ったパートをドッキングさせてできた」という仮説につながるわけです。それでは具体的に、この曲について見てみましょう。
この曲は大きく分けてメロとサビに分解することができますが、そのメロとサビでは大きく作風が異なっています。曲を聴けば、その雰囲気は全く似通わないものであることはお分かりになるはずです。まずメロは、美しく繊細なメロディをしていて、少し寂しさをにじませた甘美なバラード作品といった印象です。これが誰が書きそうな作風か・・・と来れば、そうですね。ポールです。つまり、メロはポールが書いたものと想像できます。美しいバラードはまさにポールの得意分野ですね。一方、サビは一転して薄気味悪く不気味なメロディをしています。メロの美しさと対極的にダークな雰囲気が浮かび上がってきます。さらに、後半は早口気味の性急なメロディと化します。このような作風は誰によるものでしょうか?そう、コステロです。ひねったようなメロディは、コステロの性格そのものです。こうした点、サビはコステロが書いたものと推測できます。以上を整理すると、メロをポールが、サビをコステロが書いたと考えられるわけですが、メロからサビへ移動する際の不思議な感覚は2人の違いの象徴でしょう。鈍器で頭を殴られたかのように一気に暗く、重々しくなるのですから。そして、サビからメロに戻ってきた時の安心感。この曲では、ポールとコステロの作風が別々に介在しています。
ここまで雰囲気の違うメロディが並ぶと、普通なら極端すぎて大いなるミスマッチを引き起こし聴くたびに違和感を感じてしまうことでしょう。しかし、ポールとコステロはそうはなりませんでした。これが2人のマジックなのでしょうか。この対照的な違いを上手く活用して、曲を効果的に聴かせることに成功しているのです!2人ともさすが伊達に音楽活動をしているわけではありません。その鍵となったのが、アレンジ面・・・そして何と言っても詞作です。それでは早速、演奏面そして詞作面を見てみましょう。
曲はイントロなしで始まり、まずポールが作ったメロが登場します。美しいハーモニーによるアカペラに導かれるように入る演奏は、穏やか・・・というより控えめです。キーボード主体にギターやベース、ドラムスといったバンド・サウンドが支えるという格好ですが、派手なプレイもなく静けさを漂わせています。こうした薄味の音作りが、コステロの作ったサビに突入すると大きく変貌します。先ほどまでの美しいハーモニーが急に低音中心の暗いコーラスに変わり、さらには控えめだった演奏が力強くなってきます。ドラムスも本格的に入り、'80年代にありげな硬質なビートを刻みます。そして、一番耳に飛び込んでくるのが、シンセサイザーの様々なサウンド。これもメロで入っていたキーボードとは対照的に、不気味で幻想的な音色になります。よく聴くといろんな音を使っているのが分かります。サビのラストで少しだけ明るくなりますが、メロからは想像もつかないほどの陰鬱さを強調した仕上がりです。そして、サビが高揚感を持って終わると、再びメロの美しい静けさが帰ってきます。この曲は、こうしたイメージチェンジを1.5回繰り返す構成になっています(1.5回というのは、第3節のみサビがないため)。静かになったら暗くなって、また静かになってそれから暗くなって・・・といった風に。以上見てきたように、美しいメロでは静かな演奏、不気味なサビでは暗く力強い演奏という風に、アレンジ面でも2人の性格の違いが浮き彫りになっています。これがもし曲を通して一辺倒の同じアレンジのままだったら、きっとどちらかのパートで違和感を感じることになりますが、あえてはっきりカラーを分けることで、2つの個性をしっかり生かすことができ、ドラマチックな構成にしています。2パート間のつなぎ目の温度差が演奏でさらに際立っているので、その何とも言えないスリルがたまりませんね。それにしても蛇足ですが、この曲は最後は意表をついてあっけなく終わります。ポールらしいと言えばポールらしいですが・・・(汗)。
この曲のレコーディングに当たっては、少し紆余曲折がありました。当初、この曲をポールは共作者であるコステロと一緒にレコーディングしました。『You Want Her Too』などと同じセッションでのことです。コステロはコーラスとキーボードで参加。しかし、この時は上手い具合には完成せず、ポールは出来には満足しませんでした。そこで数ヶ月後、今度はコステロ抜きで再録音を行っています。この時のプロデューサーはミッチェル・フルーム。フルームはシンセのオーバーダブもしています。後にポールの「ゲット・バック・ツアー」でツアーバンドのメンバーとなるヘイミッシュ・スチュワート(ギター)とクリス・ウィットン(ドラムス)も参加してのこのセッションで、曲はようやく完成に至りました。しかし、コステロとセッションした時のテイクも捨てがたかったポール。結局は、所々でコステロが参加した元々のテイクも採用することになります。「ヴォーカルは気に入っていたから、ほんのちょっと整えればよかったんだ」とはポールの弁。その証拠に、冒頭のハーモニーはコステロが参加しています。こうした経緯から、2つの別々のセッションの録音が使用された、珍しい曲となりました。プロデュースも、ポールとコステロとフルームの共同名義となっています。コステロが参加していない『My Brave Face』とも違い、コステロとデュエットした『You Want Her Too』とも違う、その半ばを行く曲なのです。なお、ポールはベースとアコギの他に、メロ部分でタンバリンとフィンガー・スナップも披露していて、ちょっとしたアクセントとなっています。

ところで、アレンジ以上にメロとサビのギャップを効果的に聞かせているのが、ずばり歌詞です。この曲では、詞の世界が急変するアレンジに絶妙に絡み合っています。歌詞抜きに、この曲の魅力は語れません!逆説的に言ってしまえば、歌詞の内容を知らなければその妙が分かりづらくなってしまうのでもあるのですが・・・(汗)。続いては、そんな歌詞について見てみます。
面白いことに、ポールとコステロの共作曲によく見られる詞作が、個性的な登場人物の出てくる物語風の内容です。コステロは「我々が作業を共にした結果は一連の“キャラクターソング”に一番良く表れていると思う」と語っていますが、普通のラヴソングと並んで、2人の共作には「キャラクターソング」が結構あります。物語風の詞作と言えば、ポールお得意の分野であり、ポール1人でもいろんなお話を書けてしまいますが、そこに性格が全く異なるコステロがやって来ると一味も二味も変わります。コステロの手が加わることにより、ポールに典型的なポジティブ節全開の他愛ない詞作に、ピリッとスパイスが効いたひねくれたストーリーが生まれることとなったのです。『Back On My Feet』に登場する公園に住む孤独な男や、『Mistress And Maid』に登場する冷めた関係の夫婦・・・。これらはいつものポールの作詞活動ではなかなか出てこない類のものです。そして、この曲に登場するのは・・・、心配性の男です。
この曲の歌詞は、その心配性の主人公が自分の気持ちを語る形となっています。これが実に情けない男で、彼に黙って夜に1人で外出してしまう恋人のことが心配で心配で、「今どうしているのか?」「何かあったんじゃないか・・・?」と不安になって眠れない様子が描かれています(苦笑)。『My Brave Face』でも、失恋した惨めな男の生活が歌われていますが、それに輪をかけた情けなさですね。こうした姿をありのままに告白する主人公は、ポールの詞作ではあまり見られません。特に、細かい心理描写が克明に描かれている辺りは、エンターテインメント重視の(韻を踏んでいるだけと揶揄されるほどの)ポールとはちょっと違うタッチです。この辺がコステロのひねくれ具合の影響なのでしょう。結婚生活の崩壊を生々しく描いた『Mistress And Maid』も、そんな歌詞をしていました。さらに、コステロの屈折した詞作が色濃く表れたのがコステロが書いたサビでしょう。メロでは、主人公は不安な気持ちを打ち明けているだけなので、まだまだ普段ポールが書きそうなラヴソングと同類と見られますが、サビではさらに心配性に拍車がかかってあらぬ妄想が始まります(苦笑)。それも、「らせん階段に足が張り付いて動けなくなって、落ちてゆく君」を想像したり、ついには「暴漢の手によって君の体がじゅうたんに巻きつけられて2つに切断されている姿を朝刊で見た」なんて悲観的になったりするほどです(苦笑)。思わず「心配性も程ほどに」と言いたくなりそうですが、不気味でグロテスクな光景を織り交ぜてまで過度な心配性を表現しているというのもポール史上では大変珍しいです。ここまで壊れた主人公をポールの曲で他に見つけることはできないでしょう!やはり、この辺もコステロがパンチを効かせるために入れたアイデアなのか・・・?まぁ、結局この情けない男の不安は的中せず、朝起きてみると隣で恋人は寝ていた・・・というオチなので、ご安心ください(笑)。
で、話を戻せば、そんな情けない男の出てくる歌詞が、静けさと不気味さを行き来する曲調にぴったりはまっているのです。メロの部分は先述のように主人公の不安を歌っていますが、薄味で繊細で頼りないメロディと演奏が、主人公が夜1人部屋の中で悶々としている様子を再現しているかのようです。そして、一気にダークになるサビでは男の妄想が炸裂していますが、これはそのイメージ通り不気味な雰囲気の演奏ときれいに合致しています。そう、つまりメロディやアレンジだけでなく、歌詞もメロとサビでコントラストを成しているのです。そのため、まるでこの歌詞のためにメロディやアレンジができたかのように、歌詞で繰り広げられる不安と妄想を2パート間のギャップが見事演出してくれるのです。これが周到な計算の上でそうなったのか、それとも偶然だったのかは分かりませんが、ホントに効果的でニクいアレンジです。第3節で再度やって来る静けさは、朝になって恋人の姿を発見し一安心する主人公の気持ちがそのまま表現されていますし。
最後に、ヴォーカル面に触れてみれば、こちらもまたメロとサビではカラーが全く異なります。メロで印象的なのは美しいハーモニー。最初はアカペラで始まるほど、重要な要素です。ポールとコステロ、そしてヘイミッシュが歌いますが、ポールが当初の音源を捨て切れなかったのも分かる美しさです。この部分だけ取ると、ポールに典型的なバラードに近いものがあると思います。ポールのリード・ヴォーカルは、心配性の男の気持ちを表現するかのようにか細くハスキーな声で歌われます。寂しげで頼りない歌い方でポールも主人公になりきっているかのようです(苦笑)。一方のサビでは、ポールのヴォーカルは一気に張り詰めたようなシャウト混じりに変わります。先述のように早口気味のメロディも歌います。これは当然、歌詞の世界が妄想に切り替わるからというのは言うまでもありません(笑)。妄想に悲観して叫んでしまう主人公の情けなさが伝わってきますね。「何もそこまで不安にならなくても・・・」とつい思ってしまいそうです。サビでのコーラスは、これも先述のように低音重視の暗いトーンになります。さっきの美しいハーモニーは遠く彼方へ消えていったかのようです。タイトルコールを歌う箇所は、恋人が(主人公の妄想の中で)歩いてゆく暗闇の世界を表現しているかのよう。そしてもちろん、ヴォーカル面もこの変化を繰り返しながら進んでゆきます。サビからメロへ戻った時の安心感は・・・っていうのはさっきも話しましたね(汗)。
と、このように、メロディに演奏に歌詞にヴォーカルと、すべてにおいてポールとコステロの作風の対立が効果的なメリハリを生んでいるこの曲。2人の共作の中でも、この曲ほどその妙が楽しめる例はないと思います。2人のそれぞれの個性を堪能するにはまさにうってつけ!なわけなのです。しかし・・・、その作風のギャップがあまりファンの間で受け入れられていないのが悲しい事実であります(汗)。2人の温度差をスリルとして感じるより、違和感として感じる人の方が残念ながら多いのです・・・。そのため、一連の「McCartney-Mac Manus」ナンバーの中では無名に甘んじてしまっています。特にコステロが書いたサビの不気味な雰囲気に対する印象があまり芳しくないようです(汗)。確かにグロテスクな歌詞も出てきますしねぇ。さらに、収録されたのがポールが相当力を入れて制作した人気の名盤「フラワーズ・イン・ザ・ダート」というのも、この曲にとってはバツが悪い所かもしれません。周りが名曲揃いですから。恐らく、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」では最も人気のない曲の1つではないでしょうか。
しかし、そんなあなたの違和感や先入観を、さっと拭き取ってくれる恰好の音源があります。はい、例によってアウトテイクでございます(苦笑)。この曲のアウトテイクが発見されていて、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」セッションやコステロとのセッション関連のブート(「The McCartney/Mac Manus Collaboration」「Flowers In The Dirt Sessions」など)で聴くことができます。この音源は、ポールとコステロが2人きりでデモ・セッションを行った時のもので、2人が精力的に共作活動をしていた1987年夏〜秋に録音されたと言われています。このデモで聴かれるこの曲は、既にメロ・サビ共に完成しており、情けない男が主役の歌詞も完成していますが、アレンジが公式テイクと大幅に違います。それもそのはず、このヴァージョンはアコギ弾き語りなのです!まさに、2人が顔をつき合わせてアコギ片手に曲を作ってゆく、その過程のものです。そんなテイクがある自体も興味深いですが、この時点ではまだ2パート間の温度差が出来上がっていません。そのため衝撃度は減りますが、この曲独特の不気味さもなくなってかなり聴きやすくなっています。「なんかあの曲暗いから嫌いだ」と思っている方がいらしたら、ぜひ聴いて頂きたいですね。本当にアコギ2本(ポールとコステロ)だけで、ゆったりとしたテンポでポールとコステロが2人でハモるのですが、これが実に味わい深いです(どこか暖炉の前で演奏してくれているみたい)。と同時に、この曲でのコステロの存在感が増していて、ポールとの相性のよさを無性に感じることができます。公式テイクでは不気味なコーラスも、ここでは見事なデュエットになっています。公式テイクとは違う生の魅力が詰まっているのです。このヴァージョンを聴いてから公式テイクを聴くと、この曲のよさが分かりやすいと思いますよ。ちなみに、このデモ・セッションでは他に『My Brave Face』『The Lovers That Never Were』、コステロの『So Like Candy』『Playboy To A Man』なども取り上げられていて、ポールとコステロの絶妙なハーモニーが堪能できます。
と、何かと評判がよくないこの曲をここまで必死に力説してきましたが(笑)、実はそういう私にとってはかなり好きな曲です。同じアルバムでは『This One』や『Put It There』よりも好きだったりします(マニアックですみません・・・)。私がこの曲をお気に入りな理由は、実は歌詞です。「えぇっ!?」って思われる方が多いかもしれませんが。いや、インパクトありすぎじゃないですか、あの内容は!最初に歌詞カード読んでどんな内容か知った時から何か惹かれるものがありました(その前に邦題で面白そうと思っていたのはここだけの話)。心配性の主人公の気持ちも、何となーく分かる気もします。別に私が同じ境遇にあるとか、そういうことでは全然ないんですけどね(苦笑)。ただ、大切な人を愛するゆえに生じる様々な不安(一緒にいない間何か起きているかもしれない・・・という気持ちとか)や、それに伴う妄想は誰にでも起こりうることではないかと思うんですよ。そういう点で共感ができるんです。まぁあそこまで妄想が激しいのも問題ではありますが・・・(汗)。そんなわけで、この曲は私にしては珍しく歌詞の方が曲自体より評価が高いです。他にそんな人はいなそうですが。マニアックなのは仕方ないとして、不評気味なのがちょっと意外ですね・・・。もうちょっと評価されていいと思うんですけど・・・。
今までこの曲を飛ばし聴きしていた皆さん、ぜひこの機会に新たな視線からこの曲を聴き直してみてはいかがでしょうか?ポールとコステロの2人の個性が炸裂して、不思議な快感を生み出していますから。違った角度で見れば、気づかなかった魅力に出会えるかもしれません。
さて、次回紹介する曲のヒントは・・・「プレスリーもどき」。こちらもかなりマニアックですので、お楽しみに!!
(2009.11.21 加筆修正)
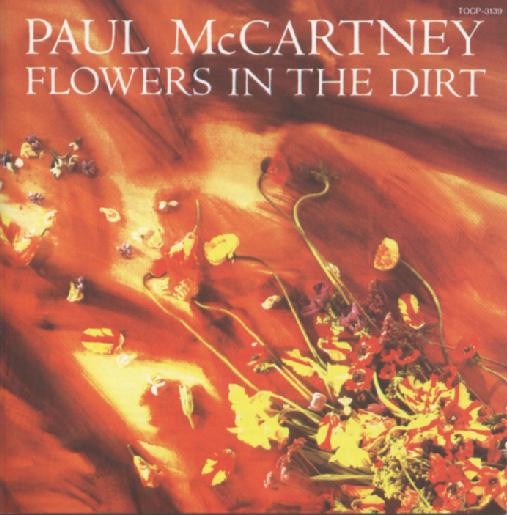
アルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」。ポールが'80年代の低迷期から復活した名盤!エルビス・コステロとの共作を4曲収録。