
Jooju Boobu 第69回
(2005.11.03更新)
Arrow Through Me(1979年)

今日(注:初回執筆日。2005.11.03)は文化の日です。このコラムとは関係ないことですが。それから韓国産キムチから寄生虫が見つかりました(注:これも初回執筆時の出来事)。危ないですねぇ・・・。おっと、話がポールではなく別方向に向かってしまいました(汗)。というわけで、気を取り直して「Jooju Boobu」を始めたいと思います。今回は、前回ご紹介した『Baby's Request』と同じく、ウイングスのラスト・アルバム「バック・トゥ・ジ・エッグ」(1979年)収録曲を語りたいと思います。それは、『Arrow Through Me』です。この曲は、ポールらしさが直球で伝わってくるポップ・ナンバーなわけなのですが、アレンジにおいてはいつものポールとは一線を画しているのが特徴です。それは「バック・トゥ・ジ・エッグ」の時期特有のアレンジが施されているからなのですが、今回は、その特異なアレンジとはいかなるものか?ということを中心に、ポールのポップ節を堪能できるこの曲の魅力を書いてゆきます。念のために言っておきますが、キムチの話はしませんので(笑)。
まず、例によって収録アルバム紹介から始めたいと思います。って、『Baby's Request』と2回連続になってしまうんですが・・・。くどいのが嫌いな方は読み飛ばしてください(苦笑)。『Arrow Through Me』が発表されたアルバム「バック・トゥ・ジ・エッグ」は、オリジナル・メンバー3人に新たなメンバー(ローレンス・ジュバー、スティーブ・ホリー)を加えたウイングスが心機一転制作した作品で、バンドにとって大きな再出発になる予定だった1枚です。結果的には、いろいろあってこれがウイングスのラスト・アルバムになってしまったのですが・・・(本当はそのつもりは毛頭なかったことでしょう)。メンバーチェンジを再び繰り返して生まれ変わったウイングスに対するポールの自信はとても強いもので、何とかして新ラインアップの結束を高めようと躍起になり、この時期には多くの新曲を書き下ろしました。それを携えてのレコーディング・セッションは、共同プロデューサーに当時売れっ子のクリス・トーマスを迎え久々に本腰を入れて取り組んだものとなりました。その中では一流ロックミュージシャンが集結した「ロケストラ」というユニットでのセッションも実現し、これもアルバムに収録されることとなります。ポールの創作意欲も非常に高かった時期で、ポールにとってはタイトル通り「卵に戻る」原点回帰の自信作でした。しかし、ポールもまさかそんな新生ウイングスの第1弾が予想外の低迷に終わるとは思っていなかったでしょう・・・。なぜか当時のチャートを賑わせることはなく、ポールは失意のうちにウイングスの活動を停滞させます。とはいえ、中身を見てみれば紛れもなく自信に満ち溢れた元気いっぱいの名曲揃い。ポールの作品で最も過小評価されているとも言える、隠れた名盤です。
「ロケストラ」という一大ロック・プロジェクトによる2曲があるように、「バック・トゥ・ジ・エッグ」の時期の曲はやたらとロック色が強いです。アルバムも、一部のバラードを除いてはほぼアップテンポで貫く、ウイングス作品でも極めてハードエッジな作風です。これは、前作「ロンドン・タウン」が大人しめに仕上がった反動もあるでしょうし、新メンバーのローレンスとスティーブの絶頂期に負けないパワフルなプレイも影響しているでしょう。さらには、ポールが「卵に戻れ」を標語にしたようにウイングスを活動の原点であるライヴ感あふれる荒々しいバンド・サウンドに回帰させようとしたことも挙げられますね。しかし、「バック・トゥ・ジ・エッグ」の魅力は、単なるロックへの回顧を図ったのではなく、そこから一歩先に足を踏み入れたアレンジになっている点が大きいです。そう、それが、当時世界を席巻しつつあった新たな流行音楽への意識です。「ロンドン・タウン」ではあえて風潮に反してトラッド風味を中心に据えていましたが、「エッグ」ではその揺り戻しか最新のミュージック・シーンを強く意識した作風を大々的に取り入れています。例えば先行シングルだった『Goodnight Tonight』はディスコのリズムを採用していますし、『To You』『Spin It On』からはパンクの影響を、『Old Siam,Sir』からはニューウェーブの影響を感じられ、実験的かつ冒険的な試みが随所で施されています。ロック路線の多いウイングスでもことさら斬新な印象を与え、今聴いても何ら遜色のない、いつでも新鮮味を覚えるロックに仕上がっているゆえんです。このように最新のスタイルを大量に取り入れていることがアルバムを聴けばよく分かりますが、その源泉となっているのはポールの新し物好きな性格でしょう。ポールは、昔から今までその時々の先端を行く音楽を実に敏感に察知して、自身の音楽に取り込んでゆく嗜好性を持った人なのですが(「マッカートニーII」「プレス・トゥ・プレイ」がよい例)、この時期も'80年代に向けてミュージック・シーンががらりとその容貌を変える中で時代に追いつかんと果敢にパンクやニュー・ウェーブに挑戦していった・・・というわけです。ピンク・フロイドやロキシー・ミュージック、日本のサディスティック・ミカ・バンドまで手がけていたクリス・トーマスと一緒に制作した所にも、ポールの気概を感じさせます。時代の先を見据えた点においても、ポールにとっては「バック・トゥ・ジ・エッグ」は自信作でした。
さて、そんな中にあってこの『Arrow Through Me』はどうだったのでしょうか。この曲は、ざっと言ってしまえばポップ・ナンバーです。アルバムに収録された『Getting Closer』『Old Siam,Sir』など一連のロック・ナンバーに比べると圧倒的にハードエッジさはありません。テンポもゆったりしています。そして、メロディを切り取ってみると、実にポールらしさたっぷりのメロディアスなものです。覚えやすく親しみやすいポップなメロディは言わずもがポールの基本となる得意分野であり、ウイングス時代はもちろん昔から今まで様々な曲を披露しています。しかし、この曲は他の時期のポールのポップ・ナンバーとは明らかに異にしているものがあります。それがアレンジです。この曲は、普段のポールではあまり耳にすることのできない異色のアレンジが施されているのです。そしてその源泉は言うまでもないでしょう!そう、この曲でも、「バック・トゥ・ジ・エッグ」で炸裂したポールの新し物好きの影響をもろに受けてしまったのです。


非常に特異なのが楽器面でしょう。ロック・バンドであるウイングスの主要たる楽器はギターですが、この曲では本来主役であるギターが脇に引っ込んで目立っていません。それどころか、ほとんど聴こえないに等しいレベルまで下がってしまっています。全く使用されていないとまでは断言はちょっとできませんが(汗)。デニー・レインとローレンス、2人のギタリストを抱えたウイングスにとってはこの時点で珍しい編成です。斬新な作風の「エッグ」内でもギターレス状態であることはとても目立ちます。他の曲ではちゃんとギターが主役ですから・・・。逆に、この曲で見事メインを張って目立っているのが、ムーグ・シンセサイザーです。実はこの曲、ほとんどムーグで出来上がっているのです!ウイングスにキーボードが曲を引っ張る例はいろいろありますが、ここまでキーボードが主役、しかも生ピアノでない音が主役なのは珍しいです。ムーグといえば「レッド・ローズ・スピードウェイ」の頃からウイングス・サウンドに登場し、ポールの奥さん・リンダの指一本弾きの名演が効果的に使用されるようになっていましたが、ここではさらに前進してムーグをフル活用しています。ウイングスも末期になって、いよいよムーグがギターを追い出すまでに至ったのですから、すごいものです。
ウイングスのムーグといえば、『Jet』や『Venus And Mars』のソロのようにいかにも人工的な、金属質な高音という印象が強いですが、ここでは低音〜中音域を多用していて耳障りよい音色になっています。よく聴くと複数の音色が使用されているのが分かりますが、いずれも落ち着いた感じです。ウイングスもようやくムーグの演奏にこなれてきたのか、それともムーグの技術が進歩してナチュラルな音色も出せるようになったからか・・・詳細を知らないので何とも言えないですが。クラビネットのような音が耳に残ります。全体的に少しもやっとしているのも特徴で、それがこの曲にゆったりした不思議なムードを作り出すのに大きく貢献しています。また、大々的なソロ回しも登場せず、あくまでバッキングといった印象です。ムーグが主役とはいえ、バリバリに目立っているわけでないのが、この曲の穏やかな雰囲気を壊さないコツとなっていますね。ミドル・テンポにもぴったりです。ギターを排しムーグを多用するという編成だけでも「おっ?」となりますが、これまでとは違うアプローチで上手くムーグ・パートをアレンジできたことも、それまでのウイングス・サウンドにない「おっ?」と思わせる要因です。それにしても、明確なクレジットはないので断言はできませんが、後述するプロモ・ヴィデオを見る限りは、ドラマーのスティーブを除いた全メンバーがムーグを演奏していると思われ、これまた衝撃的です。リンダやポールは想像できますが、普段はギタリストのデニーとローレンスがキーボーディストに・・・と思うとちょっと違和感がありますね。いっぱいムーグを並べて4人同時に演奏するという、この曲のレコーディング風景が見たかったものです。
主役級のムーグ・シンセに並んで目立つもう1つの楽器が、間奏とアウトロに入るブラス・セクションです。先述のようにムーグ自体はソロ・フレーズは登場せずただただバッキングという印象なのですが、そんな中で唯一ソロ・フレーズを聞かせるのがブラスです。これが、もやっとした感じのムーグとは対照的にかなりシャープな音色ではっきりしたメロディを奏でます。同じフレーズの繰り返しですが(どこか『Let 'Em In』の間奏を思い浮かべる)、メロディにはなっているものの斬新に感じられるのが実験的です。普通のブラス・セクションにはないような耳障りだからでしょうか。ウイングスでブラス・セクションを起用した他の曲とは違った毛色を持っています(まるでシンセ・ブラスのようでもある)。登場するのは間奏とアウトロだけなのですが、それゆえにこの部分はぱっと浮き上がる仕掛けになっていて、この辺のアレンジの妙はさすがです。ブラスがないと、もやっとしたままで終わってしまいますが、そこに1つスパイスが加えられることにより効果的な曲構成が出来上がっています。しかし、ムーグ・パートの不思議ムードを壊しそうでかえって不思議ムードを増幅させているのが面白い所です。この辺も計算されているのか否や・・・。ウイングスとしては異質なムーグとブラスの2つのサウンドが、程よく融合して、異色のサウンドを聞かせてくれます。エンディングは、そんなブラス・セクションでスパッと終わり、アナログ盤A面の終了にはもってこいのアレンジでした。
この他の楽器も実はかなり実験的です。ポールの本業であるベースは、ここではシンセベースを使っているようです(生ベースかもしれませんが・・・)。この頃からシンセの波もポールに押し寄せてきていました。ベースも例に漏れず・・・といった所でしょうか。スティーブが演奏するドラムスは、ほぼ一定のリズムを刻むのみで目立った変化がないのが特徴。これは後の打ち込みドラムスを思い起こさせるようなパターンです。その生ドラムスのバックには、ひそかにリズムマシーンが鳴り続いています(パーカッションの音で分かる)。ベーシック・トラックはこのリズムマシーンにのせて録音したのでしょう。また、要所要所で「ちゅいーん」という奇妙な音が響くのがまた異様なのですが、これはフレクサトーンというパーカッションだそうです。程よいアクセントとなっていて、気の利いたアレンジですね。いろいろ新しい楽器を取り入れて、それが見事はまっているのだからポールってすごいですね。あと音楽的に聴いていて面白いのが、間奏で2度拍子が変わっていることです。よーく聴くと分かりますが、試しに曲に合わせてドラムスをたたく真似をしてリズムを取ってみてください。途中で「あれ?」となりませんか?さらに、合わせ直したらまたずれている・・・。実は4拍子と3拍子とがめまぐるしく入り乱れているのです。リズムチェンジはむやみにやると不自然に聴こえかねませんが、ここでは2度も、しかも短時間にリズムチェンジしているというのに、普通に流し聴きしていたらほとんど気づかない程にごく自然に行われているのです。ポールのアレンジャーとしての技量を感じますね。


こう見ていると、割と分厚い音作りとなっているこの曲のサウンドのうち、生楽器が圧倒的に少ないですね。もしかしたらドラムスだけかもしれません。これは、本来ライヴを目的として結成されたロック・バンド、ウイングスにしては極めて異例です。恐らく、ちゃんとバンドで演奏したウイングス・ナンバーでは一番生楽器の比率の少ない曲でしょう(『Cuff Link』は・・・、あれはポール単独録音ですので)。このように、ムーグを前面に出したアレンジ、奇抜なブラス・セクションの挿入、シンセ寄りの演奏など、この曲では実験的なアプローチが十二分に楽しめます。・・・で、これがどうポールの新し物好きにかかわってくるか・・・?という話ですが、パンクやニューウェーブと並んで1978〜1979年当時流行の最先端を走っていた音楽がもう1つあります。そうです。日本ではYMOであまりにも有名なテクノ・ポップです。
1978年にデビューしたYMOを中心に一世を風靡したテクノ・サウンドは、英国でもブームを巻き起こしていました。そんなテクノ・ブームを何でも新しいスタイルは取り入れたいポールが無視したわけがありません。早速自分でもテクノの手法を採用した曲を作るのですが・・・、実はそれが『Arrow Through Me』と言えそうなのです。シンセを中心に据えたアレンジ、一辺倒なドラムパターン、斬新なブラスの導入。これらはYMOなどのテクノ・サウンドに通じるものがあります。ポールとテクノと言えば、「バック・トゥ・ジ・エッグ」の不振後にポールが自宅にこもってデモ録音した音源が元になったソロ・アルバム「マッカートニーII」がもろにテクノの影響を受けたのを思い起こさせますが、その序章がこの曲だったのかもしれません。しかし、結果として出来上がった曲を聴いてみると、本場テクノ・サウンドにはなっていないのが面白いです。これは、以前のコラムでも触れたように、ポールがテクノをよく知らないことも理由ですが(苦笑)、いかに流行のスタイルを採用してもそれを鵜呑みにすることなく、自分なりに噛み砕いた上でオリジナリティあふれる「マッカートニー・ミュージック」に消化してしまう・・・というポールの癖が発動したことが大きいです。この曲も、テクノ・ポップそのものではなく、ポールのポップ・センスにシンセをまぶしたくらいの「もどき」作品ですし(笑)。テクノ・ポップに本格的にのめり込むより、程よく自分の持ち味を生かした方がポールらしくて聴きやすいので、この結果でOKですし、この消化プロセスは毎度ながら絶妙です。それにしても、この曲を踏まえてポールがさらにテクノを追求した(?)「マッカートニーII」が自宅での一人多重録音が要因でチープな出来に終わってしまっているのに比べ、その序章であるこの曲の方がしっかりとしたスタジオでのバンド・サウンドだけあってよりテクノっぽくなっているのは皮肉的です(苦笑)。「マッカートニーII」の曲も、スタジオでバンドと共に録音していたらこの曲みたいな仕上がりを見たかもしれませんね。まぁ、あれはあれでチープなのが魅力でいいんですけど(笑)。
ギターを徹底的に排し、代わりにムーグ・シンセを大々的に使ったこの曲は、ポールのテクノ・ポップ(つまり最先端の流行音楽)への尽きせぬ関心と、実験的アレンジ好きの賜物でしょう。この曲のちょっと前には、『With A Little Luck』という曲でシンセをメインにした音作りを披露していたポールですが、さらにテクノの洗礼を受けてこの曲ではより実験的な試行錯誤を取り入れた感があります。そういう意味で『With A Little Luck』の進化版と言えそうです。冒険とも言える試みというのに、両曲ともポールらしさが炸裂しているのには才能を感じさせますね(ちなみに私は両曲ともかなりお気に入りなんですよ、はい)。
ポールのヴォーカルは、シャウト系が多い「バック・トゥ・ジ・エッグ」の中では落ち着いた感じであり、シャウト交じり気味になる部分もあるものの、基本的には穏やかな歌い方です。だから『Old Siam,Sir』から続けて聴くと「これホントに同じ人?」状態なのですが(苦笑)。ゆったりした曲調にぴったりですが、この曲ではそれどころか、細い声で、どこか枯れた感じに歌われています。まるでデニーのような歌い方です。面白いことに、「エッグ」の時期の曲にはなぜかこうした歌い方の曲が多く見られます。『After The Ball』『Winter Rose』『We're Open Tonight』などのバラードに顕著で、ロック系でも『To You』にも似た所があります。これは故意なのか、それともポールの声が出にくくなっていた時期だからか・・・?一説によるとドラッグの影響らしいですが(汗)。逮捕事件の前ですし、ね。しかし、枯れた味わいのヴォーカルは曲の雰囲気にぴったりはまっています。ムーグの落ち着いた音色と合わせて、どこかお上品な印象をも与えてくれます。高音が続き、起伏も激しいメロディなので、歌いにくそうですが難なくこなすポールでした。深めのエコーがかかっているのが、また何ともいい味です。これはテクノを意識したのか否や・・・(違いますか)。そんなヴォーカルも、曲全体を見渡せば比較的少なく、それよりは間奏やアウトロの方が長いです。インスト的ムードを出すことで、実験的な感じを出そうとしたのでしょうか?アウトロにかぶさるかすれ気味のアドリブが、これまたいい味です。一方、今回はウイングス王道のリンダ&デニーのコーラスは間奏の一部に登場するのみですが、これが美しいコーラスで聴き逃せません。
歌詞は、ちょっとバッドなラヴ・ソングです。同じアルバムで言えば『To You』と同じ系統でしょうか。ポールの歌い方にあいまってちょっとせつなげです。まぁ、そんなに深い思い入れを込めて書いたものでもないんでしょうけど・・・。構文がかなり難しいので、英語の勉強にはなります(苦笑)。
さて、この曲にはアウトテイクがあり、「バック・トゥ・ジ・エッグ」セッションもののブートで聴くことができます。2テイク出回っているのですが、私は最近発売されたブート「Back To The Egg Alternate Mix」で入手しました(「エッグ」ものは垂涎のアイテムだったのでうれしかった!)。まず、アルバムの曲順を暫定的に決めた際のラフ・ミックスがあります。これは基本的には公式テイクと同じアレンジ・構成・歌詞なのですが、ミックスが異なります。ムーグが大きめに入っていて、細部まで楽しめます。また、一部楽器が異なっており、ブラス・セクションは別テイクだと思われます(なんとなく聞こえが違う)。ポールのヴォーカルはガイド・ヴォーカルで、微妙に歌い回しが違います(間奏後は顕著)。エコーもかかっていなく、生々しく響きます。それでも公式テイクと同じ雰囲気が出せていて、曲想は練られていたのではないか・・・と思わせます。間奏のリンダ&デニーのコーラスはなし。エンディングは、曲が終わった後もリズムボックスが鳴り続けます。そしてもう1つ、初期テイクというものもありまして、こちらは先のラフ・ミックスのさらに原型と言えるものです。ヴォーカルはガイド・ヴォーカルのままで、ラフ・ミックスとは変わりないものですが、一番大きな違いはあの印象的なブラス・セクションが全く入っていない点でしょう!唯一のスパイスが抜けたため、かなーり地味なテイクとなっています(汗)。その分裏方のムーグの演奏が聴きやすくなっているのですが・・・。ブラスが入る箇所では、代わりにポールがスキャットでブラスのメロディを歌っている・・・という何とも珍しいテイクです。この曲の制作過程が垣間見れます。ポールも、ちゃんと間奏のイメージは初期段階からつかめていたんだなぁと思わせます。こちらのエンディングは、スパッと終わる直前でフェードアウトしていますが、ブラスがないだけでイメージががらりと変わることをよく示しています。
さて、発表後のこの曲についていくつか触れてゆきます。アルバム「バック・トゥ・ジ・エッグ」が、ポールの強い自信とは裏腹にチャート上でコケてしまったことは有名ですが、先行シングルの「Goodnight Tonight」を除いてはシングルも同様に売れませんでした。そんな中、この曲も日米で「Getting Closer」に続く第2弾シングル(1979年8月、B面は『Old Siam,Sir』)としてシングルカットされたのですが・・・芳しい結果は得られませんでした。米国では最高29位止まり。ポールにとってはどの曲も一押しだっただけに、ショックは大きかったことでしょう。ちなみに、英国では第1弾シングルが「Old Siam,Sir」で、第2弾が「Getting Closer」でした。そして面白いエピソードがあるのが日本盤です。日本では年が明けて1980年1月20日にシングル発売されたのですが、ちょうどウイングス初の日本公演が翌21日に始まるということで、シングルジャケットには「来日記念盤」と記されていました。しかし、その4日前の16日に予想外の出来事が起きます。言わずもが、日本の地を踏んだポールが成田空港で大麻不法所持の疑いで逮捕されてしまったのです・・・!当然のことながらウイングスの日本公演は中止(17日発表)。ポールも10日後に英国に強制送還されてしまうため、このシングルが祝っていた「来日記念」はなかったものとなってしまいました(刷った後だったため、結局「来日記念盤」の表記は残されている)。さらに、逮捕事件を受けてポールの曲は日本で放送自粛されたため、この曲は日本でオンエアされることすらありませんでした。来日公演を大々的に宣伝しようとジャケットを手がけた東芝EMIの担当者の方は、さぞかし驚きと落胆に包まれたことでしょう。そして、くしくもこのシングルが、日米でのウイングス最後のシングルとなってしまったのでした・・・。英国では「Getting Closer」が最後ですけれど。


シングル発売に合わせて、この曲はプロモ・ヴィデオも制作されました。『Baby's Request』の項でも触れましたが、この時期のポールは映像作品にも大変力を入れていて、同時期の8曲分のプロモ・ヴィデオを集中的に撮影しています。元々はヴィデオ・アルバム化の予定もあったほどで、アルバムと共にこちらもポールの自信作だったのです。この曲のプロモの監督は、キース・マクミラン。ポールのプロモではたびたび采配を振るっている人で、この時撮影されたプロモすべての監督を担当しています。プロモの内容は、シンプルなスタジオ・ライヴで構成されています。しかし面白いことに、先に見てきた楽器編成の影響で、ギターを弾いている人が誰もいないのです!その反対に多いのがキーボード担当。なんと、ここではリンダのみならずポール、さらにはデニーとローレンスまでキーボードを演奏しています!ドラマーのスティーブ以外がキーボードという、ウイングスにしては異様な演奏体制を見ることができます。かつて『With A Little Luck』のプロモでもデニーがキーボードを弾いていましたが、それ以上です。ムーグがこの曲でどれほど重要な位置を占めた楽器なのかがよく分かります。普段はギタリストとして演奏する姿を見るデニーとローレンスですが、意外と器用に鍵盤を操っていて、もしかしたらスタジオ・ヴァージョンも・・・?と思わせるのでした(デニーがノリノリで体動かしまくりなのが笑える)。でも一番きまっているのはポールですね、やっぱり。リズムチェンジも振り付けで難なくこなします。部分部分ではキーボードを弾く手つきがクローズアップされていて興味深いです(ブラス・セクションのメロディもここではキーボードで弾いている)。また、このプロモで面白いのは、合成技術を駆使して一画面に複数の演奏風景を同時に収めている点です。なので、例えばポールが演奏しているシーンでは別のアングルから撮ったポールが映ります。翌年の『Coming Up』のプロモのさきがけといえるのでしょうか。さらに、各映像にはわざとぶらしたかのような処理がされていて、そこにカラフルな光のエフェクトが加わって幻想的な雰囲気をかもし出しています。まるでこの曲の雰囲気を映像に表現したかのような、不思議モードが拡幅される、視覚に訴える内容です。スタジオ・ライヴ一本ながらも、映像的なクオリティが高いこのプロモですが、残念ながら公式プロモ・ヴィデオ集「The McCartney Years」には未収録です・・・。ポールが力を入れた同時期のプロモがほとんど未収録になっているのが惜しいですね。
さて、ウイングスは新譜の発売不振へのポールのショックによりしばらく活動を停止していましたが、デニーの「ライヴがやりたい!むずむずする!」というわがまま(苦笑)に動かされて、1979年秋になって久々にコンサート・ツアーに出向くことになります。それが一連の英国ツアーでした。日本公演中止もあり、結局これがウイングス最後のコンサート・ツアーになってしまったのですが・・・。ツアーでは、自信作「バック・トゥ・ジ・エッグ」の宣伝も兼ねて実に5曲(+シングルの『Goodnight Tonight』)の新曲を引っさげてのセットリストが話題となりましたが、この曲もそんな中で演奏されました。スタジオ・ヴァージョンではギターレスのムーグ中心の実験的なサウンドのため、ライヴでの再現が難しそうですが、それをちゃんとステージで再現してしまうんだからポールは、ウイングスはすごいです。スタジオ・テイクとほぼ同じアレンジで披露しています。残念なことに映像が残っていないためステージでの演奏体制は不明ですが(ポールがキーボードを弾いている映像は残っているらしい)、音源を聴く限りここでもスティーブ以外のメンバーはキーボードに専念しているようです。ヴォコーダーやリズムマシーンの導入もそうですが、当時のウイングスはステージでも実験的なことを繰り返していたわけですね。複数のシンセ音が聴こえるため、ポールとリンダ、それから多分デニーもキーボードで確定でしょう。ここでのムーグも大人しめな低音〜中音域で、ゆったりした不思議モードを携えています。さらにフレクサトーンまで再現されています。そして、ブラス・セクションは当然!当時ウイングスのツアーに同行していた本物のブラス・セクションによる本物の演奏です(間奏のコーラス・パートもブラスによる演奏)。やはり、その方がライヴ映えしますね。これは絶頂期ウイングスもそうですが、ブラス・セクションの知人を持っていたポールの人脈の賜物ですね。ポールのヴォーカルはといえば、ここではすっかり喉の調子もよくなってオリジナルよりしっかりした声で歌われています。シャウト気味の部分もあって、図らずも「ロックの回顧」を意識した当時のライヴの趣旨にぴったりはまっています。そして何より、あの変拍子含めた難しい演奏をこなしているウイングスの演奏能力には脱帽致します。演奏前後の観客の受けも意外とよさそうですね。公式発表はされていないライヴ・テイクですが、ブートでは、最終日グラスゴー公演の模様を収録した名盤「LAST FLIGHT」で聴くことができます。
この曲は、「バック・トゥ・ジ・エッグ」内ではロック色の強い名曲たちに負けてしまうものの(汗)結構私のお気に入りの曲です。この時期独特の斬新な作風に加え、そこはかとなく匂う独特の「おしゃれ感」がたまらないんですよ。前作「ロンドン・タウン」の時にその予兆は見せていましたが(例:『Cafe On The Left Bank』)、なんか「エッグ」の時期の曲って全体的におしゃれなんですよね(ワイルドな曲もありますが)。なんと説明したらいいのか・・・上品で優雅です。『After The Ball/Million Miles』『Winter Rose/Love Awake』のメドレーとか、『Baby's Request』とか・・・。特にポップ&バラード系で感じることが多いですね。これは絶頂期ウイングスにはあまりない魅力ですね。漠然としていてうまく言い表せませんけど・・・。その中の代表格がこの曲かと思います。ムーグの音とか、ポールの繊細なヴォーカルとか、フレクサトーンの「ちゅいーん」とか、音選びが上手なんですよね。私が一番好きなポール・ナンバー『With A Little Luck』の姉妹作品にも取れる点も好感度上げています。あとは、もちろん私が最終ラインアップのウイングスがお気に入りというのもあります。「来日記念」できずついぞ日本で演奏されたことのないこの曲ですが、望みが薄そうですがいつかまた、今度は日本でやってほしいなぁと思います。今のツアーバンドがキーボード弾けないから無理かな(苦笑)。
この曲は、「バック・トゥ・ジ・エッグ」からのシングル曲と同様に過小評価されがちでベスト盤に収録されていないなど不遇ですが、ポールらしいゆったりとしたポップ・ナンバーで「エッグ」の中でも聴きやすいと思います。ポールらしさと程よい斬新さがいつ聴いても新鮮ですよ。「エッグ」自体、非常に力作ぞろいなのでぜひ聴いてみてください。
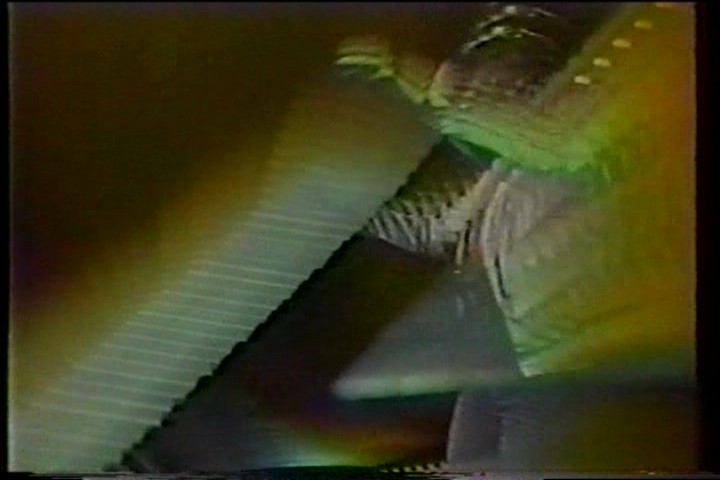
さて、次回紹介する曲のヒントは・・・「ポールの恨み?」。次回はマニアックな曲です!お楽しみに!
結局キムチの話はしませんでしたね、はい(笑)。
(2009.10.02 加筆修正)


(左)当時のシングル盤(日本)。来日記念盤だったのに・・・。ジャケットはアルバムと同じものを使用。安直ですか?
(右)アルバム「バック・トゥ・ジ・エッグ」。ロック色の強い、積極的に新しいスタイルを取り入れたウイングス会心の一作。結果的にラスト・アルバムに。