
Jooju Boobu 第67回
(2005.10.27更新)
Pretty Little Head(1986年)

前回の「Jooju Boobu」は一大名曲の『Jet』を紹介しましたが、今回からまたマニアックな選曲に戻ります(笑)。しかも今回は、かなりかなりマニアックです!でも、一応シングルにはなっている曲です。それでもマニアックですが(苦笑)。さて、その曲が何かといえば・・・、1986年発売の問題作「プレス・トゥ・プレイ」に収録された『Pretty Little Head』です。はい、マニアックですね。ポール・ファンならご承知の通り、「プレス・トゥ・プレイ」はポールの創作意欲が空回りしてしまった「駄作」と称されるアルバムですが(汗)、その中でもとりわけ問題視されたのがこの曲でしょう。その理由は簡単、まさにどこを切っても「これがポール!?」という内容だからです。ポールを聴き始めの初心者の方は特に、この曲を聴いて大きな驚きに遭遇することでしょう。ステレオタイプのポール像とは180°真っ逆さまだからです。しかし、そんな「駄作」の中の「問題作」と言われるこの曲も捨てたものじゃない、と力説するのが「プレス・トゥ・プレイ」のディープなマニアである私です(笑)。さぁ、今回はそんな私が必死にこの曲の魅力を語りつつ、この曲を擁護してゆきます(笑)。
このコラムを毎度ごらん頂いている皆さんには、アルバム「プレス・トゥ・プレイ」の説明はもういらないでしょう!それだけこのアルバムの曲を既に紹介しているので(苦笑)。半数以上紹介したのではないでしょうか?でも一応このページからごらんになった方のために改めてざっと説明しますと、「プレス・トゥ・プレイ」は、'80年代に入り売上不振に陥っていたポールがこれまでのソフトなポップやバラードの路線を切り替え、心機一転、当時の最先端を行く音楽だったコンピュータ・プログラミング主体のエレクトリック・ポップに挑戦した意欲作で、デヴィッド・ボウイやジェネシスを手がけた売れっ子プロデューサー、ヒュー・パジャムを迎えたのは有名な話です。創作意欲満開な中新たな切り口で起死回生を図ったアルバムですが、その斬新さがあだとなり、期待を裏切られた(汗)ファンの購買意欲をそぎ、新たなファン層も獲得できずチャート上で大失敗を喫した上に(全英8位、全米30位・・・)、今となってはファンの間でさえ「全然聴くことのない“駄作”」「人には勧められない“らしくない”アルバム」と酷評され、果てには当のポール本人さえも最近「このアルバムの曲目を見ると、『なんでこうなるんだ・・・』と思うよ」なんて発言をしている(個人的には絶対納得のいかないコメントです!)、悲しい運命をたどることになったアルバムです。それでも、私は大好きで大好きで仕方ないアルバムなんですけどね(笑)。
しかし、「プレス・トゥ・プレイ」はサウンドこそ革新的で機械的なものが多いものの、メロディ面を取ればポールらしさを十二分に感じられる隠れた名曲が多いことは毎度触れている通り。いちいち挙げていたらキリがない程です。また、いつも時代の流行を敏感に察知し、それを吸収してゆくポールの音楽に対する積極的な姿勢を最も感じることのできる一枚として重要です。ここではポールの創作意欲が輝かしく炸裂しています。ポールが時代の先を行き過ぎていたのは否めなく、それがチャート・アクションにつながらなかったとは言え、今聴いてもそのアイデアあふれるアレンジから新鮮なものを感じることが多いです(よく指摘されるように、ポールらしさは隠れがちですけど・・・)。ヒュー・パジャムの手がける斬新なプロデュースが先行しがちなのが欠点ですが(汗)、ポールが当時どんな方向を目指していたかはよく分かります。そう、そんなに悪いアルバムではないのです。
そして最も注目すべきなのが、元10ccのエリック・スチュワートとの共作活動。'60年代はジョン・レノンと、'70年代はデニー・レインと、それぞれ共作活動をしてきたポールですが、'80年代はアルバム「タッグ・オブ・ウォー」をきっかけにエリックをコーラスなどでフィーチャーしていました。以降'80年代ポールのアルバムでは欠かせない存在になったエリックを、「プレス・トゥ・プレイ」で初めて真のパートナーとして選んだのでした。ウイングス解散後ソロになってからしばらく1人で作曲をしていたポールにとって、エリックと面と向き合って1から曲を作ってゆくことは大きな刺激となり、その結果ポールとエリックは「プレス・トゥ・プレイ」セッションで多くの共作曲すなわち「McCartney-Stewart」ナンバーを生み出しました。結局は、レコーディングの際パジャム色の濃いプログラミングやオーバーダブを何度も繰り返したためエリックの持ち味である洗練されたメロディの魅力が殺されてしまい、そうしたポールのワンマンぶりにエリックがうんざりしてパートナー関係は解消されてしまうのですが・・・、天才メロディ・メイカーである2人の共作曲は今でも親しみやすい美しいメロディ節をアルバムで発揮しています。ジョンやデニー、そして後のエルビス・コステロとの共作とはまた一味違ったメロディックな世界が広がっています。
一連の「McCartney-Stewart」ナンバーにも、様々な種類の曲があり、2人のレパートリーの幅広さをうかがえます。例えば、無性にポップな『Tough On A Tightrope』『Write Away』、美しいバラード『Footprints』、エリックが当初アルバムの機軸となると予想していた生々しいロックンロール『Stranglehold』『Move Over Busker』などなど・・・。そんな中、ポールとエリックが最も「試行錯誤の共作」をしたと呼べる1曲があります。それこそ、今回紹介する『Pretty Little Head』です。どの曲でもそれなりの試行錯誤があったはずですが、なぜこの曲が「真の試行錯誤」なのでしょうか?
と言えば、実はこの曲、全くアイデアのない段階から行き当たりばったりで作られた曲だったからです。そう、この曲は2人にとって、まさに何もない真っ白な所からのスタートでした。まるでビートルズの「リボルバー」や「サージェント・ペパー」の頃のように、スタジオを舞台に様々なイマジネーションを集めて思いついたままに音にしてゆく。ポールいわく、「新しいスタジオで、新しいプロデューサーがいて、新しい作曲のパートナーがいる。そして何か違うことをやってみたくなった」そうですが、新たな音楽仲間たちと共に、全く未知の世界に飛び込んでみたという趣なのです。ふつふつと湧き上がる並々ならぬ創作意欲。何もない所から音楽を「創造してゆく」ことの楽しみ。ポールとエリック、プロデューサーのパジャム、そしてレコーディングに参加した演奏者たちは、そうした刺激的な音楽制作の醍醐味をこの曲を通じて味わうこととなりました。そして、こうしたアトランダムな試行錯誤の結果、この曲は革新的なサウンドで知られる「プレス・トゥ・プレイ」の中でも最も実験的な曲となったのでした・・・。すべての要素が、それまでに聴いたことのないような斬新なもの。ポール史上実に変てこな曲が出来上がることとなったのは、こうした経緯があったからでした。


それでは、そんな斬新で実験的なアレンジをこれから順に説明してゆきます。まずはサウンド。アルバム「プレス・トゥ・プレイ」自体、常のポールのイメージとはかけ離れた世界が繰り広げられているのですが、この曲ではそれにさらに輪をかけたような「ポールらしくなさ」が炸裂しています。それは聴いてみればすぐお分かりかと思います。無機質な音作りは、誰もが一瞬「これがポール?」と疑いたくなってくることでしょう(苦笑)。この曲でポールは、「僕がドラム、エリックがキーボード、ジェリー(・マロッタ)がビブラホンをやったり、みんな楽器を交換して新しい方向を見つけようとしたんだ」と語っていますが、それぞれ普段演奏することのない楽器を担当してみるという所からも、この曲にかける実験的精神が見て取れます。演奏者それぞれにとってこの曲は新たな挑戦だったのです。また、ポールによればこの曲は長い間インストだったそうで(公式発表されたものはヴォーカルが入っていますが)、まずは即興でバッキング・トラックを作っていったのでしょうか。その点もポール史上まれに見る実験的な試みです。そのためか、この曲は後付けの歌のメロディよりも、音やリズムを主体に聴かせるアレンジとなっています。これは、どんなに実験的になろうとまずはメロディありきだった今までのポールとは一線を画します。「プレス・トゥ・プレイ」はパジャム色が濃くリズム主体と言われることが多いのですが、その中でも特にリズム主義に磨きがかかっていると思います。
その中心を担うのは、やはりドラムス。曲を通して一定のリズムを保ち続けます。これは、先のポールの話によればポールの生ドラムも入っていますが、基軸となっているのは打ち込みによるコンピュータ・ドラムスです。「プレス・トゥ・プレイ」では、多くの曲で打ち込みドラムスを多用していますが、この曲もその例に漏れません。また、パーカッションもここではドラマーのジェリー・マロッタがプログラミングを行っています。特にアドリブ的なプレイもなくただ黙々と同じパターンを繰り返すアレンジは無機質そのもの。「パシッ、パシッ」といった機械的な肌触りのビートは、まさに'80年代といった所でしょうか。こういう点が当時のサウンドが嫌いな方に嫌われてしまう要因になっているのですが・・・(汗)。パワフルな音は当時ロック色を復活させていたポールの方向性に合っていそうですが・・・。ドラムロールのようなタムの音も耳に残ります。そして、そんな打ち込みドラムスがミドル・テンポで刻む4つ打ちのリズムは、当時流行のダンス・ミュージックを意識したようです。かつて「バック・トゥ・ジ・エッグ」「マッカートニーII」といったアルバムでもディスコやテクノ風の曲を作ったポールですが、ここでは最新のテクノロジーを生かしてより時代の先を行くダンス・ミュージックにしようとしているのが分かります。その観点だと、この曲は'80年代版『Goodnight Tonight』とも言えますね。エンディングはとてつもない爆音と共にドラムロールが炸裂して衝撃的に終わります・・・。
そしてもう1つこの曲で印象的な音が、随所で導入されたシンセ音です。これまた多くをコンピュータ・プログラミングで占めています。「プレス・トゥ・プレイ」ではシンセ音も多用されており作風に大きな影響を与えているのですが、やはりこの曲が最も多用されていると言えるでしょう。この曲では、実に多彩な音色のシンセ音が登場します。ストリングス系パッドの長音からピアノの高音域のような音によるアドリブ、そして今まで聴いたことのないようなエフェクト・・・。そしてそのほとんどが明確な「メロディ」ではない、斬新な「音」を出しています。ウイングス時代や「マッカートニーII」でもシンセを使用していたポールですが、その時は印象的なメロディを奏でるために主に使用していたのに対し、こちらは音の生み出すイメージ的効果を狙って多用しているのが大きな違いです。こうしたアプローチもやはり当時の音楽シーンの最先端でした。とにかく1回聴くだけで、ただただ衝撃的な音に驚かされます。「これがポール?」状態になるのは必至でしょう。また、使用されたシンセには明朗な音は1つも使われておらず、そのため全体を通してダークな雰囲気が漂います。エフェクトとあいまって不気味さすら感じさせます。かつてはダンス・ナンバーでもポールらしいポジティブで元気いっぱいな作風だったのが、ここで大きく路線転換したかのようです。この曲を一種特異なものにしているのも、そうしたポールらしからぬダークな音作りにあるかもしれません。個人的には、こうしたシンセ音の中でも第2節〜第3節のつなぎに登場する奇妙なエフェクト(2'20"〜2'38"の箇所)が何気にお気に入りです(笑)。後述する歌詞のエスニックさにも妙にぴったりだと思います。
その他には、ポール、エリックそしてカルロス・アロマーの3人による激しいエレキ・ギターが随所で挿入されていますが、これも明確なメロディをテクニカルに聴かせるというよりはエフェクトの要素が強いです。シンセ・サウンドに紛れて、あたかもノイズのようです。一方リズム隊であるポールのベースは影ながら印象的なリフを弾いています。ダンス・ナンバーっぽい感じが出ていますね。そして、何よりこの曲のイメージを決めているのがビブラホン。これは、先のポールの解説の通りドラマーのジェリーが演奏しています(驚きですね!)。イントロからエンディングまで、印象的なフレーズが繰り返し登場し、混沌としたこの曲のサウンドでもひときわ目立っています。ビブラホンならではの金属質ながらも美しい音が耳に残りますが、これまたダークで異様な雰囲気に一役買っています。
このように、時代を先行くダンス・ミュージックを意識したこの曲のサウンドは、リズム主体で無機質で、混沌とした不気味なアレンジが施され、十分実験的であることが分かります。しかし、それ以上に大胆と言えるのがこの曲のヴォーカルでしょう!なんと、ここではいつものポールからは考えられないヴォーカルスタイルを取っているのです!もうこれは一度聴いて頂ければすぐ納得して頂けると思いますが、聴いた瞬間「これホントにポールなの?」と驚いてしまうはずです。というのも、この曲でのポールのヴォーカルは、エフェクト処理によってもはやポールと聴き分けのつかない程に加工されてしまっているからです。力んだかのように勇ましく歌い上げるその声は、「誰か違う人が歌っているのでは?」と思ってしまうほど。壮大というか、オペラ風というか・・・、とにかく普段のポールの声でないのは明らかです。「プレス・トゥ・プレイ」では『However Absurd』でもこうしたヴォーカル加工をしていますが、この曲はそれ以上です。いくら七変化ヴォーカルを聴かせるポールと言えども、ここまで声が変わることは他に例を見ないでしょう。この点が、この曲が「ポールらしくない」と言われる最大の要因かもしれません・・・。さらにはコーラスも斬新なもので、これまたポールやエリックの声には到底聴こえないように加工されています。こちらも勇ましいスタイルを取っていますが、そんな声で歌われるのは「ウッサ・メジャー、ウッサ・マイナー」というフレーズの繰り返し。まるで呪文のように意味不明な言葉ですが、これがブリッジやエンディングに何度も登場し耳に残ります。気づけば口ずさんでしまうほどなのは、ポールのいつものキャッチー路線のせいか、それともこの異様さのせいか・・・。エンディングでは、ささやくような声から例の勇ましい声に移るというアレンジも施され、余計印象的です。このように、サウンドと並んで、いやサウンド以上に耳を奪われる斬新さを持ったヴォーカル・コーラスからも、この曲の不気味な雰囲気を容易に感じ取ることができます。最後の最後に入る低い声の男性による台詞も、ミステリアスです。さらにその後にあの爆音ですから・・・。
そしてミステリアスなのが歌詞です。そう、この曲は歌詞までが異様なのです。この曲は先述のように元はインストだった曲であり歌詞は後付けでできたものです。そのため分量も少ないのですが、これがまた難解というよりよく分からない内容です(汗)。推測するに、どうやら「Hillmen(ヒルメン)」という名の、神様か何かのしもべのような人たちについて歌っているようですが・・・(「忠誠の下、静かな戒律に暮らす」という一節があるため)。そして、その「Hillmen」が「pretty little head(とっても小さな頭)」を持った人(要するに子供か?)を守っている、という内容らしいです。第2節の歌詞から想像するに、どこか異国の世界の人々のことを歌っているのかと思われます。しかし、大体雰囲気はつかめるのですが全貌が見えない詞作です・・・。そもそも「Hillmen」自体が造語ですし。また、先の勇ましいコーラス「ウッサ・メジャー、ウッサ・マイナー」は、実は「大熊座、小熊座」という意味です。これもなぜ唐突に星座が出てくるのかは分かりません。しかし、この歌詞のおかげで、この曲にはミステリアスさ・不気味さと共にエスニックな雰囲気も漂っています。まさに「異国の伝説(exotic legends)」。そう考えれば、シンセの中には東洋かどこか異国を意識したようなエフェクトも登場しますし・・・。無機質なサウンドなのに、そんな味付けも感じられる。実に混沌とした世界です。
以上、この曲の斬新な側面を見てきましたが、この曲ほどにサウンド・曲調・ヴォーカル・詞作と揃ってポールが「らしくない」アレンジを繰り広げているのはほぼないと言っても過言ではないでしょう(『Check My Machine』辺りもなかなかですが)。そうなった理由は、もちろん。この曲が最初から実験的な意図で作られたからです。ポールとエリックは、曲のアイデアを予め練ってきて2人で照合しながら作る共作曲とは違い、ここでは本当に0からスタートしたのです。それも創作意欲が旺盛な状態で。今まで聴いたことのないような混沌とした音楽になるのは当然のことでした。そして、それに大きく寄与したのが、ヒュー・パジャムによるプログラミング主体のアレンジでしょう。世の先を行くパジャムにより、この曲の衝撃的な異様さはますます磨かれることとなりました。ポールとエリックの実験魂と、パジャムの革新的プロデュース。これが功を奏して、この曲は意欲作にして実験作「プレス・トゥ・プレイ」の象徴的存在となったのでした。ポール自身、後に「特異な曲」と認めているほどです。


さて、そんな創作意欲と試行錯誤から生まれたこの曲をポールは誇りに思っていたらしく、発売に際して2つの暴挙を起こします(苦笑)。これが、ポールにしては珍しく「やっちゃった」感の強い事件なのですが・・・。1つめの暴挙は、「プレス・トゥ・プレイ」発売後のこと。なんと、アルバムからのシングルカット第1弾に、こともあろうかこの曲を選んでしまったのです。よりによって、アルバムで一番実験的で難解な曲を、アルバムで最もポール節あふれるバラード『Only Love Remains』より先にシングルカットとは・・・(汗)。よっぽどポールは自分のサウンドの新境地に自信を抱いていたのでしょう。アルバム発売の1ヶ月後の1986年10月に、7インチシングル・12インチシングル双方で発売されますが(B面は『Write Away』。12インチには『Angry』のリミックスも収録)、これがどういう結果になったかは火を見るより明らか。既にこの頃までに、先行シングルの『Press』がチャートで苦戦し、アルバム自体も不振に陥っていたのですから・・・。英国で76位までしか上昇しませんでした。(ちなみに、日米ではさすがにヒットしないと見込んだのか、よりストレートな『Stranglehold』を代わってシングルカットしています。)76位という結果は、ウイングス時代・ソロ時代含めてポールのシングルではこれまでで最低の記録(汗)。こうしてポールはチャート不振のどん底に落ちてしまったのでした・・・。まぁ、理由はよく分かります。『Press』の時点で打ち込みを多用したサウンドに違和感を覚えつつそのポップぶりにまだ救われていたファンを、この曲のシングルカットで一気に「ポール、どうしちゃったの?」と不安にさせてしまったのです(その前にアルバムで困惑していますが)。それまでのポール節を期待してきたリスナーにとっては、この曲で失望するのは当たり前の話でしょう。あまりにも斬新すぎて、ポールらしからぬ内容ですから。ファンにポールへの疑念を抱かせるには十分でした。この辺は、ポールの音楽へのアグレッシブな姿勢と、旧来のポール・サウンドを求めるリスナーとのギャップがあだになりましたね・・・。このシングルが大コケに終わったことで、続いてシングルカットされた『Only Love Remains』までもチャートで伸び悩む結果に。もしリリースの順番を変えていれば、きっと『Only Love Remains』も売れて、まだ成功できていたに違いありません・・・。ポールも惜しいことをしたものです。
なお、シングルには別ヴァージョンが収録されています。さすがのポールも、アルバム・ヴァージョンをそのまま収録すると売れないことは分かっていたのでしょうか(苦笑)。よりシングルに似合った格好にリミックスをした上でシングルカットしました。そのリミックスでも、7インチと12インチではまたヴァージョンが違いややこしいったらありゃしないのですが、ここからはこの2種類のリミックスについて解説してゆきます。なお、両ヴァージョンとも未CD化です。「プレス・トゥ・プレイ」期のリミックスは未CD化というケースが多いのですが、アルバムの大ファンにとっては早くCD化してくれ・・・といった所です(笑)。アルバム未収録曲・未収録ヴァージョンを集めたブートでは容易に入手できますけれど。
まずは、7インチに収録されたいわば「シングル・ヴァージョン」。こちらがメインでシングルで売り出されました。リミックスを行ったのは『Angry』のリミックスと同じラリー・アレキサンダー。このヴァージョンは、アルバム・ヴァージョンと大きく異なる点がいくつもあります。そのため、ちょっと聴いただけでは「同じ曲!?」状態です(『It's Not True』ほどではないですが)。やはり売るには抜本的に変える必要があったのですね(それでもシングルカット第1弾というのはどうかと思いますが・・・)。まず、根底を成す打ち込みドラムスが新たなパターンに差し替えられています。アルバム・ヴァージョンでは全体的に重々しい雰囲気が漂っていましたが、ここでは圧倒的に軽い耳障りの音になっています。「パシッ、パシッ」という音が中心になっています。'80年代を思わせる無機質で機械的なビートであることは変わらないのですが、アルバム・ヴァージョンに比べるとよりキャッチーなリズムになっている感があります。ダンス・ミュージックらしい軽快さはこちらが上です。楽器面では他にもかなり音を差し替えており、アルバム・ヴァージョンにあった音がなくなったり小音量のミックスになったりしている箇所が多いです。アルバム・ヴァージョンではダークで不気味なサウンドが展開されていましたが、そうした音が減ったため、このリミックスはかなり明るいです。その方がシングル向きではあります。特に大きいのが、あのビブラホンの音がほとんどなくなっている点です。これは曲のイメージを大きく変えています。他にも、ギター・フレーズやエフェクトがなく、アルバムで聴き慣れていると衝撃的です。逆に付け加えられた音も多く、中でもベースのフレーズが前面に出ています。続いて曲構成も、イントロとエンディングを大幅にカットして、アルバム・ヴァージョンが5分ちょっとなのに対して、このシングル・ヴァージョンは4分にも至りません。この点も、シングルの方が聴きやすい要因です。また、第3節の後にもう一度第1節に戻っています(ただし第2節の歌詞も混じっている)。そして、シングル・ヴァージョンは爆音で終わらずフェードアウトしてしまいます。
そして、何よりこのシングル・リミックスがアルバム・ヴァージョンと大きく違うのは、ポールのヴォーカルです!アルバム・ヴァージョンではご存知「これがポール?」といったヴォーカルの加工処理がされていましたが、なんと、リミックスではポールのヴォーカルは普段の声に差し替えられているのです!・・・やっぱりこれもセールスを意識してか(当然のことでしょうけど)。これが一番曲のイメージを変える要因となっています。しかも、ポールの「ノーマル・ヴォーカル」はかなり軽やかに歌っています。アルバムでの壮大で力んだスタイルとは全然違います。コーラスは、「ウッサ・メジャー、ウッサ・マイナー」の部分は相変わらず例の不気味な声なのですが、そこにアルバムにはないポールの掛け合いヴォーカルが入ります。これもかなりイメージが異なります。掛け合いヴォーカルがあるおかげで、メロディにキャッチーさも出ている気がします。特にアルバムでは延々と「ウッサ・メジャー、ウッサ・マイナー」が続くエンディングはがらっと装いを新たにしています。ポール・ファンからすればとっつきやすさから言えばもちろんポールの生の声が聴ける方がよいわけで、このシングル・ヴァージョンの方がお気に入りという意見が圧倒的です。セールス的にもこっちの方がキャッチーで売れるという考えは妥当でしょう。ただ、結局は結果に結びつかなかったですが・・・(汗)。ちなみに、個人的にはミステリアスでエスニックな雰囲気も味わえるアルバム・ヴァージョンの方がお気に入りです(笑)。異端でしょうか・・・?
続いては12インチに収録されたリミックス。こちらはJohn Potokerが手がけたものです。12インチという時点で皆さんご想像しているかもしれませんが、'80年代恒例のロング・ヴァージョンです(笑)。7インチでは4分足らずだったのが、ここでは演奏時間が7分近くもあります。下敷きになっているのは7インチ・ヴァージョンで、よってヴォーカルもポールの「ノーマル・ヴォーカル」です。また、「ウッサ・メジャー、ウッサ・マイナー」の部分の掛け合いヴォーカルも収録されています。その一方で、曲構成はアルバム・ヴァージョンを引き伸ばしたかのようなつくりになっています。さらに、サウンド的にはアルバム・ヴァージョンで使用されていた音源がかなり復活しています。ビブラホンも随所で使用していますし、イントロ・エンディングなどはアルバム・ヴァージョンそのままの雰囲気です。こうした点から、このヴァージョンはシングルとアルバムの中間点を取ったようなリミックスと言えるでしょう。アルバム・ヴァージョンのミステリアスさをそのままに、シングル・ヴァージョンのヴォーカルで聴きやすく中和したような感じです。なので、双方のよさが堪能できます。そういった点では実に重宝するリミックスです。一方でリミックスならではのアレンジもあり、4つ打ちビートが中心になっていたり(冒頭はドラムソロ)、歌が入るまでに2分ほどかかったり(歌が入る直前のリズムが途切れる箇所がいかにもリミックス!)、コーラスが加工されて登場したりと、'80年代の雰囲気たっぷりです。おなじみのリミックスでも結構凝っていて割かし楽しく聴けるのですが、そういう系統が苦手な人にとっては長くて退屈するかもしれません(汗)。私は十二分に楽しんでいるんですが(笑)。特に例の第2節〜第3節間のエフェクトが大々的にフィーチャーされているのがお気に入りです。
さて、ポールもう1つの暴挙があります。それが、プロモ・ヴィデオの制作です。こんなに実験的でこんなに変てこな曲でプロモが作れるのか?という疑問がわくでしょうが、ポールは本当に作ってしまったのですからすごいです!よっぽどこの曲に力を入れていたんでしょうね。この曲のプロモ・ヴィデオの監督はスティーヴ・バロン。マイケル・ジャクソンの「Billie Jean」などのプロモも手がけており、当時は売れっ子でした。そんな監督の影響あってか、プロモは曲と同様、かなり異色の作品となりました。特に、モノクロとカラーを使い分けた映像処理、合成技術の多用によるスケールの大きい非現実的な展開などは、普段のポールのプロモにはない特徴です。ポールは「映画的な映像で美しく撮られている」と後にコメントしています。演奏シーンはなし。なお、使用されている音源は7インチシングル・ヴァージョンです。
プロモの内容は、歌詞から想像できる「子供を守る神秘的な人たち」を題材としたストーリー仕立てとなっています。登場するのは、とある家庭。そこで夫婦喧嘩が始まる所からプロモは始まります。外が嵐となり中にまで雨風が入り込んでいるのが、喧嘩のすさまじさを物語ります。険悪な両親を見ていた娘は、たまりかねてかばんを抱えて家を出てしまいます。そう、このお話の主人公はこの家出少女なのです。その証拠に、プロモの冒頭ではビートルズ時代にポールが書いた『She's Leaving Home』のエンディングが使用されています(この曲は家出少女を題材にしている)。電車に乗り、少女は遠く見知らぬ街へ着くのですが、そこはビルばかりが立ち並ぶ殺伐とした暗い街。途中途中では、ポールが大きな電光掲示板に登場します。なお、ポールのパートは1986年10月18日に撮影されています。街で少女が出くわしたのが、黒装束を着た悪魔たち。小さくなったり大きくなったり変幻自在のサイズで登場します(というより、このプロモの登場人物はみな周りの景色とサイズが変わることが多いです)。空腹になった少女は、道端に捨ててあるハンバーガーを手に取ろうとしますが、そこには悪魔がひしめき合っていました。その後も執拗に少女を追いかける悪魔たち。今度は巨大化してビル街に出没。ついに少女に襲い掛かり、かばんや上着を奪ってゆきます。逃げ惑いつつも、いよいよ絶体絶命のピンチを迎えた少女。・・・と、そこに現れた正義の味方こそ・・・、我らがポール・マッカートニーです(笑)。ここでは、なんと巨大化してビルの谷間から大きな顔を覗かせます。早速ポール、少女を救うべく悪魔に攻撃を仕掛けます。そう、息を吹きかけて悪魔を吹き飛ばしたのです!突然のポールの登場になすすべもない悪魔たちは息で四方八方に飛ばされてゆきます。再び息を吹きかけるポール。今度は少女の元にかばんと上着を返してくれます。そして再度息を吹きかければ・・・、今度は電車がやってきます。この電車に少女を乗せて、家に帰してあげようと言うのです。息を吹きかけるたび、電車は家へ向かって走ってゆきます。巨大化しているものの、ポールの呼気には恐れ入ります(笑)。そして、最後に少女は無事家に帰り着き、両親も仲直りしていて、ハッピー・エンディングで締めくくります。


ポールは、このプロモのストーリーに関して「家を出ることは危険も伴う」ということを伝えたかったそうです。その分ポールは脇に回っていますが、メッセージ性の強い内容は興味深いです。そしてそれを伝えるための技法がここでは革新的で、非常に印象に残ります。暴挙といえども(苦笑)、結果的にしっかりした出来となっているのはすごいですね。ポールのアイデアと監督の手腕の賜物でしょう。異色ですが、見事曲のイメージ(特にシングル・ヴァージョン)にはまっていると思います。よくあんな実験的な曲でプロモが作れたと感心しますね。見所は、やはり後半の巨大化したポールでしょう!正義の味方の登場です(笑)。なお、このプロモは当時発売された公式ヴィデオ「Once Upon A Video」(現在廃盤)に収録されたほか、現在は公式プロモ・ヴィデオ集「The McCartney Years」に収録されています。こんなマニアックな曲ながらポールがコメンタリーを入れているのがうれしいです。
この曲のアウトテイクが発見されており、「Pizza And Fairy Tales」や「The Alternate Press To Play Album」といった「プレス・トゥ・プレイ」関連のブートで聴くことができます。これはアルバム・ヴァージョンのアウトテイクで、曲構成は公式テイクと同じです。演奏もほぼ公式テイクに近く、だいぶアイデアが練り固まった頃のテイクだと思われます。ただし、ミックスがだいぶラフな上、ドラムパターンやシンセなどで若干異なる演奏があります。そして、何より興味深いのは、このテイクでのポールのヴォーカルは普段の声で歌われている点でしょう!アルバム・ヴァージョンに「ノーマル・ヴォーカル」という取り合わせはここでしか聴けない貴重なテイクです。ガイド・ヴォーカルのためか、だいぶ気を抜いた歌い方です。まだ歌詞は完成していなく、この時点では第2節・第3節でも第1節の歌詞を繰り返しています。そして、あの印象的な「ウッサ・メジャー、ウッサ・マイナー」のコーラスと、最後の台詞がまだ入っていません。そのため、後半は完全インスト状態となっています。この点はちょっと退屈するかもしれません(汗)。しかし、普通の声で歌うアルバム・ヴァージョンという点で必聴であることには変わりありません。各楽器の演奏もじっくり味わうことができます。
ここからは個人的な話を。私は、この曲を聴く前にプロモ・ヴィデオの話題は聞いていたので、ストーリーから「感動的なバラードタイプの曲なのかな?」と思っていました。そんな先入観の上で初めて聴いたときの衝撃は今でも忘れられません。イントロまではまだよかったものの、あの奇妙な声で「ヒルメン、ヒルメン、オーオ、オーオ・・・」と始まった瞬間、思わずタイトルを確認してしまいました(笑)。「まさかそんなわけは・・・」と思いながら。後はただあっけに取られておりました。一種のカルチャーショックのようでした。『Mull Of Kintyre』並みのショックでしたよ。それが影響して、私はしばらくの間この曲を好きになれなかったのですが(汗)、やがて「プレス・トゥ・プレイ」ブームが私に到来すると一気に好き・・・というより「面白い!」と思うようになりました(笑)。今ではこの「らしくなさ」がとても面白いと思っています。アルバム中最も変てこでダンサブルなので、そういう点ではかなり好きです。現在では、だいぶ前にこのコラムで紹介した『Talk More Talk』より好きかもしれません。さすがに『Press』や『Angry』にはかないませんが。個人的には、先述したようにシングル・ヴァージョンよりアルバム・ヴァージョンの方が好きです(笑)。そういう人は少ないと思いますが・・・。あのミステリアスな面が好きなんですよ。あれがないシングル・ヴァージョンはなんだかあっけなくて。でも、12インチ・リミックスは好きですよ?(笑)もっと少ないか、そういう人は・・・。ポールには、ぜひ一度これを演奏してほしいです、ライヴで(苦笑)。雨の日だけの特別セットリストでいいので。
いまやポール本人までもが「駄作」扱いする悲しき運命の「プレス・トゥ・プレイ」。確かに、ポールらしくなく、初心者向けでもなく、もろに'80年代サウンドが濃くてくせがありますが、だからこそポールが当時どんな音楽を目指そうとしていたのかが分かる1枚です。そしてその中でも、この曲の実験的なサウンドにはポールの並々ならぬ創作意欲の結果が詰まっているのです。最初に買うアルバムとは言いませんから、ぜひ一度だまされたと思って聴いてみてください。はまる人ははまる、分かる人には分かる、そんなアルバムですよ!できればシングル・ヴァージョンを聴いた方がとっつきやすく、この曲のよさが伝わりやすいのですが、未CD化ですからねぇ・・・。

と、今回もかなりマニアックにいきましたー(笑)。そして次回紹介する曲のヒントは・・・「ラスト・ナンバー」。マニアックが半減しますが、お楽しみに!
(2009.9.07 加筆修正)
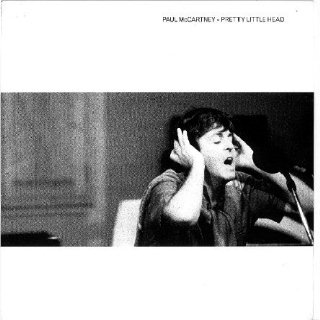

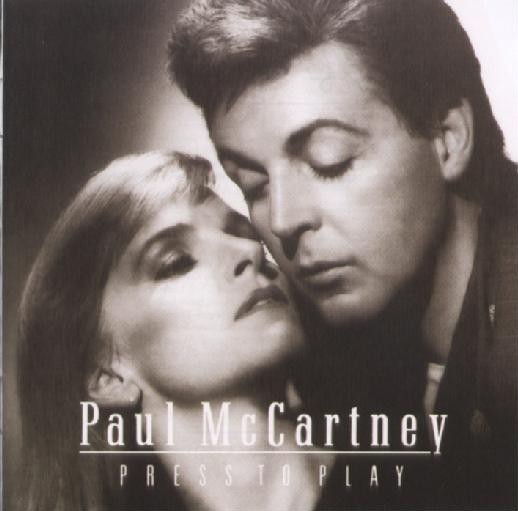
(左から)当時のシングル盤(英国のみ発売)。ポールの暴挙は見事砕け散りました(笑)。左が7インチシングル、右が12インチシングル。
アルバム「プレス・トゥ・プレイ」。実験的なサウンドが光るポールの意欲作。私のお勧め!