
Jooju Boobu 第66回
(2005.10.23更新)
Jet(1973年)

マニアックな曲が続いている(苦笑)「Jooju Boobu」第6層。しかし、今回は打って変わってとびきり有名な曲を紹介します!それも、ポール・マッカートニーのソロ活動の中でも珠玉の名曲の1つ!ポールのベスト盤はもちろん、洋楽のオムニバス盤さらにはポールのライヴですっかりおなじみの「あの曲」ですよ!ポール・ファンなら、聴きたての初心者でも知っている大人気ヒット曲とくればもうお分かりでしょう。・・・そうです。今日は、1973年に発売されたウイングスの名盤「バンド・オン・ザ・ラン」からのスマッシュ・ヒットとなった永遠のロック・ナンバー『Jet』を紹介します。ほら、もうこの曲は皆さんご存知ですよね・・・?(笑)
ウイングスはもちろん、ポールの歴史に燦然と輝く一大名曲として、今でもポール・ファンのみならず'70年代洋楽のファンに愛され続けているこの曲。あまりにも有名な曲なので私が語る前にどんな曲なのか皆さんよくご存知かと思いますが(汗)、今回は初心に立ち返って『Jet』の魅力をたっぷり語ってゆきたいと思います。あまりも有名な曲なので、語ることが多く長文になりそうですので、覚悟の上読み進めてください(苦笑)。
まずはこの曲が発表された頃のポールの時代背景を復習してみます。アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」セッションでのウイングスについてはあまりにも有名であり、このコラムでも既に何度か触れていますが、名曲『Jet』が生まれたこの時期のウイングスは危機的状況下にありました。1973年夏、新作に向けて曲を書き溜めていたポールは、新作をレコーディングする地としてアフリカはナイジェリアのスタジオを選びました。ヴァケーションも兼ねてゆったりセッションを・・・と思っていたのですが、悲しきことにこれがウイングス崩壊の危機を生んでしまいます。まず、ウイングスのギタリストであるヘンリー・マッカロクが音楽観の相違を理由にグループを脱退。さらに、ドラマーのデニー・シーウェルもナイジェリアに飛ぶ直前になって脱退を表明。「アフリカに行くのは嫌だ」とまで言われてしまうことに・・・(汗)。仕方なくポールは、残された愛妻リンダとデニー・レインの3人でナイジェリアに渡り、レコーディングを行います。メンバーの相次ぐ脱退という緊急事態の上にポールを待ち構えていたのは、豪雨・猛暑・デモテープの盗難そして劣悪なスタジオ。まさに泣きっ面に蜂のような状況でした。しかし、ここでくたばるような凡庸なポールではありません。ここから、リンダとデニーの強い協力に支えられながら火事場の馬鹿力で挽回してゆくのです。これまで以上に結束を固くした3人のメンバーによりレコーディングは順調に進行。セッションには程よい緊張感が漂い、いつしかまとまりある演奏となりました。こうして完成した作品はロンドンに持ち帰りオーバーダブが施されると、これまでのウイングス作品を凌ぐ出来に仕上がりました。このような紆余曲折を経て世に出ることとなったのが「バンド・オン・ザ・ラン」で、発売されるや否や世界中で大ヒットを記録、グラミー賞を獲得する栄誉も得て超大ヒットアルバムに成長しました・・・というのは有名な話ですね。ウイングスにとっては結成以来初めて名声を確かなものにした1枚であり、今でも「ウイングスの名盤」「最高傑作」と呼ばれ続けるほどです。収録曲自体はアフリカに渡る前、2人のメンバー脱退以前にほとんどできていたのですが、それを様々な困難を乗り越えながら高い完成度で仕上げてしまうウイングス、ポールは本当に素晴らしいです。


「バンド・オン・ザ・ラン」の楽曲は概して「名曲」と呼ばれており、どれも根強い人気を保つ高レベルの作品なのですが、中でもシングルカットされた2曲・・・つまり『Band On The Run』と『Jet』は、メロディも構成もアレンジも寸分の隙もない完璧さで、今でもウイングスそしてポールの代表曲として広く知られています。『Band On The Run』のどんな所が完璧であり人気を保つ理由となっているのかは、既にその曲を紹介した際に触れましたが、3部構成によるドラマチックな展開、キャッチーなメロディ、効果的に変化してゆくダイナミックかつ爽快なアレンジなどが挙げられます。それでは、今回ご紹介する『Jet』が名曲として今でも聴き親しまれている、その根源とはどこにあるのでしょうか・・・?これから順次紐解いてゆきます。
『Band On The Run』がどちらかと言えばポールお得意の「ポップ」のイメージが強いのに対して、この『Jet』といえば・・・皆さんのご想像通り「ロック」のイメージが強いロック・ナンバーです。『Band On The Run』とはまた違ったテイストの曲なのです。しかし、一言にロックと言ってしまえば簡単ですが、この『Jet』はそこらの単なるロックでは終わるようなことはありません!さすが名曲。それは、単にハードでロック色が濃いだけでなく、同時にポールらしさも持ち合わせているからです。そのポールらしさとは、ずばりストレートさとキャッチーなメロディです。元々シンプルで分かりやすい構成・演奏の曲を多く世に出しているポールですが、『Jet』でのロックも、何も奇をてらった難しいことをせずストレートさを前面に出しています。ハードさは幾分減ってしまいますが、そこがポールならでは。力強いながらもとても聴きやすい軽快さを感じられる内容となっています。それはメロディも同様で、こちらも一度聴いたら忘れられないようなキャッチーなメロディです。天性のメロディ・メイカーのポールならではですね。特にタイトルコールの箇所はとってもシンプルで覚えやすいですよね!
ポールはビートルズ時代から既にいろいろロック・ナンバーを書いてきていますが、この曲に代表されるストレートさとキャッチーさをメインに打ち立てたポール流ロック・ナンバーが炸裂するのは、実はこの時期からであり、極論すればこの『Jet』でその方向性が確立されたと言っても過言ではないほどです!まさにこの曲こそ、ウイングス時代にポールが生んでゆく様々なロックの名曲のさきがけなのです(同時期の『Helen Wheels』も似たような役割を担っているとも思いますけど)。特に初期ウイングスにおいてはポールはブルージーでスローなロックに傾倒していたので、その変わりようは目を見張るものがあります。明らかにこの曲以降、ポールの書くロック・ナンバーはストレートさとキャッチーさが中心のダイナミックなものとなります。『Junior's Farm』『Rock Show』『Girls' School』『Getting Closer』などなど・・・。『Jet』はまさにその原動力となった曲なのです。
演奏の全体的な魅力として挙げられるのが、緊張感と疾走感です。なかなかそれを言葉で表せないのがもどかしい所ですが・・・(汗)。この曲では緊張感が曲全体に張り詰めていてそれがリスナーをひきつけます。演奏が重低音を強調しているのは大きな要因でしょう。特にブラス・セクションとムーグ・シンセの演奏の影響は大きいです。そして曲構成。これが効果的でドラマチックな展開を見せてくれます。この曲ではイントロにブラス・セクションをフィーチャーしたユニークなリズムのパートがありますが、これがインパクトたっぷり。この後どんな展開になるのかはらはらさせてくれます。これがしばらく続いた後に、タイトルコールのシャウトが入り一気に加速してゆく流れは痛快です。この切り替わる瞬間が、ファンにとっては非常にたまらないのです(皆さんもそうですよね?)。その後もタイトな演奏が緊張感を出し続けます。エンディングもイントロのパートが再登場し、メリハリがついています。最後の最後、意外とおとなしく迎えるロックらしからぬ(?)エンディングがポールらしいといえばポールらしいですが(笑)。疾走感は、イントロとエンディング以外のパートで常に感じられます。次から次へと矢継ぎ早に突っ走る息をつかせぬ構成がずっと続きますが、これが本当に痛快です。あっという間にエンディングに到着してしまうようなぐいぐい引っ張ってゆく展開が見事です。前曲『Band On The Run』の第3パートに負けず劣らずです。こうした緊張感・疾走感はまさに一発勝負のフィーリングを持っていて、なかなか再現がしにくいのか、スタジオで録音されたヴァージョンがこの点では最高の内容だと思います。ウイングスは、3人にメンバーを減らしながらも固い結束の元こんな気迫あふれる名演を残してくれたのですから、これはすごいことです。この演奏が生まれたのは奇跡に近いですね。後述するライヴ・ヴァージョンではいまいちそこら辺が追いついていない気がします・・・。


演奏面を詳しく見てみましょう。先述したように、この曲はウイングスが3人(ポール、リンダ、デニー)の時期に録音されています。ちなみに、レコーディングはこの曲のみナイジェリアからの帰国後、ロンドンで行われています。しかし、依然3人であることには変わらず、この曲でもベーシック・トラックは3人のみで録音されています。しかし、3人にしては意外なほど分厚い音に仕上がっているのが面白いです。まぁ多重録音もしていますが・・・、ちょっと聴いただけではこれが3人のみによる演奏とは思えません。曲を聴いてまず印象に残るのが、先にちょっと触れましたがブラス・セクションです。イントロとエンディングの「ちゃーちゃっちゃっちゃー」というメロディはポールをあまり知らない方でも皆さん聴いたことがあるでしょう。それほど耳に残ります。やけにヘヴィーな音色が先の緊張感を出しています。この他にも随所でブラス・セクションはアクセント的に登場します。アレンジは、「バンド・オン・ザ・ラン」のオーケストラ・スコアを担当したトニー・ヴィスコンティによるもの。このフレーズはポールのアイデアかヴィスコンティのアイデアかは不明ですが、いずれにせよいい仕事していますね。ロックらしからぬ(?)エンディングにちらっと登場するサックス・ソロは、後にウイングスのツアー・バンドの一員となるハウイー・ケイシーの演奏です。
ブラス・セクションに並んで耳に飛び込むのが、キーボードでしょう。これは、当時ムーグ・シンセと呼ばれていたシンセサイザーの一種で、リンダが弾いています。ポールがウイングス結成後しばらくしてこのムーグに興味を示しだし、様々な楽曲で使用するようになったのは有名ですが、そのよい例としてこの曲を挙げることができるでしょう。ポールのムーグの使用法のコツがよく分かるからです。この曲でムーグは、大半の箇所で低音一音がずっと鳴り響いています。よく聴くと「ブーン」と鳴り続いているのが分かるはずです。これは、ブラス・セクションと同じく重低音を強調していて、緊張感を出すのに一役買っています。別に技巧的な演奏では全くないのですが(苦笑)、いい隠し味として機能しています。そしてこの曲のムーグときて一番知られるのが、ご存知間奏の部分。こちらは一転して高音域で、歌いだしのメロディをソロで弾いています。これがめちゃくちゃ印象的なのは言うまでもないでしょう!元々のメロディがシンプルで覚えやすいのに、それをちょっと異質で斬新な(←あくまで当時としてですが・・・)音で奏でられると、否応にも惹かれてしまいます。いかにも簡単なフレーズになっているのは演奏が得意でないリンダのためでもありますが(この曲のソロはリンダの指一本弾き)、それと同時にポールはムーグを効果的に使用するにはキャッチーなメロディが最適と分かっているからでもあります。ただ闇雲にムーグの音を実験的に多用するのではなく、単音で印象的なソロを弾かせてメロディを際立たせるためにもっぱら使用している所に、ポールのセンスのよさを感じます。この曲でムーグが目立つのはそうしたポールの気の利いたアレンジのおかげなのです。なお、ムーグの他にも間奏には高音をたたきつけるようなピアノが入りますが、これは恐らくポールの演奏でしょう。こちらも曲を盛り上げるのに効果的です。
その間奏は他にもギター・ソロも聴き所であります。演奏はデニーとポール。曲全体では目立ったソロは少ないですが、やはりロック・ナンバーであるこの曲の根幹を担っています。イントロの力強いカッティングもインパクトあります。そして最後に、やはりドラムスを挙げねばなりません。「バンド・オン・ザ・ラン」セッションでは、ドラマーが「アフリカに行くのは嫌だ」と脱退しているので(笑)、代わりに素人ドラマーのポールがドラムスをたたいていますが、この曲も例に漏れずポールによるドラミングを聴くことができます。ポールのドラミングに関してはいろいろ言われていますが、下手なんだけど妙にツボにはまっている「ヘタウマ」なものが多く、この曲も可もあり不可もあり・・・といった状況であるのは否めません(汗)。イントロ&エンディングでドラムパターンを変える試みや、詰まりながらもちゃんと的確に入っているフィルインなどはそこそこ聴けます。リズムのノリも十分。さすがマルチ・プレイヤーは一味違いますな。結構上手いんだなぁ、と思わせます。しかし、欠点を言ってしまえば、スタジオ・ヴァージョンでのポールのドラミングは圧倒的に力不足です・・・(汗)。躍動感とダイナミックさは、ベテランドラマーに比べればやはり物足りなさを感じざるを得ません。同時期の『Let Me Roll It』はもっとダメですが(苦笑)、ポールの力量にも限界があるということです。全体的な緊張感・疾走感が最高なだけに少し残念です。
そして、こうした名演が光る演奏に負けじと魅力を輝かせているのが、何を隠そうポールのヴォーカルです!これがなくてはこの曲の魅力が一気に落ち込んでしまいそうなほどです。前曲『Band On The Run』では軽快な歌いっぷりだったポールですが、ここでのポールは一転してロックらしい力強さを携えて歌います。力み気味の野太いその声はまさに「熱唱」という言葉がぴったりです。それでいて曲のキャッチーさを削ることがないのがまた素敵な所です。さらにポールは、そんなハイテンションな歌い方をこの曲では終始貫いています。イントロでうっすら聴こえるアドリブから既に熱いです。それどころか、後半にかけては徐々にシャウト交じりになりますますヒートアップしてゆきます。崩し歌いも入りながら、圧巻と言えるエンディングのアドリブまで、こちらも演奏同様疾走感を感じられます。甘いヴォーカルをよく想起されがちなポールですが、実は立派なロッカーであることを改めて実感できる1曲なのです。特に、スタジオで録音したこのオリジナル・ヴァージョンでのポールの熱唱は完璧です!これまた、後のライヴ・ヴァージョンはオリジナルに追いつけていない気がします・・・。これは他の人が歌ってもそうで、蛇足ですが私はこの曲をカラオケで歌ったことがありますが、オリジナルの野太いテンションは再現が難しいです(単純に自分の歌が下手だからかもしれませんが・・・)。まぁ私を引き合いに出さずとも(苦笑)、オリジナルのポールのヴォーカルは本人でも再現不可能なほど最高の出来なのです。ちなみにハイライトは2度目の間奏だと個人的には思います。ポールやデニーのアドリブが一番盛り上がっています。
コーラス面ではやはり何と言ってもタイトルである「ジェット!」の掛け声でしょう。これなくしてはこの曲は語ることができません。緊迫感ある冒頭を破って登場し、以降随所で繰り広げられる「ジェット!」の豪快さは聴いていて本当に痛快です。歌っているのはポール?デニー?いずれにせよウイングスにしては(と言うと失礼ですが)非常に力強い掛け声です。曲にいいアクセントを生んでいるのは言うまでもなく、キャッチーさも同時に生んでいます。だって皆さんも、これを聴いたらすぐに「ジェット!」と歌いたくなるでしょう?これがライヴでは重要な役割を担うことになるのですが・・・その辺は後述します。そしてこれまた、オリジナルが完璧な出来なのでした(ライヴではどうもあの豪快さを再現しきれていないようで・・・)。一方、ウイングスらしいコーラスもあります。ウイングスの魅力である、ポール、リンダそしてデニーの3人によるハーモニーです。ポールの熱いヴォーカルとはコントラストを成しますが、この曲のウイングスらしさを引き出してくれます。一部の語尾を一緒に歌うという形がいい感じです。もちろん、「ジェット!」の掛け声の後の「ウウウ、ウーウウ、ウーウウ」も印象的ですね(リンダの声が目立つ)。


と、ここまでこの曲の醍醐味を語った・・・つもりなのですがなんだか変な文章だなぁ(汗)。でも、演奏も完璧なら、ヴォーカルも完璧。まさに『Jet』がポール史上まれに見る傑作であることがよーくお分かりかと思います。まぁ、この曲に関してはもう百聞は一見にしかずですね。一度だまされたと思って聴いてみるしかないです(苦笑)。絶対だまされない、期待を裏切らない内容ですから!・・・うーん、名曲になればなるほど曲の感想は難しいものです(笑)。でもここでくじけては仕方ないので頑張って今日のコラムを完成させます。
さて、ここからは予備知識的なことを補足として書いてゆきます。まずはタイトルと歌詞。タイトルはずばり「ジェット」ですが、皆さんはこれで何を思い浮かべますか?やはり最初にジェット機を思い浮かべることでしょう。しかし、この曲はジェット機の歌ではありません(笑)。確かにジェット機を想起させる演奏ですが・・・。かといえば、ジェット気流の歌でもありません。では一体ここでの「ジェット」とは何かと言えば・・・、ポールの飼い犬の名前なのです。ジェットという犬をポールが飼っていて、それにインスパイアされて書かれたのが『Jet』というわけなのです。名曲の裏側に犬がいたとは、これはちょっと驚きですね。動物好きのポールはいろんな犬を飼ってきましたが、ビートルズ時代に当時の愛犬・マーサの名前を冠したのが『Martha My Dear』(1968年)という曲であるのは有名な話ですね。そちらはヒットすらしませんでしたが、この『Jet』は見事なスマッシュ・ヒット。さらにポールの一大名曲にまで上り詰めました。ポールにとっては愛犬さまさまですな。ちなみにヒット曲の立役者・ジェットはラブラドール犬で、当時の飼い犬が生んだ数匹の子供のうちの1匹だそうです。ジェットの兄弟の中には「ゴールデン・マラシーズ」という名前もいたそうな・・・。もしちょっとずれてポールが「ゴールデン・マラシーズ」という曲を作っていたとしたら・・・(苦笑)。愛犬の名前から生まれた曲とはいえ、歌詞自体は犬を歌ったものではありません。これは『Martha My Dear』と同じですね。その内実は、皮肉交じりのラヴ・ソングです・・・が、これが厄介で、実はラヴ・ソングに取れそうで内容がかなりナンセンスなのです。なので、ラヴ・ソングと言うべきか迷ってしまう所です。「ジェット」は女性の名前に置き換えられていると考えられますが、よく読むと支離滅裂な内容で、急に特務曹長が出てくるなどめちゃくちゃです。ポールがナンセンスな歌詞を書くことは極めて珍しいので、そんな現象がヒット曲にあるというのが興味深いですが、どうやら内容よりも語呂合わせを優先して書いたようです。そのためか、韻の踏み具合は最高です。なお、途中「婦人参政権運動(lady suffragette)」という単語が出てきますが、ポールによればこれに政治的な意図はないとのことです。ただ「ジェット(Jet)」と韻を踏むために入れたようです。後にポールは女性賛歌として『Daytime Nightime Suffering』という曲を書きますが、それとは趣旨が違うようですね。
これまで見てきたように、メロディも演奏もヴォーカルも(ついでに歌詞も)すべて完璧なこの曲は、誰もがアルバム「バンド・オン・ザ・ラン」の代表格でありシングルにふさわしい曲だと思うはずですが、なぜか当初この曲のシングル発売の予定はありませんでした。それどころか、『Helen Wheels』を先行シングルとして発売してしまうほどでした。これは、ポールが当時考えていた「アルバムとシングルでは別の楽しみを与えたい」という信条があり、アルバムからのシングルカットを躊躇したということが大きく作用しています。ポールいわく「アルバムが純粋なものに仕上がったのでシングルは出したくなかった」とのこと。しかし、アルバムは最初のうちはヒットしたものの、やがて下降しだしました。ポールがその状況に困っていた頃、声をかけた人がいました。それは米国キャピトル・レコードの担当者、アル・コーリーでした。そこでコーリーがポールに提案したのはずばり、「『Jet』をシングルカットしよう!」。コーリーは、『Jet』がシングル発売されれば確実にヒットすると思っていました。この時のやりとりに関するポールとコーリーの述懐は「バンド・オン・ザ・ラン」の25周年記念盤に収録されていますが、コーリーはこの曲の持つキャッチーさに目をつけていたのです。「絶対売れるよ!」と強く勧められたポールも心を動かし、年が明けた1974年2月にようやくこの曲がシングルカットされるに至りました(B面はファースト・プレスのみ『Mamunia』、以降は『Let Me Roll It』)。シングルは発売されるとスマッシュ・ヒットを記録。コーリーの言うとおりになりました。ただし、意外にもチャート上では英米共に最高7位止まり(米国キャッシュボックス誌では5位まで上昇)。既にアルバムが出回った後だったため、アルバムを買った人が買わなかったこともあったのでしょうが、TOP 5に入らなかったのはちょっと異常ですね・・・。ちなみにビルボード誌の1974年年間チャートでは77位。しかし、ラジオ局では毎日のように『Jet』が流れ、アルバムの売れ行きにも好影響を与え、この曲のシングルカットは間違いなく成功したのでした。この曲を後年「永遠に聴き継がれる曲」と評価するコーリーには、確かにヒット曲を見る目があったのでした。というより、こんなにヒット要素のある曲をシングルカットしようとしなかったポールのセンスのなさが問われるべきですね(苦笑)。当初は『Band On The Run』もシングルカットしていませんから・・・。ポールもちょっとシングルとアルバムの差別化にこだわりすぎましたね。
シングルカットと同時期には、プロモ・ヴィデオも制作されています。・・・しかし、その出来がなんともおかしなものです。「これがスマッシュ・ヒット曲のプロモ・ヴィデオか!?」と思ってしまうことでしょう。というのも、はっきり言ってこのプロモ、手抜きなのです(笑)。制作にかける時間がなかったのか、凝ったものを作らなくても売れるという状況だからだったかは分かりませんが、いくらなんでもこれはなかろう!プロモの内容ですが、ほとんど中身がありません。なんと、歌に合わせて歌詞の書かれたスライドが映るだけなのですから。下手したら誰でも作れてしまうレベルです(苦笑)。歌詞は1単語ずつ書かれており、歌にぴったり合っています。そのため、早口の部分は単語が次々と切り替わってゆきます。その辺がまた笑えてしまいます。歌詞のない部分は、ポールとリンダの写真が登場しますが、なぜかモノクロ・・・。それしか内容のない、あまり見ても面白くないプロモであります。折角のヒット曲なのだから、演奏シーンも含めてもっとかっこいいものを作れたのでは?と思いますが・・・。ちなみに、現在このプロモはブートでのみ出回っていますが、なぜか音も映像も質が最悪で、なんだかものすごいことになっています(苦笑)。私も持っていますが・・・。イントロを聴いた時はその音の悪さに思わず笑ってしまいましたよ。公式プロモ集「The McCartney Years」には未収録です。まぁ、それも納得いきますね・・・。その噂のプロモは以下のような感じです。


そして、この曲について語る時に外せないのが、ライヴ・ヴァージョンでしょう!大ヒットアルバムからのスマッシュ・ヒットであり、内容的にも完璧であり、キャッチーかつロック色の濃いアップテンポの曲だけあって、ライヴ演奏にはうってつけであることは疑う余地がありません。当然ながら、ポールはこの曲をライヴで取り上げています。それも、発表後のほぼすべてのコンサート・ツアーで演奏しています!ウイングス時代からソロ時代まで、'70年代から現在に至るまで、ほぼ欠かさずセットリストに入れられている、まさにポールのライヴの定番曲なのです。さすが一世一代の名曲だけあります。元々ライヴ映えしますし。ちなみに、唯一この曲が演奏されなかったコンサート・ツアーがあります。言わずもが、1979年のウイングス全英ツアーです。これは極めて異常事態ですが、まぁあのツアーは『Jet』の代わりに『Getting Closer』を演奏するというマニアックぶりが魅力でして・・・(苦笑)。それを除けば皆勤賞。『Band On The Run』や『Live And Let Die』、『Maybe I'm Amazed』に並んで長い間演奏されています。この曲でポールのライヴを思い浮かべる方も多いことでしょう。
ライヴ・ヴァージョンのうち、CDとして公式発表されているのは1976年のウイングス全米ツアー(ライヴ盤「ウイングス・オーヴァー・アメリカ」収録)、1989年〜1990年の通称「ゲット・バック・ツアー」(ライヴ盤「ポール・マッカートニー・ライヴ!!(Tripping The Live Fantastic!)」収録)、2002年〜2003年ワールド・ツアー(「バック・イン・ザ・US」「バック・イン・ザ・ワールド」収録)の3種類です。1993年ワールド・ツアーの模様はライヴ盤未収録ですが、同ツアーのサウンドチェックの模様が「バンド・オン・ザ・ラン」の25周年記念盤に収録されています。それを含めると4種類。ウイングス、通称「ランピー・トラウザーズ」、そして現在のポールのツアー・バンドと、異なるラインアップでの演奏が楽しめるのは定番曲ならではでしょう。映像では、「The McCartney Years」に映画「ロック・ショー」(1976年全米ツアーの模様を収録)と、グラントンベリー・フェスティバル(2004年6月26日)の模様が収録されているので、ウイングス時代のポールと近年のポールが演奏するこの曲を簡単に比べることができます。1975年〜1976年のワールド・ツアーでは、『Venus And Mars/Rockshow』とのグランド・メドレーで演奏されました。映画「ロック・ショー」で感動された方も多いことでしょう。伝説の全米ツアーの幕開けにもなったメドレーの一翼を担いました。『Rock Show』からドラムソロを経てこの曲へなだれ込む箇所はいつ聴いても身を震わせます。なお、このライヴ・ヴァージョンは映画「ロック・ショー」の公開に合わせて日本でのみ1981年にシングル発売されているようですが・・・超レアらしいです。
共通しているのは、演奏がオリジナル以上にハードになっていることでしょう。ライヴを意識してのことか、それともスタジオ・ヴァージョンに迫力が不足していたからか・・・。特に、ギター・サウンドが大々的にフィーチャーされていてロック色を濃くしているのが違いです。オリジナルはちょっとしか入っていませんから、大きな違いです。それと、ドラムスは明らかにライヴの方がダイナミックです。まぁオリジナルは「ヘタウマ」ポールですから(苦笑)。スタジオ・ヴァージョンの素晴らしさは先述の通りですが、躍動感の上ではライヴにはかないません。ライヴ・ヴァージョンにもライヴならではのよさがあるのです。ウイングス時代は、ブラス・セクションは実際のブラス・セクション4人組が再現しています(ソロではキーボードとギターで再現)。そして、1993年までは間奏のムーグはもちろんリンダさんが演奏しています!また、ライヴではいくつかポールのお決まりがあります。1つは、間奏に入る際に入れる“She said”という掛け声。これは、スタジオ・ヴァージョンの2度目の間奏でのアドリブが元になっていますが、オリジナルよりはかなり大人しめです。続いて、後半の崩し歌いが“I thought the major〜”から“Don't you know that〜”に変更されている点。これもライヴでは今に至るまで変わらぬアレンジです。そしてもう1つ忘れてはいけないのは、「ジェット!」の掛け声でしょう!この箇所では、いつしか観客が掛け声と共に片手をこぶしにして突き上げるというのがお決まりとなっています。ポールも片手を挙げて観客に掛け声を促します。皆さんはこの曲といえばこのイメージが強いかもしれません。スタジオ・ヴァージョンを聴きながら思わずこぶしを挙げたことのある方もいらっしゃるのでは?(苦笑)


ライヴでのこの曲といえば、セットリスト中での位置にも注目です。皆さんもうお分かりですよね。この曲は、必ずコンサートの序盤で演奏されているのです。特になぜか2曲目〜4曲目に集中しているのです。オリジナル・アルバムで2曲目だったせいなのか分かりませんが・・・、コンサートの中盤・終盤での登場はまずありません。中でもオリジナルと同じく2曲目に演奏されることが多いです(1975年〜1976年ワールド・ツアー、1989年〜1990年「ゲット・バック・ツアー」、2002年〜2003年ワールド・ツアー、2009年全米ツアーなど)。その割にはなかなか1曲目に演奏されることはありません。1993年ワールド・ツアーでは4曲目、2005年全米ツアーでは3曲目。なかなか1曲目を飾らない「万年2曲目」の道を歩んでいたのですが・・・、2004年ヨーロッパ・ツアーで初めてオープニングを飾りその肩書きは終焉しました(笑)。最近でも、まれに1曲目に演奏することがありますが、基本は2曲目です。冒頭で目立つこともなく、あえて2曲目以降に位置し、観客のボルテージを上げるためにこの曲は日々投入されているわけです。いまやライヴで演奏され続ける数少ないウイングス・ナンバー(というのが非常に悲しいのですが・・・)。これからもきっと定番曲として演奏され続けることでしょう。それほど、ポールのライヴには欠かせない1曲です。いつかアンコールで演奏される日は来るのか?(苦笑)
最後に、マニアックなアウトテイクの話をしたいのですが、実はこの曲のアウトテイクはライヴ音源やサウンドチェックを除いては見つかっていません(汗)。というのも、「バンド・オン・ザ・ラン」セッション自体アウトテイクがほとんど発見されていないのです。ブートでも聴けません。この曲のみナイジェリアではなくロンドン録音なので、何か残っていそうな気もしますが・・・。強いてアウトテイクを挙げるなら、1974年に行われたウイングスのリハーサル・セッション「One Hand Clapping」の音源でしょうか。この曲のライヴ・ヴァージョン(スタジオ・ライヴですが)では一番早いもので興味深いです。ドラムスがジェフ・ブリトンというのも超レアです。
私にとっては、初めて聴いたポールのアルバムが「バンド・オン・ザ・ラン」だったため、この曲は2曲目に聴いたポールのソロ時代の曲になります。前曲『Band On The Run』がすごくキャッチーだったので、続いてキャッチーな曲が登場したのに満足していました。当時私が抱いていたポールのソロへのイメージは「キャッチー」一色でしたから・・・。結局その後3曲目(言わずもが『Bluebird』)以降のゆったりした展開に落胆してしまったのですが(笑)。その次に買ったアルバムが「オール・ザ・ベスト」英国盤だったのですが、そのためポールのソロを聴き始めた当初からこの曲はたくさん聴いていました。「オール・ザ・ベスト」英国盤では『Band On The Run』と順序がひっくり返って万年2曲目が見事オープニングを飾っていてちょっと違和感を感じますが(苦笑)。米国盤の順当な流れの方がすっきりする私です。蛇足ですが、「オール・ザ・ベスト」のこの曲のイラストが、紙飛行機になっているのが何気にお気に入り(タイトルの紙飛行機への織り交ぜ方が技巧的で好き)。ポールのソロキャリア、ウイングスでもベタな曲ですが、今でも結構お気に入りですね。どちらかといえば『Band On The Run』の方が好きですが(おい)。スタジオ・ヴァージョンは人が言うほど悪くないと思っています、ポールのヘタウマドラムス含めて。ヴォーカルと緊張感はスタジオ・ヴァージョンが最高だと思います。ライヴでもすっかりおなじみですが、まだ生ポールを拝んだことのない私にとってこの曲すら未体験であり・・・(汗)。いつかポールに目の前で歌ってもらいながら「ジェット!」とこぶしを挙げたいですね。既にウイングスのコピーバンドさんの演奏では何度もこぶしを挙げているんですがね(苦笑)。
この曲を聴かずしてポールのソロキャリアやウイングスは語れません!百聞は一見にしかず!ポールのロックの傑作です。ベスト盤には必ず収録されているので、それで聴くのもよし、名盤「バンド・オン・ザ・ラン」で聴くのもよし。あと、数々のオムニバス盤にも収録されています。最近では「ロック・スピリッツ」というアルバムに収録されていましたね、確か。

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「実験的ナンバー」。またマニアック指向に戻りますので(苦笑)、お楽しみに!
(2009.9.01 加筆修正)



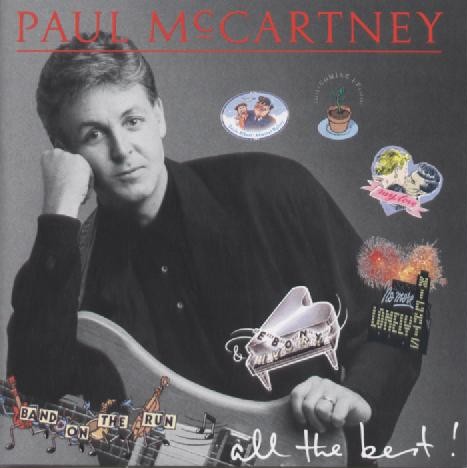
(左から)当時のシングル盤(日本)。/アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」。タイトル曲とこの曲をはじめ完成度の高い起死回生の名盤!初心者にお勧め。
ライヴ盤「ウイングス・オーヴァー・アメリカ」。ウイングス時代のライヴはこちらで!/ベスト盤「オール・ザ・ベスト」。ポールのソロ入門にお勧め。もちろん米国版!(笑)