
Jooju Boobu 第60回
(2005.10.03更新)
Ballroom Dancing(1982年)

1日遅れの更新となりまして申し訳ございませんでした。通算60回目となる今回の「Jooju Boobu」は、ポールの名盤との呼び声が高いソロ・アルバム「タッグ・オブ・ウォー」(1982年)の収録曲『Ballroom Dancing』を語ります。'80年代になりソロ活動に戻ったポールが世に送り出した、'70年代(ウイングス時代)とは一線を画した落ち着き払った曲調とシリアスな詞作が多い内容で話題となった「タッグ・オブ・ウォー」ですが、そんなアルバムの中でもこの曲は突飛出て明るく華々しく、目を引きます。シングルにこそなりませんでしたが、多くの名曲を抱える「タッグ・オブ・ウォー」の中でも負けず劣らずの個性を発揮し、人気曲として親しまれているこの曲の魅力を、今回は語ってゆきます。
アルバム「タッグ・オブ・ウォー」は、ポールの諸作品でも改めて説明不要な程有名な1枚ですが、今一度おさらいしておきましょう。'80年代が始まってまもなく制作が開始されたこのアルバムは、ポールにとってはまさに激動の時代の中で生まれました。そもそも、「タッグ・オブ・ウォー」は当初ウイングスの新作としてレコーディングが計画されていたものでした。1980年初頭のポールの日本での逮捕事件で活動が停滞していたウイングスの復帰作が、これになる予定だったのですが・・・。ウイングスで他のメンバーと共にリハーサルを行い正式なレコーディングへの準備をしていたものの、結局はポールの意向で自らのソロに切り替えて発表することとなりました。その契機となったのが、年末にNYで無二の親友であるジョン・レノンが射殺された例の事件なのは言うまでもありません。事件にショックを受けたポールは、しばらくアルバム制作を停止。そして、活動再開にあたって正式にソロとしてレコーディングすることとしたのです。翌1981年からはソロとしてアルバム制作が続けられますが、この間にウイングスのオリジナル・メンバー、デニー・レインがグループ脱退を表明、ウイングスは自然消滅します。こうしたことで「タッグ・オブ・ウォー」は、ウイングス解散後再びソロに戻ったポールの新たな「出発点」となる1枚となりました。数年前から「グループとしてやることがマンネリ化している」と感じ始めていたポールを、ジョンの死やデニーの脱退事件がくしくもソロに引き戻すこととなったのでした。
ポールが、アルバム制作をソロに移行するにあたって、プロデューサーにビートルズ時代の「恩師」であるジョージ・マーティンを迎えたのは有名な話ですね。そして、そのマーティンのアドバイスによりポールは、収録曲各曲ごとに的確なミュージシャンを選択し、さらにポールよりも上を行く大物ゲストを多くセッションに招待しました。スティービー・ワンダー、リンゴ・スター、カール・パーキンスなどなど・・・。こうした新体制による一連のセッションを通じて生まれた膨大な曲から、ポールとマーティンの判断で12曲を厳選して発表したのが、さらに1年経った1982年に世に出た「タッグ・オブ・ウォー」でした。ポールにとって約1年半ぶりの新譜となったアルバムは、ジョンの死やポール自身の成長を通じてウイングスから脱皮し「大人」になったかのような洗練されたメロディや穏やかな曲調、ビートルズを想起させる「ビートリー」なアレンジと、社会問題を鋭く歌い上げた詞作が受け大ヒット。英米はもちろん日本でも1位を記録するほどの売れ行きでした。楽曲も、『Ebony And Ivory』をはじめ『Take It Away』『Here Today』『Wanderlust』とファンの間で「名曲」として親しまれているものが目白押し。今でも「名盤」として愛され続ける作品となりました。
今回紹介する『Ballroom Dancing』も、こうした紆余曲折を経て完成したアルバムのたどった経緯に沿って出来上がりました。この曲が最初に録音されたのは1980年夏のこと。ポールがパークゲート・スタジオで録音したデモが残されています。これは、いきなりマニアックですが(苦笑)「タッグ・オブ・ウォー」関連のブートで聴くことができます(「Rude Studio Demos」「Tug Of War & Pipes Of Peace Sessions」など)。ブートを聴けばお分かりですが、この時点で姉妹作にして次作の「パイプス・オブ・ピース」収録曲含め多くの楽曲が存在し、その原形を見ているのに驚きです。この曲のデモも、既に全体のアイデアが固まっていることをうかがわせて興味深いです。詳しくはこれから随所でお話しますが、ピアノ中心の演奏や1オクターブ上がるサビのヴォーカルなど・・・。すべてこの時点で登場します。ちなみに、このデモはポールの単独録音であり、ピアノ・ベース・ドラムスに加えヴォーカルとコーラスもポール1人でこなしています。さすが!また、この年の秋にはウイングスのリハーサルでも演奏されています。これは「タッグ・オブ・ウォー」が元々ウイングスの新譜になる予定だったことを裏付けています(他にも『Keep Under Cover』『Average Person』などが録音されている)。こちらは「When It Rains,It Pours」などのブートに収録されていますが、面白いのはウイングスだけにタイトなバンドサウンドになっている点でしょう。ピアノが入っていなく、エレキギター中心にぐいぐい迫ってくるストレートな演奏は往時のウイングスナンバーをほうふつさせるようなバリバリのロックそのものです。これが、ウイングスのラストアルバムとなった「バック・トゥ・ジ・エッグ」に入っていてもおかしくないくらいです!公式テイクからはちょっと想像がつかないでしょう。この姿で世に出ていたらこの曲への印象も評価もがらっと変わっていたと思われますが、ウイングス・ヴァージョンはボツとなり、結局は前者のポール単独デモを基にしたアレンジが採用されるに至りました。そして、ジョンの死を挟んでアルバムをポールのソロ作品に切り替えた後、1981年春に改めてレコーディングし直して完成させています。「タッグ・オブ・ウォー」の多くの楽曲に言えるのですが、まさにウイングスからソロへポールが移行する時期の1曲なのです。


この曲は、先程「バリバリのロック」と言いましたが、その通り大雑把な分類をすればロックに含まれる曲です。しかし、同じロックでも、この曲はウイングス時代の諸ロックナンバーとは違うニュアンスを感じることでしょう。それはなぜか・・・と言えば、この曲では'50年代や'60年代をほうふつさせるようなオールド・スタイルが取り入れられているからです。過去のポールの曲でいえば『I Saw Her Standing There』に近いと言えば分かりやすいでしょうか。初期ビートルズや、さらにそれ以前のチャック・ベリーやリトル・リチャードの頃のダンスナンバーの雰囲気・・・「ロック」と言うより、「ロックンロール」という言葉の方がぴったりな、昔懐かしい響きを覚える仕上がりなのです。ポールは、この曲を'50年代に放送されていたダンスのコンテスト番組「Come Dancing」にインスパイアされて書いたと語っていますが、まさにそんな時代にぴったりなロック・スタイルなのです。ブギウギのリズムがちょっと入っているのが要因でしょうか?極めてシンプルなコード進行もこのイメージに寄与しています。このオールド・スタイルは先述のポール単独デモのアレンジを引き継いでいて、ウイングスのリハーサルではアレンジを変更されたものの逆転で見事復帰した形となっています。(だから、ストレートなロック・アレンジになっているウイングスのリハーサル・ヴァージョンはすごく異様に聴こえるのですが・・・)
実は興味深いことに、'70年代・・・つまりウイングス時代のポールは、この曲のようなオールド・スタイルのロックンロールをほとんどと言っていいほど発表していません。ビートルズ解散後のポールが手がけたロックは、ブルースに影響を受けたものからグラムロックに影響を受けたものに変化し、やがて絶頂期のストレートなアメリカンロックや、時代の先端を行くパンクやニューウェーブ、テクノなどをうまく取り入れた斬新なものが主流になってゆきましたが、こうした変化の中でオールド・スタイルの曲はなくなってゆきました。これはウイングスを率いて常に時代に追いつかんと励んだポールの意気込みあってのことですが、その結果ポールにとってアイドルにあたるロック・アーティストをほうふつさせる曲は聴かれなくなってしまったのです。しかし、'80年代に入り、ウイングスが活動休止した中で生まれたこの曲で、ここに来て初めて昔懐かしいオールド・スタイルのロックンロールが戻ってきたのです。これにはいろいろ理由が考えられそうですが、活動開始から10年近くが経過してマンネリ化してきたウイングスの活動からふと離れて(「マッカートニーII」のように)自らの原点を振り返ったことも要因と思われますし、ジョン・レノンとの和解が急速に進展を見せ始めビートルズを思い起こすことが多くなったことも一因でしょう。さらにはそのジョンの死によって否応にも昔のことを振り返らざるを得なくなったことも少なからず関わっているのかもしれません。あくまで推測ですが、'80年を前後してポールの心境に生じたいろいろな変化が、ポールに過去の作風や思い出を呼び戻し、懐古的な曲を書かせたのでしょう。それを証明するかのように、'80年代以降のポールは『Move Over Busker』『Get Out Of My Way』や『Flaming Pie』『That Was Me』といったオールド・スタイルのロックナンバーを積極的に手がけていますし、そこから進展させて『My Brave Face』のようなビートルズ回帰的な曲を多く書くようになっています(むろんそれだけではないですが・・・)。'80年代以降のポールがウイングスから一転してビートルズ推進派になったことは言うまでもありません。こうした傾向にジョンの死が大きく作用したことは否めないでしょうが、その先鞭としてこの曲があると考えるとなかなか興味深いと思いませんか?
そして、それは詞作でも裏付けられます。先程、この曲のできるきっかけがダンスのコンテスト番組「Come Dancing」だと触れましたが、それは曲のタイトル『Ballroom Dancing』にしっかりと表れています。「ボールルーム・ダンシング」とは舞踏室でのダンス、つまり「社交ダンス」のことです。歌詞では、この社交ダンスを通じて子供たちの青春が歌われていますが、ポールいわくこれは「子供の頃の思い出」だそうです。つまり、ここで歌われているのはポール自身の青春時代の思い出であり、曲調と同様に歌詞でも自らの過去を振り返っているのです。幼い頃に見た夢の思い出や、友達と喧嘩をしながらもボールルームでのダンスに憧れる子供たちの様子は、ポールの幼い頃の体験そのものを表しているのでしょう。ポールは、インタビューでこの曲について実に詳しく歌詞の背景を説明していますが、それほど自らの青春に思いをはせて書いたのでしょうね。ちなみに、ポールによれば「ボールルームに行く目的は女の子を見つけること。今で言うディスコみたいなもんだね」とのこと。青春ですね(笑)。そして、その思い出の風景の中には、当然ジョンやジョージ・ハリスンもいたことでしょう。実際ポールは、同じ学校の友だったジョージと一緒にダンス・パーティーに足を運んでいたそうで、そんな思い出も語っています。そう、この曲で取り上げられている思い出は、ビートルズとも無関係ではないのです。もしかしたら、'80年頃のポールはジョンと和解し再び仲がよくなるにつれ、こうした昔の出来事を肯定的に捉えられるようになったのかもしれませんね。ウイングス時代には「幻想」として必死にもみ消そうとしていた過去を、封印から解いて名誉挽回させる最初の一歩がこの曲だったのかもしれません。そう考えると、この曲を作り出した矢先にジョンが死んでしまうとは悲痛きわまりありません・・・。
歌詞についてはポールが詳述していますが、歌が進むにつれて子供たちが大人になってゆく展開となっています。第1節は、「本当に幼い頃の遊び」を歌っています。“Sailing down the Nile in a china cup(磁器のコップに乗ってナイル川を下る遊びをしてさ)”というくだりは、ポールによれば子供にとっての夢とのこと。「チャイナ」「ナイル」という響きが幼少のポールには憧れだったようです。第2節では、「少し成長してからの遊び」が歌われています。「空飛ぶじゅうたん」や「デイヴィ・クロケット」(アメリカの開拓時代のヒーローの名前)が登場しますが、まだまだ幼い頃の思い出といった趣です。そして、ミドルの部分では「いつもいいことばかりではなかった」と歌われますが、これもポールが強調しておきたかった箇所だそうです。つまり、いつも仲良く遊んでいたわけでなく、喧嘩もいっぱいしたということです。自分自身の思い出だけあって、ちゃんと心配りがされた歌詞ですね。そして、喧嘩しても最後はボールルームで仲直りし、TVで見たダンスに憧れる・・・と締めくくります。なんだかんだあってもダンス・パーティーが青春の舞台ということですね。「Big B.D.(偉大なるボールルーム・ダンシング)」とまで言われています。間奏を挟み第3節では一転して大人になった様子が歌われますが、ここでは“And I wouldn't want to knock it(思い出を消し去りたくない)”という一節が出てきます。大人になっても、青春時代の純粋な思い出を忘れたくない、汚したくない・・・というポールの思いが込められてます。「タッグ・オブ・ウォー」は、歌詞で様々な二元的対立を取り上げ、問題提起したアルバムとして知られていますが、この曲で歌われている「子供の頃の思い出」と「大人になった現在の自分」というのも、ある種二元的対立と言ってもいいのではないでしょうか。そこまで考えるのは深読みのしすぎですか・・・?


もちろんポールにとって昔の思い出は素直に振り返ることのできる楽しい思い出なのですから、当然曲調も歌詞も明るいものとなります。その結果、この曲の明るさや華やかさはこの曲を「タッグ・オブ・ウォー」随一に目立つ存在にのし上げています。ジョンの死やウイングスの解散の影響でアルバムの大半の楽曲の作風が穏やかでシリアスな空気を携えているのに反して、やたらと輝いています。アナログ盤ではB面の冒頭なのですが、この位置がうってつけの1曲です。前曲の『Here Today』で感じられる一抹の寂しさと比べればその差は一目瞭然です。まぁ、こうなってしまったのも、「タッグ・オブ・ウォー」セッションで録音された曲のうち明るい曲調のものをほとんど次作「パイプス・オブ・ピース」に送ってしまったことが一因なのですが・・・。次作回しにされた理由は「アルバムの雰囲気に合わないから」だそうですが、一見アルバムの雰囲気に合いそうにもないほど賑やかなこの曲が、シリアスムード全開の『Keep Under Cover』さえも跳ね除けてアルバム入りしているのが面白いです。ほどよいスパイスということなのでしょうか・・・?いずれにしても、この曲が非常に存在感を示すことのできる配置となりました。きっとポールが相当思い入れを持っているんでしょうね、この曲に。そうとしか言いようがありません。ポールにとっては、この曲に込められた青春時代の思い出への思い入れはとても深いものだということが分かります。
さて、「タッグ・オブ・ウォー」で発表されたヴァージョンは、驚くべきことにほとんどの楽器をポールが演奏しています。演奏を聴いているだけではそう思わせないのでちょっと意外な事実ですが、ベースはもちろん、ギターやピアノ、そしてドラムスまでも演奏していてまさに「マルチ・プレイヤー」ぶりを発揮しています!「タッグ・オブ・ウォー」セッションでは周知の通り、曲に合わせていろんな演奏者を招待し、その道のプロによる息の合った演奏が聴けるのが醍醐味なわけですが、リンゴ・スターやデイヴ・マタックスといった敏腕ドラマーを呼んでいるのにもかかわらず、なぜかこの曲では彼らに頼まずポール自らドラムをたたいています。理由は不明ですが、どうせ集めたのならプロに演奏してもらえばよかったのでは・・・。この曲でのポールのドラミングは、なかなかタイトで乾いた音ではあるのですが、少しだらだらした感が否めません(汗)。もうちょっとメリハリがあればいいと思うのですが・・・。ほとんどポールの演奏でできてしまっているためか、いまいち演奏の評価が高くない「タッグ・オブ・ウォー」ヴァージョンです(汗)。しかし、マーティン先生のプロデュースにより長い月日をかけてアレンジし、ミックスしたおかげか、完成度は高く、他の曲と比べても遜色しない出来となっています。
サウンドの中心はピアノと言えるでしょう。全編に入っており、華やかなサウンドを作り出す重要な材料となっています。高音中心で、ホンキートンクのようにガチャガチャしたような音を出しているのが'50年代の雰囲気たっぷりです。きっとポールも古きよき昔を思い描いてこういう音にしたのでしょう。特に目立つ演奏はないですが、これだけでオールド・スタイル気分になれます。ピアノに続いて重要な役回りがエレキ・ギターで、これにはポールの他にウイングスのデニー・レインが参加しています。デニーの参加は前述した制作経緯と無関係ではないでしょう。事実、同時期録音の多くの曲にもデニーが参加しています。とはいえ、ウイングスに比べると遥かに存在が目立たなくなっているのはポールのソロだからでしょうか。「ウイングス」という看板を取ればデニーという人は元々地味ですからね・・・(汗)。そして、もう1つ忘れてはいけないのがブラス・セクション。これが'50年代のダンスナンバーの雰囲気を出しているもう1つの材料です。間奏から入り、一気に曲を賑やかにします。このブラスが入っていることで、初期ビートルズというよりはそれ以前のオールディーズの雰囲気が強くなっている感があります(この辺が『Move Over Busker』との違いでしょうか)。第3節のサビでは、それ以前にはなかったブラスが絡み合い大きく盛り上がります。間奏では、ブラス・セクションとクラリネット・ソロが交互に出る格好となっていてこれも印象的なアレンジですが、クラリネットはジャック・ブライマーの演奏です(この人、英国では有名らしい・・・)。間奏では、さらにエレキ・ギターとパーカッションが絡み合うハードなパートがあり、この部分は唯一「ロック」な瞬間でしょう。ここで、ポールのうなり声(?)がブラスに変わってゆく編集はお見事です。結構凝っていますね。エンディングはブラスを交えて華やかなまま、スパッと終わります。実に爽快ですね!
ポールのヴォーカルも、'50〜'60年代を意識したスタイルで、少し太い声を出しています。エルビス・プレスリーとまではいきませんが、往年のアイドルを念頭に置いているのかもしれません。聴き所は、第2節からサビを1オクターブ上のラインで歌っている点でしょう!これが痛快なアレンジです。出だしは大人しめにしておきながら、中盤からタイトルコールをシャウトするのですから!太い声から一転、高音で声を張り上げるのはロックンロールのスターといった趣ですね。印象もここで一気にぱっと明るくなります。途中から1オクターブ上のラインで歌うというパターンは結構ポールの曲に散見されますが、この曲でもとても効果的に決まっています。ほとんどのヴォーカルがポールによるものですが、コーラスに愛妻リンダと、「タッグ・オブ・ウォー」以降'80年代ポールに欠かせない存在となるエリック・スチュワートが参加しています(“Big B.D.”の部分)。エリックの参加は、ここから徐々に増えてゆきます。一方それまでリンダとコーラス隊を組んでいたデニーがその位置から外れています(汗)。これもウイングス→ソロという流れの中での(デニー・ファンにしてみれば)どこか寂しい出来事ですね・・・。そして、間奏に移る際に入るDJ風のナレーションはピーター・マーシャル。なんでも現役アナウンサーらしいですが、まくし立てるような話し方が曲に勢いをつけるようで効果的です。個人的には好きな演出ですね。チャー、チャー、チャー!って(笑)。
「タッグ・オブ・ウォー」の中で発表されたこの曲ですが、実は当初シングルカットされる予定でした。全体的に穏やかな作風のアルバム中随一の華やかさを持ち、キャッチーな内容は確かにシングル向きと言えるでしょう。全英&全米No.1ヒットの『Ebony And Ivory』、全米10位の『Take It Away』に続く第3弾シングルとして発売される・・・はずだったのですが、結局その座はタイトルナンバー『Tug Of War』に譲っています。結局このシングルは全英&全米53位という低調に終わってしまったわけですが、よりアップテンポなこの曲だったらもうちょっとましな結果は出せたのではないか・・・と思います。
しかし、これでこの曲の成長が止まってしまったわけではありません。発表から2年後の1984年、ポールが主演・脚本・音楽を手がけた自主制作映画「ヤァ!ブロード・ストリート」で見事再演されたのです。この劇場用映画に使用された曲は、ポール主演ということですべてポールの楽曲で占められており、わずかな新曲を除けば過去に発表した楽曲が選ばれ再演されたのは周知の通りですが、ポールの(当時はまだ短い)ソロキャリアからは『Wanderlust』と『So Bad』、そしてこの曲の3曲が選ばれ、ポールのソロ活動に対する自信がうかがえます。珠玉の名曲揃いの「タッグ・オブ・ウォー」から選抜されたことは、ポールのお気に入りの程を思わせます。映画で使用された曲の多くは、ポールがいわゆる「口パク」を嫌ったため、実際の映画のシーン撮影時にライヴ録音されたものがそのまま使用され、同名サントラにもその時の音源が収録されていますが、この曲も映画の撮影時の音源がサントラでも使用されています(ただし、サントラに収録されたものはかなり編集が加えられて短くなっている)。


映画でのこの曲の登場シーン、つまりこの曲の再演に参加したミュージシャンは、なんとも豪華な顔ぶれです!ギターにデイヴ・エドモンズとクリス・スペディング、ベースにジョン・ポール・ジョーンズ(レッド・ツェッペリン)、そしてドラムスには・・・元ビートルズのリンゴ・スターが!これにピアノを演奏するポール&リンダと、8人のブラス・セクションを加えた、映画のためのスペシャル・バンドでの演奏となりました。もちろん全員映画の演奏シーンにも登場します。さりげなくポールとリンゴの共演がこの曲でも果たされていることに注目したい所。この再演は、豪華メンバー集結はもちろんのこと、映画撮影と同時進行でライヴ録音されているだけあって、ほぼポールの一人芝居であったスタジオ・ヴァージョンに比べ格段とロックしているのが魅力的です。そうそうたる顔ぶれによる、ライヴ感あふれる生き生きとしたバンドサウンドに仕上がっています。ドラムス1つ取っても、躍動感が全く違います(スタジオ・ヴァージョンもリンゴにすればよかったのに!)。スタジオ・ヴァージョンでは「そこそこ」ロックしていた間奏も、よりイメージを広げた長いものに生まれ変わり、デイヴ&クリスによるハードなギターソロが繰り広げられます。パーカッションもこっちの方が多彩に入って緊張感を出しています。ポールの弾くピアノや、ブラス・セクションも生演奏だけあってアドリブを交えながらの賑やかさを増したものになっています。さらに華やかさを増したエンディングもさらに爽快です。ポールのヴォーカルは、スタジオ・ヴァージョンのような太い声ではなくなっていますが、溌剌さがよく出たスタイルとなっていて、軽快さはこちらの方が表れているでしょう。それで第2節以降の1オクターブ上のヴォーカル&シャウトはそのまま聴かせるのですから!新たな歌い回し“1 and 2 and 3 and 4”がいい感じですね(笑)。迫力で言えば明らかにこの再演の方が上であり、それゆえにファンの間でもこちらのヴァージョンの方がお気に入りという人も多いです。
また、この再演ヴァージョンは第3節の後にもう1度間奏があり、その後映画のために新たに書き下ろされた第4節が登場します。この第4節の歌詞は基本的に他の部分と同じ内容で、子供たちが大人になってからの様子が歌われますが、ちょっと無理しているかな・・・という感があります(汗)。いくら韻を踏むからといって、唐突に「ロケット」が出てくるのはさすがに違和感を覚えますね・・・(いかがでしょう?)。なお、サントラでは収録時間の都合上、1度目の間奏の途中から2度目の間奏に飛ぶよう途中の第3節がカットされており、本来の第4節が第3節に来るように編集されています。そのため、よく「第3節を丸ごと書き換えた」という誤った説明がされることがありますが、本当はこの通りですのでご注意ください。映画ではスタジオ・ヴァージョン以上に長く演奏を楽しめ、その点もお得です。
映画「ヤァ!ブロード・ストリート」は、脚本家としてのポールの力量のなさと、ストーリーの他愛なさが災いして興業的に大失敗に終わったことは有名な話ですが(汗)、この曲の演奏シーンも「なんだかなぁ・・・」といった感じが否めません(笑)。実は、この曲のシーンが映画中最も費用が掛かったそうで、あのスティーブン・スピルバーグ監督もセットを見学しに来たそうな・・・。この曲は、映画中盤でポールがダンスホールを控えた舞台でミュージカルのシーンの撮影に臨む場面で歌われます(リハーサルという設定のようですが)。演奏前に、子供たちにポールがピアノを弾いて曲を教えている様子が登場するのがちょっと興味深いです。演奏はポールの勢いよいカウントで始まり、最初のうちはポールはカメラの載ったクレーンからハンドマイク片手に歌います。舞台では子供たちが歌詞の内容に合わせた劇をしています。磁器のコップに乗ったり魔法のじゅうたんに乗ったりと楽しそうです。ポールも子供たちに掛け声をかけます(これはそのままサントラにも収録されている)。第2節のサビになると舞台が反転し、それまで影で演奏してきたリンゴたちスペシャル・バンドの面々が登場します。これと同時にポールは舞台に上がりリンダと向き合ってピアノを演奏。ビートルズ・ファンからすればポールとリンゴが同じステージで演奏しているのがうれしい見所でしょうか。さらにダンスホールでは正装をまとった紳士淑女の、まさに「ボールルーム・ダンシング」が始まります。華麗な間奏の雰囲気にぴったりなダンスが登場し、楽しいミュージカルが続く・・・はずだったのですが。
ここで突如、不良風の若者カップルがホールに乱入。困惑するダンサーたちを脇目に好き勝手に踊り出すのはまだいいものの、喧嘩まで始めてしまうのですから驚きです。和気あいあいとした雰囲気はどこへ?いつの間にか大勢集まってきた若者はどこから沸いてきたんだ・・・?第3節が始まると、いったんは紳士淑女の巻き返しにより不良どもを追い払って演奏&ダンスが続けられほっと一安心・・・なのですが。これまた2度目の間奏でさっきのカップルが帰ってきます。しかも今度は喧嘩がエスカレートしてナイフまで取り出す一触即発の事態に。刃傷沙汰には至らなかったものの、今度は紳士淑女を怒らせる羽目になってしまい、小競り合いがあちこちで起こります。ずっと様子を見ていた大人の観客たちもつまらなそうです(苦笑)。そして演奏も終盤に差し掛かると小競り合いはポールたち演奏者のいるステージまでも巻き込む大乱闘に変貌。淑女たちは混乱のうちに逃げ惑い転倒し、若者はステージで踊り狂い、至る所で殴り合いが発生、さすがのポールも驚きの顔を隠せません(なんとなく涙目になっている?)。演奏が終わる頃にはステージも崩壊してしまいます(汗)。前半の楽しい雰囲気はどこの空といった感じの結末に、ポールも我々も呆れるばかりです。ポールも演奏後には“Lunch”とたった一言(これもサントラに入っている)。それにしても、ホールが混乱の様相を見せているのに最後まで黙々と演奏を続けるポールたちもすごいですね!最後のステージ崩壊で思いきり幕をかぶってしまったリンゴがちょっと哀れですが(でもなんだか面白い)。エンディング付近で、ステージに乱入した男性をリンダがパンチで撃退しているのには笑ってしまいましたが(笑)、あれはどう見ても不良には見えないんですが・・・?(あまりにもの混乱ぶりにリンダも混乱したか?)
それにしても、このシーンに関して疑問なのは、途中から乱入してきた不良たちは「演技」で乱闘していたのか?それとも本当に「乱入」だったのか?という点です。前者は、ミュージカルの撮影ということと、演奏後に不良の1人がさっきまで争っていた紳士を親しそうに抱き起こしている点で考えられるのですが、後者も、ダンサーたちや演奏者たちの顔に本当に驚いたり怒ったりしている表情が見受けられるので否定しがたいですし・・・。皆さんはどうお考えでしょう?まぁ、どっちみち結末が「夢」だからあいまいなのでしょうね(笑)。こんな風にストーリーは「何やってんだ・・・」と言いたくなるくらいハチャメチャなのですが(汗)、演奏シーンはさすが素晴らしい面子だけあって見せてくれます。この映画の唯一の取り柄であるんですけどね・・・。この曲では演技中心で演奏シーンはあまり映っていないのですが、やはり混乱の中黙々と演奏しているのが見所でしょうか(苦笑)。
ちなみに、この再演ヴァージョンは『No More Lonely Nights』に続くサントラからの第2弾シングルとして1985年にシングルカットされる予定でした(B面は『Wanderlust』の再演ヴァージョン)。しかし、ここでもシングルの話は流れてしまいます。代替のシングル発売はなし。これは、肝心の映画が大失敗を喫したのが要因であることは言うまでもないですが・・・(汗)。こうして、スタジオ・ヴァージョンに続き再演ヴァージョンもシングル発売はならず、とてもツいていない運命を歩む曲となってしまいました。
この曲について非常にもったいないことがあります。それは、ポールが1度もこの曲をライヴで演奏したことがないことです。ノリノリのロックンロールで、ライヴで演奏したらまず間違いなく盛り上がるであろう曲なのに・・・。発売当時のポールがスタジオ活動に専念しライヴを行っていなかったことも一因ですが、それでも映画で再演したのにもかかわらず全く取り上げていないのは不思議です。ポールがライヴ活動に復帰した'89年以降の一連のセットリストの傾向に、「ウイングスの曲」「'80年代ソロ時代の曲」を演奏しないことが挙げられますが、これは非常にもったいないことだと思います。特にこの曲に関しては、ひいき目なしでもライヴで演奏してほしいナンバーです。もちろん、それを願うファンは私の他にも多いことでしょう。ポールはビートルズナンバーばかりに目が行って、非常にもったいないことをしていると思います。時にはビートルズナンバーでなく、この曲で盛り上がるというのもありだと思いませんか・・・?
私は、アルバム「タッグ・オブ・ウォー」自体結構好きなのですが、この曲はその中でも上位に入ります。個人的には全体的にはスタジオ・ヴァージョンの方が好きですが、ライヴ感ある映画ヴァージョンも捨てがたいですね。ドラムスに限っては映画ヴァージョンの方が断然好きです!ポールの一人芝居はちょっと盛り上がりに欠けて・・・(汗)。でも、間奏前のナレーションが入っていたり、エンディングのアレンジなんかはスタジオ・ヴァージョンがお気に入りですね。この曲はなんといっても飛び切り明るい曲調が楽しいですよね。オールド・スタイルのロックンロールは意外とウイングス時代にはなかったパターンですが、この曲以降書かれているこのスタイルの曲では一番出来がよい気がします。映画は、あらまぁ・・・といった感じですが(苦笑)、演奏シーンと半ライヴ音源が生まれただけ大きな収穫でしょう!リンダが意外とお強いことも分かります(笑)。ウイングスでのリハーサル・ヴァージョンは、かなり雰囲気が違うので驚きです。しかし、これまた実にかっこよくて奥深いです。
この曲は、同アルバムの『Here Today』『Wanderlust』共々なぜかベスト盤に収録されていないのですが、ポールのロックンロールとしては「名曲」と呼んでも過言ではない曲です。ちょうど収録アルバムが名盤「タッグ・オブ・ウォー」なので、ぜひ一度聴いてみてください!映画ヴァージョンもお勧めです。そして、ポールが元気なうちにこの曲がいつかライヴで演奏されることを一緒に願いましょう!

さて、次回紹介する曲のヒントですが・・・「ロカビリー」。お楽しみに!!
(2009.5.17 加筆修正)
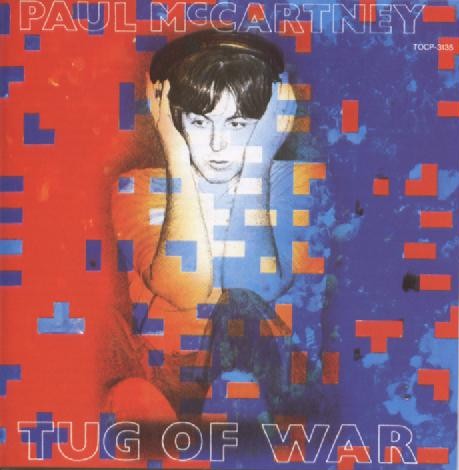
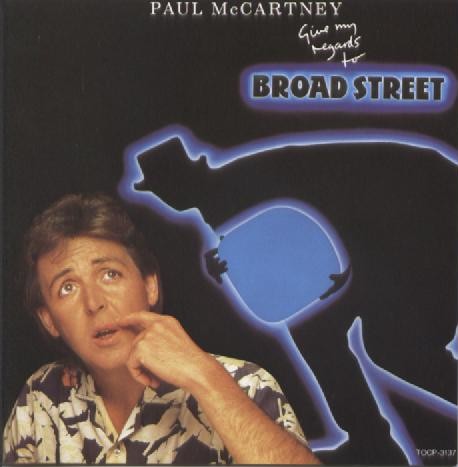
(左から)アルバム「タッグ・オブ・ウォー」。上質なメロディ、アレンジ、詞作が大人の風格を見せる、ポールの諸作品でも名盤のひとつ。
ポールの映画「ヤァ!ブロード・ストリート」のサントラ盤。この曲はリメイクの方が出来映えがよいかも。