
Jooju Boobu 第11回
(2005.4.14更新)
My Brave Face(1989年)

今回の「Jooju Boobu」は、ポールが「復活」を遂げたことでファンの記憶に残る1989年の名盤「フラワーズ・イン・ザ・ダート」より、アルバムのファースト・ナンバー『My Brave Face』を語ります。言うまでもなく先行シングルとしても発売され(B面は『Flying To My Home』)、英国で18位、米国で25位。英米では『Once Upon A Long Ago』以来のポール久々の新譜だけあって注目を集めたものの、過去のヒット曲ほど上昇できなかったのは、時代の流れによる「ヒット曲」の性質が変化してしまったことも指摘されますが、上位にこそならなかったものの、この曲はポールはまだ健在だ!と世界中に示すには十分でした。その後、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」が英国で1位を獲得するなど、ポールにとって久々のヒット作となったことは周知の通り。'80年代の低迷期を抜け出して、再び世界の表舞台に躍り出たポールの勢いを感じさせる、まさに象徴的なこの曲を取り上げたいと思います。ファンならご存知の話ですが、エルビス・コステロとの共作でもありこちらも注目を集めましたが、その辺も触れていこうと思います。
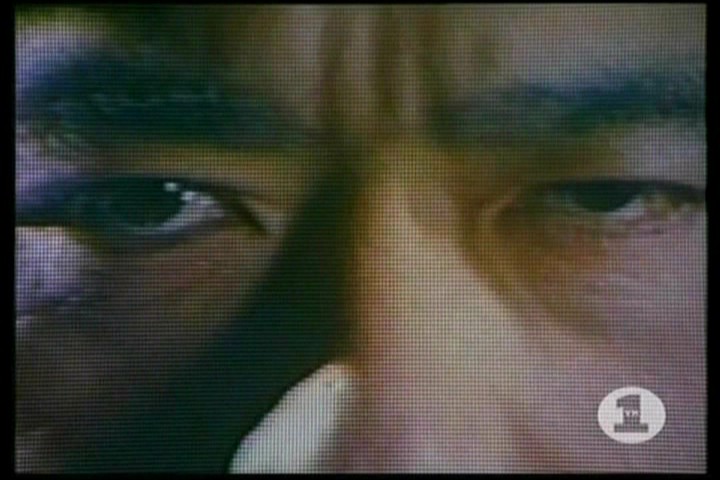
この謎の男の正体は、このページを読めば判明する!?(笑)
まずは、「フラワーズ・イン・ザ・ダート」で再び成功を掴むまでの経過と、この曲をはじめこの時期のキーパーソンとなったエルビス・コステロとの関係について解説をしてゆきます。「フラワーズ〜」期の曲の紹介は初めてですしね。
ジョン・レノンを失い、続いてウイングスを失った'80年代のポールは、当初はよかったものの、その後はスランプの連続でした。アルバムはことごとく売れず、自主制作映画「ヤァ!ブロード・ストリート」は失敗、起死回生を計って最新鋭のエレクトリック・ポップに挑戦したアルバム「プレス・トゥ・プレイ」も結局のところ不振に終わりました。また、スティービー・ワンダーやマイケル・ジャクソンを皮切りにエリック・スチュワートなどと共演・共作もしましたが、彼らはポールにとってしっくりくるパートナーではなかったようで、結局は(パートナー関係が5年ほど続いたエリック・スチュワート含め)かつてのジョン・レノンのような刺激的なパートナーにめぐりあえずにいました。アルバム制作面でも、ジョージ・マーティンとのコラボレーションから、デヴィッド・フォスター、ヒュー・パジャム、フィル・ラモーンと様々なプロデューサーを迎えた試行錯誤が繰り返されましたが、いずれもポールの納得するものとはなりませんでした。
そんな中、ポールは1986年の「プリンシズ・トラスト」において久しく立っていなかったステージで演奏したことをきっかけに、ウイングス以降停止していたライヴ活動を再開させようと思い立ちます。そして、そのためのアルバム制作に必要な、新たな作曲パートナーとしてポールが電話をかけたのが、エルビス・コステロだったのです。
エルビス・コステロの本名はデクラン・パトリック・マクマナス(作曲クレジットではこの名前が使用されている)。英国・ロンドン出身で、1977年に本格的にデビュー、パンク調の作品は早くから注目されていました。その後、バックバンド「ジ・アトラクションズ」との共同名義でいくつか作品を出した後、ソロ名義で活動しています(最近は新たなバックバンド「ジ・インポスターズ」との共同名義でも活動)。独特の眼鏡顔がなんともユーモラスな風貌のコステロですが、ポールと初めて会ったのは1979年末の「カンボジア難民救済コンサート」での共演と思われます。そして1987年、ポールからコステロの元に作曲パートナーにならないか、という誘いが来たのです。
こうして、ポールの会社MPLなどを舞台にした2人の共同作業が始まったわけですが、ポールが驚いたのはコステロの辛辣で大胆な態度でした。きっとポールもコステロの性格を知らずに共作を持ちかけてしまったのでしょう。結局は「うれしい誤算」だったわけですが、きっと戸惑った場面が多々あったことでしょうね(苦笑)。というのも、コステロは相手がポールであろうと誰であろうと遠慮なく自分の意見をぶつけてきたからです。これは、前回の『Press』で触れたようなエリック・スチュワートの「裸の王様」状態とは一線を画します。コステロにとっては「天下のポール・マッカートニー」だからといって間違いを正すことにためらうことは、決してありませんでした。有名なエピソードですが、時にはポールの持ってきた曲を「ゴミだ」と言い放ちさえしました。コステロは自分の意見を絶対貫こうとする考えの持ち主でもあり、決してポールに甘くは接しませんでした。「裸の王様」ポールのプライドはずたずたに傷つけられたものと想像できますし(苦笑)、これまでの共作者とは全く違う態度で扱いに大変困ったと思いますが、しかしこれが本来の「パートナー」のあるべき姿。こうポールは悟ったのです。そして、ポールはそんなコステロをかつての辛辣なパートナー、ジョン・レノンの姿を重ね合わせて「ジョンとの共同作業を思い出すよ」と語っています。コステロの存在・意見は、方向性を失っていたポールの音楽に活を入れる結果をもたらし、それが絶妙なコンビネーションとして楽曲に反映されたのです。無二の親友にして最高のパートナーであったジョンには遠く及ばないものの、コステロはポールにとってはいい刺激になったようです。スタジオにいるみんなが「よい、よい」とおだててきた'80年代ポールにおいて、唯一「だめなものはだめ」と言い切れたのが、コステロですから。

ポール・マッカートニー(右)と共演するエルビス・コステロ(左)。
結果、ポールとコステロの共作は10数曲にのぼり、うち12曲がこれまで公式発表されています。1987年にポールのシングル「Once Upon A Long Ago」のB面で発表された『Back On My Feet』を皮切りに、コステロのアルバムに5曲、ポールのアルバムに6曲が収録されています。共作とはいえ、すべての曲のレコーディングに2人が揃って参加していたわけではなく、実際2人が共演したのは5曲にとどまります(ポールのアルバムでは3曲)。今回紹介する『My Brave Face』には、残念ながらコステロは参加していません。
いきなりマニアックな話ですが(笑)、この曲をはじめ、未発表曲含めた多くの「マッカートニー=マクマナス」作品をポールとコステロがデモ・レコーディングしている様子を、ブートで聴くことができます(「The McCartney/Mac Manus Collaboration」など)。時期は1987年の夏〜秋ということですから、まさにポールとコステロが顔をつき合わせて共作に励んでいた時期の音源ということになります。ここでは全曲が2人のアコギ弾き語り形式のシンプルなものであり、公式発表されたものとは一味違う、手作り感が伝わってきます。また、ポールとコステロのデュエットスタイルがほぼ全編で堪能でき、対等に渡り合った2人の息の合ったハーモニーを聴くことができます。ポール側で発表された『Don't Be Careless Love』『The Lovers That Never Were』などは、公式発表版よりいいなぁと思いますし、コステロ側で発表された『So Like Candy』『Playboy To A Man』なども聴けます。未発表曲『Twenty-Five Fingers』の軽快さは痛快です。そんな中、現在聴ける『My Brave Face』のデモは2種類あります。1つは先述のようなアコギ弾き語り形式のデュエットスタイルによるもので、公式発表版と印象が違って驚きです。こちらの方がヴォーカルが溌剌とした感じがします。2人の息の合い方はお見事です。公式でも聴きたかったと思わせるハーモニーです。コステロの渋みがいい感じ。歌詞はこの時点で完成しています。もう1つは、ラフなバンドサウンドにのせてコステロが歌うもの。オリジナルよりテンポが速く、コステロが途中で笑い出してしまい歌うのをやめています(演奏もそこでフェイドアウト)。録音中のリラックスした1こまを垣間見ているかのようで面白いです。
なお、ポールとコステロはその後も親交が続き、1995年には「ポール・マッカートニーとその仲間たちの夕べ」で共演、共作曲やビートルズ・ナンバーを演奏しています。1999年に開催されたポールの愛妻リンダの追悼コンサートでも共演を果たしています。


さて、この曲のレコーディングは、ポールがライヴ活動再開のために制作したアルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」のセッションで行われました。じっくりと制作された「フラワーズ〜」の一連のセッションでは始めの方に取り上げられたと言われていて、時期的にはコステロとのデモとそれほど遠くないと思われます。「フラワーズ〜」セッションでは、前作「プレス・トゥ・プレイ」などの失敗を教訓に、曲ごとにふさわしいプロデューサーを選んでいますが、この曲ではミッチェル・フルームとニール・ドーフスマンが共同プロデューサーとなっています。このアルバムで取り上げられたコステロとの共作はフルームとの共同作業で手がけられています。先ほども触れたように、この曲にはコステロは参加していません(「フラワーズ〜」での共作では唯一)。
曲調は、穏やかな曲調が目立っていた'80年代ポール、特に複雑化していた「プレス〜」期の作風や、ポールが「老けた」かのような直近のシングル『Once Upon A Long Ago』とは一線を画したもので、久々に登場した単純明快で軽快なポップ・ナンバーでした。相変わらずのポールのポップ節が復活したことに、当時のファンの方はきっと安心したことでしょう。ライヴ映えする爽やかな曲調で、コンサート再開を意識して作られたことは明らかです。ポール自身「'60年代のフィーリングだよ」と語っているように、どこかビートルズ時代(特にライヴ活動をしていた頃)の作風を思わせますが、これは長年避けてきたビートルズ・ナンバーを見直したということも関係あるかもしれません。ジョンに似たコステロとも出会い、徐々に過去の思い出を素直に振り返ることができたポールは、この後コンサートで多数のビートルズナンバーを取り上げることになります。この「コンサート回帰的」「ビートルズ回帰的」なサウンドは、「フラワーズ〜」からのシングルカット『This One』や『Figure Of Eight』にも通じ、この時期のポールの指標とも言うべきものでした。そして、その回帰に大きく寄与したのがコステロというのは間違いないようです。全体的に明るく元気よく仕上がっていますが、途中に陰りを見せるメロディが登場するのはコステロの作風が影響しているのでしょうか?ほんのり苦味も覚えるのも、コステロとの共作に特徴的です。


ヘフナー・ベースで演奏するポール。[(左)プロモ・ヴィデオ、(右)「夜のヒットスタジオ」]
演奏面で特筆すべきは、この曲のレコーディングにおいてポールがひさしぶりにヘフナーのヴァイオリン・ベースを復活させていることでしょう。ビートルズ・ファンの皆さんにはもう説明不要の、ポールの初期ビートルズにおけるトレードマークです。ビートルズ解散後、ウイングスやソロにおいては出番のなかった(『Coming Up』のプロモのみ?)ヘフナー・ベースですが、ここに来て復活を遂げたのは、実はこれもコステロの一言だそうです。「僕はあの音が好きなのに」と助言したそうですが、ちょうどビートルズを見直しつつあったポールにとってこの発言はビートルズ肯定への大きな自信につながったことでしょう。ここでもコステロの存在がよい方向に作用しています。この後、ポールがヘフナーを好んで使うようになるのは周知の通りですね。この曲では久々に演奏できたうれしさか、跳ねるようなメロディラインが印象的です。他にも、12弦ギターが登場するなど何かとビートルズをほうふつとさせる演奏で、間奏のアコギソロもそれっぽいです。
他に、イントロに渋めのブラス・セクション(サックス)が入っていたり、ミッチェル・フルームが演奏するキーボード類も多少使われてはいますが、あくまでも最低限にとどめており、「ビートリー」な演奏を保っています(なお、タンバリンはポールの演奏だそうですが、ここらへんもビートルズを思い起こさせます)。興味深いのは、ギターにヘイミッシュ・スチュワートとロビー・マッキントッシュ、ドラムスにクリス・ウィットンが参加している点。この3人はアルバム完成後にいずれもポールのツアー・バンドのメンバーに抜擢され、ポールの「復活」を印象付けた一連のワールド・ツアーに赴くこととなります。さらにクリス以外は1993年のアルバム「オフ・ザ・グラウンド」とそのアルバム・ツアーまでポールと活動を共にする仲間となります。そう考えると、コステロとの共作ながらポールのツアー・バンド(通称「ランピー・トラウザーズ」)の色が強い演奏ですね。


この曲のレコーディングに参加したヘイミッシュ・スチュワート(左)とロビー・マッキントッシュ(右)。そのままポールのツアー・メンバーに。
ポールのヴォーカルスタイルも、久々に溌剌としています。特に発表順に聴いてみたらその差は歴然でしょう。だって、直近の新作が老けた感じの『Once Upon A Long Ago』ですから(笑)。のっけからポールの多重録音によるタイトルコールという構成が非常に新鮮で爽やかです。この辺りも、ビートルズナンバーを否応なく思わせますね。ヴォーカル、コーラスはすべてポールの多重録音らしいですが、前年までの不振はどこ吹く風といった感の元気いっぱいの歌声(後半にはシャウトっぽくも歌われる)は、この曲の大きな魅力のひとつですね。ポールの「復活」を告げるにはあまりにももってこいです。アルバムのオープニングにもまさにうってつけです。
面白いことですが、ポールとコステロの共作には共通点がよく見られます。3拍子の曲が多いのもそのひとつですが、歌詞もそのひとつ。この曲などの歌詞では単なるラヴ・ソングというよりは、「キャラクター」に焦点を当てた作風が目立ちます。しかも、常のポールの楽曲にあるような単純にハッピーな物語ではなく、コステロ節が影響したかのような、どこか屈折したような感のある物語が展開されているのです。『Mistress And Maid』の夫婦、『Back On My Feet』の公園の男・・・。いずれも普段のポールなら考え付かないであろう題材です。そして、この曲及び『Don't Be Careless Love』では、情けない感じの主人公が登場します。普段のポールだったらこの手のラヴ・ソングは楽観主義一色に染まるところですが、失恋に自分の過去の生活を重ねたこの曲の歌詞はなんというか・・・苦味が効いています。どこかほろ苦さを味わえるのです。過去を振り返る、という点では「ビートルズ回帰」にもつながるものがありますが、「都会の派手な生活になじもうとしたけど、だめだった」というくだりは、'60年代のポール自身の姿のようです。


ここからは補足的な説明を。冒頭でも触れたように、この曲がアルバムからの先行シングルに選ばれ、アルバム発売1ヶ月前の1989年5月にシングル発売されています。英国では「Once Upon A Long Ago」(1987年)以来、さらに米国では「Only Love Remains」(1986年)以来のシングルとだけあって、否応にも注目を集めました。チャートでの結果は冒頭に示したとおりで、これまでのポールにしてはそこそこの結果でしたが、これは時代の変化によるヒット曲の質の変化が要因と思われ曲自体が評価されなかったわけではないでしょう(その証拠にアルバムは英国1位の大ヒット!)。「Once Upon A Long Ago」以降、CDシングルも発売されますます多様となったポールのシングルですが、このシングルもB面・カップリングの『Flying To My Home』の他に、12インチ・CDシングルには当時ソ連のみで発売されていたアルバム「CHOBA B CCCP」より2曲が収録されていました。
シングル発売されたためプロモ・ヴィデオも制作されますが、これがまた非常に印象に残るものです。特に我々日本人にとっては(笑)。というのも、このプロモには日本人が登場しているからです。しかも、その日本人はポールやビートルズのグッズなら何でも持っているという非常にマニアックなコレクターで、ポールのヘフナー・ベース(まさにこの曲で使用されているベース!)をスタジオに忍び込んで盗んだ挙句逮捕される、という設定なのです!これは、当時から「1980年の日本での逮捕劇を意識した!?」と大騒ぎになったそうです。日本人にとっては皮肉たっぷりの内容で、なんだか複雑な気持ちにもなりますが、ポールいわく「監督(ロジャー・ラング)のアイデアで、たまたまスタジオに日本人俳優がいたので起用した。日本人じゃなくてもよかった。誤解を招かないようコレクターを逮捕する警官も日本人にしたよ」とのこと。確かに警官役も日本人ですが、どう見てもポールの「日本での逮捕に対する反撃」にしか取れません(苦笑)。よほど1980年の日本での逮捕劇が気に食わないのか、ポールは・・・。『Frozen Jap』で誤解を招いた教訓をよそに・・・(苦笑)。一説には、当時バブル経済期の真っ只中だった日本人が「金にまかせてあらゆるものを買いつくす」という偏見を受けていた影響があるのでは・・・という意見も聞かれますけど。いずれにしても、ポールの日本への「こだわり」が強く表れ、親しみがわくようなわかないような、といった作品です。
プロモはのっけからこの日本人コレクター(しかもどアップ!)から始まります。しかも、日本語で「私はポール・マッカートニーのものに関する収集家として〜」うんぬんとその情熱を語り始めるのですから滑稽極まりないです(日本語の台詞は英語で字幕がついている)。同時に「日本人はこんな風に見られていたのか・・・」という気持ちにもなります。ポール以上に個性をアピールしているこの日本人俳優、情報が全くないのですが一体誰なのでしょうか?とかく、このコレクターが「最新の取得物」として取り出したヴィデオが、この曲の演奏シーン、ということになります。その演奏シーンにあいまって、彼とその仲間たちがポールのグッズを次々と盗んでゆく痛々しい(苦笑)光景が挿入されますが、これがポール・ファン、ビートルズ・ファン必見の映像となっています。なぜなら、ビートルズやウイングスのレアな映像、グッズが目白押しだからです!中には「サージェント・ペパー」の衣装(ポールが着ていたもの)、ビートルズの前身・クオリーメンの名刺なども登場します(恐らくポールがこのプロモのために引っ張り出してきたのでしょう)。映像では、ウイングスの1975年頃の映像(ジョー・イングリッシュが映っている!)も興味深いですが、なんといっても初期ビートルズのレア映像がたくさん出てきて、ポールの「ビートルズ回帰」がここでも打ち出されています。他の元メンバー(ジョージ・ハリスン、リンゴ・スター)はこのプロモを見てどう思っただろうか・・・。そしてエンディングで、日本人コレクターはその異常なコレクター魂の末にポールのヘフナー・ベースを盗み出したものの、そこで日本人警官に御用となってしまいます(笑)。しかも、最後に堂々と映し出される監視カメラが某「日本家電メーカー」製という凝りようには参ってしまいます(笑)。最後の最後に登場するポールの満面の笑みが「どうだ、参ったか!」という日本人へのメッセージに見えてしまうほど(笑)。まぁ、こんな感じの、ビートルズ・ファン必見、でも日本人ファンにとっては複雑な内容のプロモです。出演した日本人俳優も、ポールの様々なグッズに実際に触れることができてさぞうれしかったことでしょう。彼がポール・マッカートニーやビートルズのファンであればの話ですが(日本人コレクターの口調で)。
一方の本編である演奏シーン(本来ならこちらが中心に語られるべき・・・)は、白黒映像を中心としていて時折カラー映像が混じるというもの。スタジオで後のツアー・バンドと一緒にポールが演奏する光景ですが、レコーディングに参加していないポール・“ウィックス”・ウィッケンズの姿もあり、ツアー・バンド全員が揃う形となりました。各メンバーは1人ずつ必ずスポットが当たるようになっていて、アップで映し出されています。各自なかなかクールに決まっていますが、やはり注目すべきはポールでしょう。レコーディング同様、ヘフナー・ベースを演奏しています(プロモでは『Coming Up』以来)。ビートルズ以来の光景に「懐かしい!」と思ったファンの方も多いのではないでしょうか。しかし、プロモでコレクターが盗み損ねたのがこのへフナー・ベースと考えると、カメラに向かって堂々と見せ付けるポールが「どうだ、僕のベースは盗めまい!」と誇示しているようでなんとも複雑ですな(苦笑)。このページで、いくつかプロモからのシーンを挙げておきますので参考にしてください。プロモ集「The McCartney Years」にも収録されているので入手は簡単です。


アルバム「フラワーズ〜」の成功後、ポールはレコーディングを共にしたミュージシャンたちと一緒に、念願だったワールド・ツアーに出ます。日本での逮捕劇以来久々のコンサート・ツアーとなったことは言うまでもありません。ビートルズ・ナンバーも数多く取り上げられたこのツアーは、悲願の日本公演があったことでも知られていますね(それを控えていたというのに、上記のプロモを作ったポールの神経ときたら・・・)。ポールの自信を表すかのように、ニュー・アルバムの曲も何曲か演奏されましたが、当然ながらこの曲も含まれました。このツアーでの演奏は公式ライヴアルバム「ポール・マッカートニー・ライヴ!!(Tripping The Live Fantastic!)」に収録されています。しかし、当時の最新作からの最新ヒットというのに、歓声が割かし小さく感じられるのは気のせいでしょうか(汗)。ビートルズ・ナンバーの方がよっぽど歓声が大きい気がします。確かに、ライヴ盤を聴く限り、スタジオ版に比べてちょっとラフな感も否めませんが・・・。この後のコンサート・ツアーでは演奏されていなく、いい曲だけに残念です。ちなみに、コステロも当時のコンサートでこの曲を取り上げていたようです。
また、この曲は当時盛んにポールが宣伝に活用していた音楽番組出演時にも演奏されていました。中でも当時の日本のファンの皆さんにとっては懐かしいと思われるのが、日本の音楽番組「夜のヒットスタジオ」でしょう。洋楽も盛んに取り上げていたこの長寿番組ですが、ポールも1987年と1989年の2度出演しています。うち、後者で当時の新曲『My Brave Face』と『This One』を披露したのです。日本のファンにとっては、日本でのコンサートがなかっただけにヘフナー・ベース片手に歌うポールのライヴ映像はうれしかったことでしょう。しかし、皆さんお気づきかと思いますが、映像はスタジオライヴ(英国のスタジオにて収録)なのに、音はオリジナルの演奏そのままという有様。しかもこの曲にいたっては、出だしの印象的なコーラスをカットしてのスタート・・・。ちょっと拍子抜けした格好となっています。なぜライヴ演奏そのままの音で放送しなかったのかは理解できません・・・。以下のような感じです。


私は、ポールとコステロの共作の中ではこの曲が一番好きですね。『Don't Be Careless Love』も相当好きなのですが・・・。やはり、コステロの味が加わりつつも、基本はポールらしさいっぱいのポップナンバーだからです。コステロ色が強すぎないのがミソですね。リアルタイム世代の方ほど強い思い入れというものは(残念ながら)ないのですが、後追い世代でも十分とりこにしてしまう、ポール節たっぷりのキャッチーさがありますね。あとは、歌詞も好きですね。こういう情けない感じの主人公というのも、ポールには珍しいと思います。『Don't Be〜』もかなり情けないですが(笑)。なぜか共感できてしまう私も情けないですな(汗)。もっとヒットしてもよかったと思いますが、ポールのチャート上での「空白期間」もあったのでそれは酷な話でしょうか・・・。日本ではプロモや「夜ヒット」、さらに悲願の来日で話題性は十分でしたが・・・。プロモの内容が災いしたか?(笑)
この曲は、ポールの近年(といってもだいぶ昔ですが・・・)の楽曲では代表曲とも言えそうですが、各種ベスト盤の選曲範囲が原因でベスト盤には未収録です(日本限定発売の「ザ・グレイテスト」は除く)。しかし、ポールが「生き返った」時期の、ビートルズ回帰指向とエルビス・コステロとの絶妙なコンビが同時に味わえるこの曲、そしてこの曲と同様並々ならぬ完成度の「フラワーズ・イン・ザ・ダート」各曲はぜひ聴いていただきたいですね。後追いファンでもその魅力は十二分に堪能できますよ。

さて、次回紹介する曲のヒントは・・・「プロテスト・ソング」。お楽しみに!!
(2008.3.09 加筆修正)
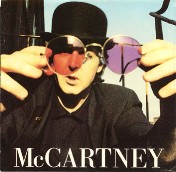
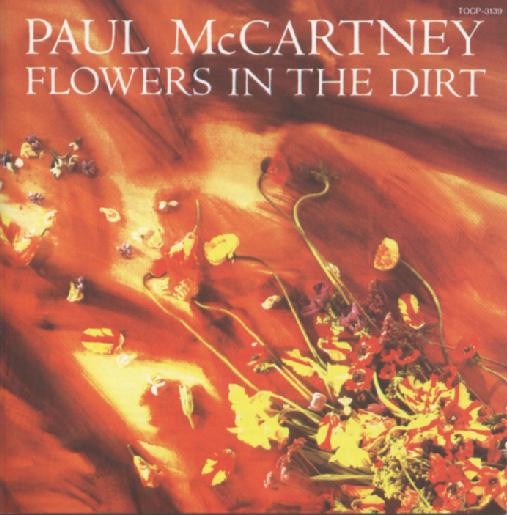

(左から)当時のシングル盤。B面・カップリングの『Flying To My Home』もかなり好きです。
アルバム「フラワーズ・イン・ザ・ダート」。ポールが「復活」を遂げた名盤。/ライヴ盤「ポール・マッカートニー・ライヴ!!」。ライヴ・ヴァージョンはこちらでどうぞ。