
Jooju Boobu 第10回
(2005.4.10更新)
Press(1986年)

「Jooju Boobu」は今回で10回目。もちろん、紹介する曲も今回で10曲目となります。このコラムでは大体(更新した時のですが)私のお気に入り順に紹介していますが、10曲目に紹介するこの曲もかなりのお気に入りとなります。これまでも、『Only Love Remains』『Angry』を紹介している私の愛聴盤、1986年のアルバム「プレス・トゥ・プレイ」に収録された、その名も『Press』です。アルバムタイトルの由来となっている通り、このアルバムの核となるような、そんな1曲です。既に3曲目の紹介となることからも、私がいかに「プレス・トゥ・プレイ」がお気に入りかがお分かりになるかと思います(笑)。今回はその中でも割かし普通のファンの間でも人気の高い、この『Press』を語ります。

『Only Love Remains』『Angry』のページでも既に触れているため、重複になってしまいますが(汗)、一応アルバム「プレス・トゥ・プレイ」についておさらいを。「そんな説明聞き飽きた!」という方は読み飛ばしてください(笑)。「プレス・トゥ・プレイ」は、'80年代における低迷期に入っていたポールが、起死回生を図るべく、当時の売れっ子だったヒュー・パジャムをプロデューサーに迎え、'80年代のパートナーだった元10ccのエリック・スチュワートと共同作業したアルバムです。パジャムをプロデューサーに迎えていることからも、ポールが当時の最先端の流行音楽を強く意識していたことは明らかで、結果として常のポール色は薄れ、パジャム色の強い打ち込みサウンド中心のエレクトリック・ポップが特徴的となりました。ポールのこれまでの系譜からしても非常に異色で斬新な意欲作だったのですが、発売後旧来からのファンの拒否反応を引き起こし、新たなファン層もつかめず、歴史の闇に葬り去られてしまう悲しいアルバムとなってしまったことは、以前も述べたとおり。そして実はポールがこき下ろすほどそんなに悪いアルバムではないことも(以下略)。
結果的にパジャム色が濃くなってしまいましたが、エリック・スチュワートがポールと本格的にタッグを組んだのはこのアルバムとなります。アルバム収録曲の実に半分以上がポールとエリックの共作でした。2人のポップ職人が作り上げたポップやロックの数々は、非常にメロディアスで印象的な響きのものが多くあります。そんな中、今回紹介する『Press』は純然たるポールの曲です。『Only Love Remains』もそうですが、エリックの力がなくともキャッチーで秀逸なメロディを書いてしまうのは「メロディ・メイカーの大御所」ポールのなせる業でしょう。創作意欲が強かった時期ですし、エリックの才能から刺激も受けていたでしょうし、このアルバムではポールの単独作曲の曲も共作曲に負けじとそのメロディアスな魅力を見せています。サウンドのエレクトリック・ポップ化と共に、この辺はエリックの立ち位置が非常に微妙になってしまった感が否めないですね・・・(汗)。結局エリックがいなくてもよかったような仕上がりになってしまいましたから・・・。エリックいわく当時のポールは「裸の王様」状態だったようで、共作活動ではある程度の刺激を与えることはできても、セッション自体には特に発言権を与えられることなく、結果的にポールの独壇場となってしまった・・・ということですね。そんなサウンドが、このアルバムにはあふれているというわけです。
さて、そんな「裸の王様」ポールが生み出した「PTPサウンド」のため、この曲の作風も、聴いてみるとそれまでのポールの曲とは違った趣があります。他のアルバムでの同系列の曲と聴き比べれば誰しもその肌触りの違いに気づくはずです。「プレス・トゥ・プレイ」全体に通じますが、メロディよりもリズムを優先したかのような、リズミカルなアレンジが耳につくからです。「メロディ・メイカー」として定評の高いポールからしては異例のアプローチで、これが「まずメロディありきのポールが、なぜ・・・」というファンの拒否反応の要因となっています。'80年代中期頃から、こうしたリズム重視のエレクトリック・ポップが巷にあふれるようになり、誰もがこうした音作りを取り入れていて、ポールも時代に追いつかんとヒュー・パジャムのサポートを借りて挑戦したわけですが、他アーティストと同じく、ポールの場合も必ずしも上手くいったとは言い難いのが現状です(PTPマニアである私にとっても・・・)。この曲はそれほどメロディがないがしろにされているわけではありませんが(最たる例は『Pretty Little Head』『Talk More Talk』辺りか?)、打ち込みドラムスも含めた力強く一定のリズムを保ったドラムビートが「リズム中心主義」を際立たせています。この曲の場合、メロディがよいだけに、一定で若干大仰なドラムスのリズムとの相性の悪さを感じてしまい、そこが非常に残念な点です。また、コンピュータ・プログラミングによる打ち込みサウンドが流行していたのもこの時期で、ポールもこの曲をはじめ「プレス〜」ではこうした機械的な打ち込みサウンドをオーバーダブを重ねて多用しています(パートナーのエリック・スチュワートはこうした音作りを望んでいなかったそうです・・・)。この曲でも、ギターやベースといった生の楽器より、キーボード類の音が目立ちます。オーバーダブを重ねているため、いろんな種類のシンセの音であふれ返っています。こうした音作りはいかにも当時のアレンジですが、今聴くと「チープだ」「大仰だ」という評価もあるようです・・・。確かに、人工的な響きは否めません。現在の音楽シーンにもつながるような音作りの原型になるような音作りは、私のような後追い世代にはさほど違和感を覚えませんが、当時リアルタイムで聴いた方は、「あのポールが、なぜ・・・」と強い衝撃を受けたことでしょうね・・・。


時代を意識したポールの「リズム中心主義」と「シンセの多用とオーバーダブの繰り返し」は、この曲に「いつものポールではない」イメージを与え、メロディとアレンジとのギャップに違和感を覚えさせますが、実はお聴きになれば分かるとおり、曲そのものはいつものポールらしい楽観的なポップナンバーです。恐らく、アルバム中『Only Love Remains』と並んで最もメロディアスではないでしょうか。「幸せいっぱい!」といった気持ちをそのまま表現したかのような、うきうきするようなメロディはかつての『Listen To What The Man Said』のようなポップセンスを感じさせます。後半のコーラスフレーズの覚えやすさはアルバム随一で、これもポールならでは。やっぱり、どんな音を取り入れようと、リズムが重視されようと、根底は「天才メロディ・メイカー」であることの証明といえるでしょう。それだけに、打ち込みサウンドを極力控えて聴きやすい『Only Love Remains』に比べて、派手なドラムビートとシンセをフィーチャーしてしまったこの『Press』は、秀逸なメロディが聴きにくいアレンジとなってしまい、そのよさがなかなか伝わりにくく残念な所です。リズムは「うきうきした気持ち」を表現する努力をしているように聴こえますが、力強すぎですよね・・・。
演奏面を見てみましょう。やはり機軸はリズムを強調した力強いドラムスでしょう。いかにも当時といった、大仰なフィルインも交えた演奏で、後半のドラムソロの展開は、当時としては典型的かもしれません。意外と多いのがギターで、ポールとエリック、カルロス・アロマーの3人による演奏です。イントロのメロディはなんとなくエスニックな感じも醸し出していて、個人的には面白いと思っています(後でちょっと触れます)。2回登場する間奏のエレクトリック・ギターのソロはポール自らが弾いています。ポールらしく、ストレートなフレーズです。ただ、例のようにリズムが強調されているのでギター・プレイがあまり目立たなくなってしまっているのが残念。キーボード類も多く入っていて、いかにも当時を思わせる音もありますが、こうした音によってますます統一感がなくなっているように聴こえ、混沌としてしまっているのが残念。全体的にうきうきした明るい雰囲気にはなっていますが、いまいちピンとこない演奏となってしまいました。当初エリックが望んでいたようなストレートなアレンジだったら、どうなっていたことだろう・・・と思ってしまいます。
サウンドの反面、そしてメロディと同様に、歌詞ではいつものポール節が光っています。メロディの跳ねたような感じに合わせて、「ダーリン、君のこと大好きさ」「僕に愛してもらいたいなら、抱いてって言ってよ」など、芽生えた恋にうきうきしているハッピーな雰囲気たっぷりです。タイトルであり、アルバムのタイトルの由来にもなった「press」には、「押す」という意味がありますが、文脈から考えて多分「抱く」でしょう(と、私は考えています)。また、中盤に登場する「オクラホマはこんなんじゃなかった(Oklahoma was never like this)」というくだりは特別意味はないとのこと。「地元や昔の場所へのこだわり」だそうですが、意味不明です(苦笑)。意味のない歌詞は当時のポールの詞作の影の特徴ともいえ、『Talk More Talk』『Stranglehold』『However Absurd』に顕著に登場します。この意味不明なフレーズから発展した後半の“Never like this(こんなんじゃなかった)”のコーラスが楽しいです。この後半部分では、ポールがアドリブ・ヴォーカルを炸裂させ、一種のハイライトといえるでしょう。この部分は聴いていて非常に楽しいですね。ポールのヴォーカルも、終始楽しそうです。イントロではカウント(Say 1, Say 2, Say 3)をきめています。ただ、イントロなど随所に入る低い声は少し違和感を覚えます・・・(次に語るオリジナル・ヴァージョンには入っていない)。


さて、ここで(後追い世代には)驚きの事実。実は、アルバム「プレス・トゥ・プレイ」に収録されているあの音源は、リミックスなのです!よーくアルバムのクレジットを見れば分かりますが、Bett BevansとSteve Forwardの2人が手がけたリミックス(以下、Bevans/Forward Remix)なのです。では、オリジナルは・・・といえば、ちゃんと公式発表されています。後述するシングルにのみ収録されたヴァージョンです。ここでは、アルバムヴァージョン(=Bevans/Forward Remix)よりもシンプルな演奏で、比較的聴きやすくなっています。プロデュースは当然ヒュー・パジャムですが、「プレス・トゥ・プレイ」本編に比べると圧倒的にシンプルです。荒削りながらも、生楽器の比率が高くなっていて肌触りが全然違います。特に、Bevans/Forward Remixでは大仰だったドラムスが圧倒的に控えめになっています。恐らくジェリー・マロッタの生演奏なのでしょう、無駄な力強さがありません。リミックスでドラムスを差し替えて、あの大仰なアレンジになった・・・という経緯ですね。その他、キーボード類も減り聴きやすさを上げています。そのため、ギター色が濃くなっています。何のエフェクトもかけていないイントロの音色は、その違いに驚くことでしょう。エンディングには妙にエスニックなギターソロも入っていて、これも驚きです。構成面でも、Bevans/Forward Remixより間奏が1回が少なく、すっきりした構成になっています。リミックスが間延びした感があるのは、構成を変更したためだったのです。ヴォーカルは同じものですが、後半のアドリブが若干違います。Bevans/Forward Remixに比べて圧倒的に聴きやすく、生楽器の使用度が高めで控えめな演奏で、好感が持てるこのオリジナル・ヴァージョンは、未CD化(「プレス・トゥ・プレイ」の一部プレスに収録されていたという伝説があるようですが・・・)。後述するシングルのB面だった『It's Not True』と同じく、アルバム収録のリミックスよりも断然聴きやすいシングル収録のオリジナル・ヴァージョンが、現在未CD化で入手困難というのは納得いきません。『It's Not True』については特に!ですが、このお話はその曲が紹介された時にでも・・・。
この『Press』はアルバム発売前に先行シングル発売されています('86年7月)。やはり、一番キャッチーでポップな所が売れ線だとポールも考えたのでしょう。エリックと組んだセッションからのファースト・シングルがポールの単独作・・・という辺りもエリックの存在がこの時点で薄くなっていたことを暗に象徴しているようです。前年の'85年にはシングル「Spies Like Us」の発売だけで、いよいよ意欲作の発表・・・ということだけあって、久々の新曲にファンの関心は高まったはずです。が、蓋を開けてみれば、英国で25位、米国で21位。普通ならまずまずの結果でしたが、以前は毎度のようにチャートをにぎわせたポールとしては低すぎの結果でした。その理由は、「ポールらしくない音作り」が従来のファンを困惑させたからに他ありません。ポールの「アーティスト・パワー」と曲のメロディアスさに救われ、まだ20位代の結果で収まりましたが、直近までTOP10チャートの常連だったポールがファースト・シングルからコケていることは作風の変化に対するファンのショックがいかに大きかったかを物語っているようです。この衝撃は、その後のアルバム発売でさらに強まり(全米30位止まり・・・)、さらにその後のシングルカットでポールはこれまでにない大不振を見ることとなります(こともあろうか『Pretty Little Head』をシングルカットしてしまいましたからねぇ)。ポールにとっての起死回生の意欲作は、全体的に見ればポール・ファンの心を掴むことはなかったのです(好んで聴いた少数派もいるとは思いますが・・・)。その後、この時期はポールの「黒歴史」とされてしまい、そのレッテルはポール本人をも巻き込んで今に至ります(悲しい・・・)。この不振真っ只中に切り込んでいったのが、極上ポップのこのシングルと考えると、複雑な気分です。他の時期だったら、絶対TOP 10入りしそうな曲だと思いますが・・・。

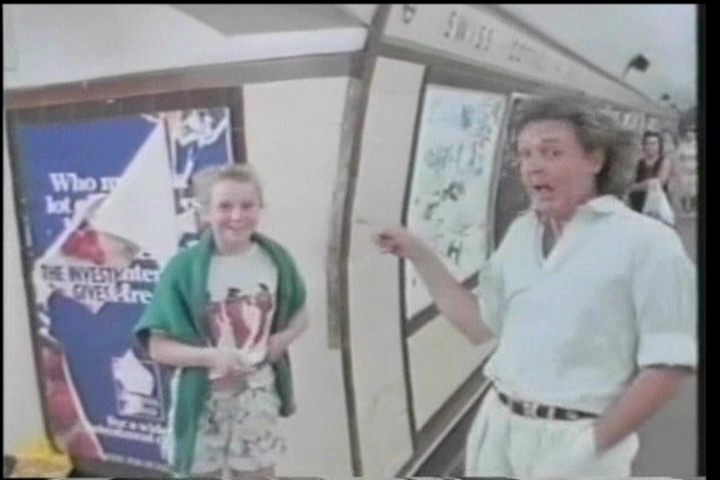
折からのリミックス・ブームにあやかって、「プレス・トゥ・プレイ」期には多くのフォーマットでシングル発売がされ、多くのリミックスが収録されました。中でもこのシングル「Press」は、多彩なフォーマットで発売され、ファンを泣かせたのです(1990年の「Figure Of Eight」の方がすごいですが・・・)。ポールの歴史でも最も発売形態が多彩なシングルの1つでしょう。熱心な「プレス〜」ファンである私でもその全容が掴みきれないままです。まず、7インチシングルが発売され、A面にはヒュー・パジャムによるオリジナル・ヴァージョンが、B面には『It's Not True』のオリジナル・ヴァージョンが収録されていました。しかし、その直後にA面がBevans/Forward Remixのショート・ヴァージョン(video edit、後述)に差し替えられた7インチシングルが発売されています。これと同日、12インチシングルが発売され、A面にBevans/Forward Remix(アルバム収録版と同じ完全版)と『It's Not True』のリミックス(これもアルバムと同じ)を、B面に『Press』の新たなリミックス(dub mix、後述)とアルバム未収録のインスト『Hanglide』を収録しています。さらに、6千枚限定の10インチシングルも登場し、ヒュー・パジャム・ミックスとBevans/Forward Remixの『Press』と、リミックスの『It's Not True』が収録されました。・・・と、こんな風に非常に頭が混乱する多彩ぶりだったわけです(汗)。この曲に関しても、「オリジナル・ヴァージョン」「Bevans/Forward Remix」「video edit」「dub mix」の4種類が公式発表されたことになります(さらに、プロモ盤には何種類かの別ミックスが存在するらしい)。その中で、CD化されているのはアルバムに収録された「Bevans/Forward Remix」のみ。残りはすべて未CD化です。
ヒュー・パジャムによる「オリジナル・ヴァージョン」と、「Bevans/Forward Remix」に関しては前述しましたので、残る「video edit」と「dub mix」に関して語ります。まず、「video edit」ですが、これはアルバム収録の「Bevans/Forward Remix」のショート・ヴァージョンです。具体的には、後半の2分42秒〜3分23秒と、3分45秒〜4分3秒をカットして、全体で約1分短い3分40秒ほどに短縮されています。ヒュー・パジャムの「オリジナル・ヴァージョン」とはまた違うカットの仕方ですが、間奏を1回減らし、終盤のくどいドラムソロをカットしたおかけでアルバムよりは聴きやすくなっています(ミックスは同じですけど・・・)。コーラスの入る後半部分にスムーズに入ってゆくのがなんだか爽快です。一方、12インチB面の「dub mix」は、いかにも当時のリミックスといった感の強いロング・ヴァージョンで、「Bevans/Forward Remix」を元にしています。ほとんど歌が入っていなくインスト状態が長く続くので、非常に聴きづらいと思います。また、フィルインの部分をくどく繰り返すなど、リミックス特有の大仰なアレンジが鼻につきます。いくらこの曲が大好きな私でも、あまり聴くことはありませんね(汗)。
この曲ときて、当時話題となったのがプロモ・クリップです(監督はフィリップ・デイヴィ)。「チューブ」の愛称で親しまれているロンドンの地下鉄に繰り出して撮影されたこのプロモは、地元・英国をはじめアルバムの宣伝に大々的に使用され注目を集めました。ポールは、当時巷にあふれていたプロモ・クリップが予算をつぎ込んで大掛かりな装飾を施したものが多いのに疑問を投げかけ「最近のプロモは曲の歌詞と無関係のものが多い」と嘆いていたようです。そこで、この曲のプロモを制作するにあたって「低予算で、歌詞を反映した内容を・・・」と考え、「all these people listening in(そこにいる人たちが聞き込んでいるのを見ると)」という一節から連想させて、地下鉄での撮影というアイデアを思いついたのが、そのゆえんだそうです。歌詞を元にプロモの内容を決めるのは、歌詞を大切にするポールらしいですね。低予算での撮影を目指したため、なんとポールは事前に撮影許可を取らずにゲリラ的に撮影を行っています(1986年6月16日)。ジュビリー線のチャーリング・クロス駅〜スイス・コテージ駅間で、途中ボンド・ストリート駅で下車しての(駅の看板で分かる)撮影でしたが、何の予告もなしに乗客がたくさんいる地下鉄に乗り込み、そこで『Press』を歌うという前代未聞の事態に、ポール自身も最初はすごくはずかしく思ったそうです(出だしの歌詞が「愛してるよ」ですから・・・)。もちろん乗客たちも、あの天下のポール・マッカートニーがカメラを従えて乗り込んできて歌い出す・・・となれば気が動転してしまうほど驚いたに違いありませんが、面白いことに意外とすんなり受け入れているようです。苦笑いで終わってしまう人もいますが(笑)、中には一緒に手をたたいて歌う人まで登場し、非常に打ち解けた雰囲気になっています。ポールも非常にリラックスしていて終始にこやか、指差しをしたり、ファンにサインをあげたり、途中下車中には大道芸人のヴァイオリン奏者にコインを投げ込んだりと楽しんでいます。周囲からすごく目立っていたこと間違いなしでしょうね。よいカットのみを編集しているので全貌は不明ですが、不快に思うような人が登場せず、まして警官が飛んでくることもなかったのは、英国のお国柄ゆえんでしょうか。もしこれが日本だったら、まず警官が飛んできて、その後罰せられるのでしょうが・・・(汗)。ポールのプロモでも、異色の制作過程ということで話題を呼び、比較的有名な方です。無事公式プロモ集「The McCartney Years」にも収録されました。和気あいあいした雰囲気が、曲のうきうきした感じにぴったりです。ただ、ポールにだいぶ老けた感が見て取れるのが・・・(苦笑)。ちなみに、使用されている音源は「Bevans/Forward Remix」です。そのためか、「Bevans/Forward Remix」は「Video Soundtrack」という別称があります。
映像としては、この他にスタジオで演奏する様子を捉えた映像がいくつか存在しています。中にはヒュー・パジャムのオリジナル・ヴァージョンがBGMという興味深いものもあります。ポールがエレキギター片手に1人歌うのですが、ギターを振り上げたり、カウントする仕草を見せたりとなかなかかっこいいです。以下のような感じです。


ほぼ全曲のアウトテイクが確認されている「プレス・トゥ・プレイ」において、この曲のアウトテイクも発見されています。「プレス・トゥ・プレイ」のアウトテイクは、公式発表されたヴァージョンよりオーバーダブが少なく、圧倒的に聴きやすい、曲の魅力を再発見できるものが多いですが、この曲もアウトテイクでは非常にシンプルなアレンジで聴きやすくなっています。シングル収録のヒュー・パジャムのヴァージョンに近いですが、それよりさらに輪をかけて音が薄くなっています。この段階で、既に基本的な構成や楽器アレンジは練られていて、間奏のギター・ソロやシンセのフレーズなどおなじみのメロディが登場しています。ただ、歌詞が一部完成していなかったり、2度目の間奏でも歌が入っていたりと、オリジナルと違う点もあります。後半はコーラス部分をポールが歌うものになっていて、終盤にアドリブヴォーカルが炸裂するパターンになっています。盛り上がりには欠けますが、この曲のポップなメロディを再確認できるアウトテイクです。
ポールが'80年代の低迷を抜け出さんと、最新鋭の流行音楽に果敢に取り組み、創作意欲を強くして起死回生を図るべく売り出した「プレス・トゥ・プレイ」は、ポールの期待とは裏腹にセールスでは大不振に陥りました。「ポールらしくない」という、常のポールとの激しいギャップゆえの失敗でしたが、本当に(ポール本人もそうですが)「駄作」と切り捨てていいような最悪な内容のアルバムでしょうか。確かに、アレンジ面でうまくいっていないものも散見されます。しかし、「ポールらしくない」という先入観を取り去って聴いてみると、意外にもメロディアスで多彩な曲が詰まっていて、意外にもポールらしいことに気づくことでしょう。特にこの曲や『Only Love Remains』などは、今聴いても遜色のない、マッカートニー・ワールドが炸裂した名曲です。ポールが時代を行き過ぎていたのでしょうか。今だからこそ、聴かれるべきアルバムだと思います。そしてこの曲も、今だからこそ聴かれるべきです。不運にもベスト盤などには一切収録されていませんが、ぜひアルバムの他の曲と同様聴いてみてください。あっさりしていて聴きやすいシングル収録のオリジナル・ヴァージョンが未CD化なのが残念ですが、ブートなんかでは簡単に入手できますのでそちらでもチェックしてみてくださいね。
さて、最後に個人的な感想などを。私は、一般的な評価と正反対に「プレス・トゥ・プレイ」は非常にお気に入りのアルバムなのですが(笑)、この曲はその中でも上位の方です。ポールと一緒に心が弾んでいくような雰囲気にさせてくれます。確かにリズムは強調されすぎの感もありますが、その分ノりやすいですね。最後のアドリブとコーラスの掛け合いが特に楽しいです。最近は「video edit」の方が聴きやすいかな・・・とも思っています。ヒュー・パジャムのオリジナル・ヴァージョンもいい感じですね。それにしても面白いのは、私が最初にこの曲を聴いた時、即座に頭の中でジャッキー・チェンが思い浮かび、それ以来この曲を聴くとジャッキー・チェンばかり思い出されるのですが、一体なんで・・・!?(笑)イントロがどこかエスニック風(=香港風)だから?そのイントロ(カウント含む)と“You can give me・・・”の部分が特にジャッキーが思い浮かびますね・・・。カンフーというよりも、「ジャッキーが米国の映画で英語の主題歌を歌っている」ような雰囲気がしてならないのです・・・(笑)。誰にも理解されずにいますが、個人的にはこの曲は聴き始め当初から現在に至るまで「ジャッキー・チェン」です(笑)。ライヴでも演奏してほしいですが、まぁ「プレス・トゥ・プレイ」を目の敵にするポールだから無理かな(苦笑)。
さて、おかげさまで今回でこのコーナーも10回目を迎えました。つまり、私のお気に入り上位10位が揃ったことになります(更新当時の話ですが)。その時々によって順位は変わることがありますが、大好きな曲が並んでいます。『With A Little Luck』『Waterfalls』『Only Love Remains』『Press』・・・こう考えると、あまりメジャーでないシングルナンバーが大好きだという傾向があるようにも思われます。予告しておきますが(笑)、今後もしばらくその傾向が続きそうなので売れなかったシングルナンバーを再確認しておくと次回紹介の曲が当たりやすくなるかも・・・!?

ということで毎回お楽しみの次回紹介する曲のヒントは・・・「エルビス・コステロ」。お楽しみに!!
(2008.2.10 加筆修正)
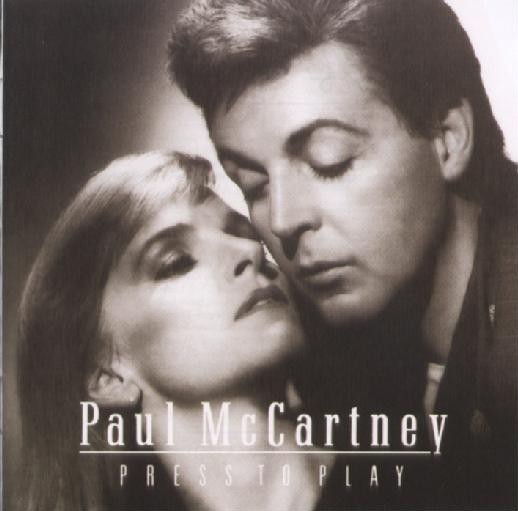
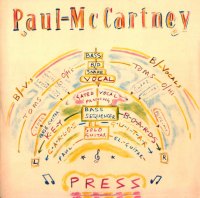
(左)アルバム「プレス・トゥ・プレイ」。エレクトリック・ポップに果敢に挑戦した意欲作。影の名盤!ジャケットが内容とミスマッチしている気が・・・(汗)。
(右)当時のシングル盤。多彩なフォーマットで発売され、数種類の別ヴァージョンの他、『It's Not True』(2ヴァージョン)と『Hanglide』(未CD化)も収録された。